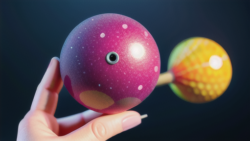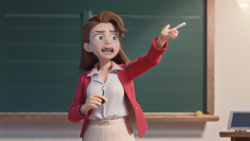その他
その他 知られざる染色体:常染色体
人間の体は、約37兆個もの細胞が集まってできています。一つ一つの細胞には核が存在し、その中には遺伝情報であるDNAが格納されています。DNAは、生命の設計図とも言える重要な物質です。
DNAは、ヒストンというタンパク質に巻き付きながら、クロマチンという糸状の構造を作ります。この構造は、まるで糸巻きのように、長いDNAをコンパクトに収納する役割を担っています。さらに、クロマチンは複雑に折り畳まれ、より凝縮された状態へと変化します。そして、細胞分裂の際にのみ観察される棒状の形になったものが、染色体です。
染色体は、遺伝情報を正確に複製し、新しい細胞に分配するための重要な役割を担っています。染色体のおかげで、親から子へと、生命の情報が脈々と受け継がれていくのです。