原子力安全の国際基準:NUSS

電力を見直したい
先生、「NUSS」ってどういう意味ですか?原子力発電の安全に関係するみたいですが、よく分かりません。

電力の研究家
よくぞ聞いてくれました!「NUSS」は「原子力安全基準」のことで、世界中の原子力発電所が安全に運転するための、いわば「ルールブック」のようなものなんだよ。

電力を見直したい
「ルールブック」ですか?具体的にはどんなことが書かれているんですか?

電力の研究家
発電所の場所の選び方や、設計、運転、品質管理など、安全に関する様々なことが細かく決められているんだよ。世界中でこのルールを守ることによって、原子力発電を安全に行おうとしているんだね。
NUSSとは。
「原子力発電に関する用語『NUSS』は、原子力安全基準を意味します。国際原子力機関(IAEA)では、1974年から原子力発電の世界的な広まりに対応するため、原子力安全に関する考え方と具体的な対策を国際的に統一し、その成果を加盟国に提供することで、陸上にある原子力発電所の安全性を高めることを目指しました。この取り組みを「原子力安全基準策定計画」と呼び、1985年までに、(1)原子力発電所を規制するための国の組織、(2)原子力発電所の立地場所の安全性、(3)原子力発電所の安全設計、(4)原子力発電所の安全な運転、(5)原子力発電所の品質保証、という5つの分野において、5つの安全基準と55の安全指針などが定められました。しかし、1986年に起きたチェルノブイル原発事故をきっかけに、これらの基準を見直す必要性が指摘され、1988年6月には、5つの安全基準の見直しが行われました。そして、安全基準の基本となる安全原則の作成が進められ、それに基づく具体的な安全指針についても、順次、改訂作業が進められています。
NUSSとは

– NUSSとは原子力発電所は、私たちの生活に欠かせない電力を供給してくれる一方で、ひとたび事故が起きれば、環境や人々の健康に深刻な影響を与える可能性も秘めています。そのため、世界共通の安全基準に基づいて、原子力発電所を設計し、建設し、運転することが非常に重要となります。NUSS(Nuclear Safety Standards)は、国際原子力機関(IAEA)が中心となって策定した、原子力発電所の安全に関する国際基準です。世界中で原子力発電の利用が本格化する中、より一層の安全確保の必要性が高まり、1974年からNUSSの策定が始まりました。NUSSは、原子力発電所の安全を確保するために、設計、建設、運転、廃炉など、あらゆる段階における安全要件を網羅的に定めています。具体的には、原子炉の安全設計、放射線防護、緊急時対応、品質保証など、多岐にわたる分野をカバーしています。NUSSは、国際的に認められた専門家の知見と最新の技術に基づいて作成されており、世界中の国々が原子力発電所の安全性を向上させるための共通の指針として活用されています。原子力発電所を新たに建設する国や、既存の施設の安全性をさらに高めようとする国にとって、NUSSは重要な役割を果たしています。NUSSは、国際的な協力体制の基盤となるだけでなく、原子力発電に対する国際的な信頼性の向上にも大きく貢献しています。世界中の国々がNUSSの原則を遵守し、協力し合うことで、より安全な原子力発電の実現に向けて着実に前進していくことが期待されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| NUSS (Nuclear Safety Standards) | 国際原子力機関(IAEA)が中心となって策定した、原子力発電所の安全に関する国際基準 |
| 策定の背景 | 世界中で原子力発電の利用が本格化する中、より一層の安全確保の必要性が高まったため、1974年から策定が始まった。 |
| NUSSの内容 | 原子力発電所の安全を確保するために、設計、建設、運転、廃炉など、あらゆる段階における安全要件を網羅的に定めている。 – 原子炉の安全設計 – 放射線防護 – 緊急時対応 – 品質保証 など |
| NUSSの意義 | – 国際的に認められた専門家の知見と最新の技術に基づいて作成 – 世界中の国々が原子力発電所の安全性を向上させるための共通の指針 – 国際的な協力体制の基盤 – 原子力発電に対する国際的な信頼性の向上 |
NUSSの構成

原子力発電所の安全を確実にするための仕組みであるNUSSは、多岐にわたる分野を網羅しており、大きく分けて「政府組織」「立地」「設計」「運転」「品質保証」という五つの主要分野から構成されています。それぞれの分野は、原子力発電所の安全確保に向けて重要な役割を担っています。
まず「政府組織」は、原子力発電所の安全を監督・規制する機関の役割や責任、組織体制などを明確化し、効果的な規制体制を構築することを目的としています。
「立地」は、原子力発電所の建設場所を選定する上で考慮すべき自然災害や人口分布、周辺環境への影響などを評価し、安全性を確保するための基準を定めています。
「設計」は、原子炉や冷却システム、安全装置など、原子力発電所の主要な設備や機器が、想定される事故や自然災害に耐えうるよう、適切な設計や材質、強度などを規定しています。
「運転」は、原子力発電所の運転開始から停止、保守、点検、燃料交換に至るまで、あらゆる段階における手順や責任、異常時の対応などを明確化し、安全な運転を確保するための指針を示しています。
「品質保証」は、設計、建設、運転、保守といった原子力発電所の一連の活動において、品質を確保するための体制や手順、記録などを規定し、安全に係る重要な機器やシステムが設計通りに機能することを保証します。
これらの分野に対して、安全を担保するための基本的な考え方や要求事項をまとめた「安全基準」と、より具体的な方法や技術的事項を詳細に規定した「安全指針」などが整備されており、NUSSはこれらの基準や指針を通して、原子力発電所の安全を多角的に確保しています。
| 分野 | 概要 |
|---|---|
| 政府組織 | 原子力発電所の安全を監督・規制する機関の役割・責任・組織体制を明確化し、効果的な規制体制を構築する。 |
| 立地 | 原子力発電所の建設場所選定において、自然災害や人口分布、周辺環境への影響などを評価し、安全性を確保するための基準を定める。 |
| 設計 | 原子炉、冷却システム、安全装置など、原子力発電所の主要な設備や機器が、想定される事故や自然災害に耐えうるよう、適切な設計・材質・強度などを規定する。 |
| 運転 | 原子力発電所の運転開始から停止、保守、点検、燃料交換に至るまで、あらゆる段階における手順・責任・異常時の対応などを明確化し、安全な運転を確保するための指針を示す。 |
| 品質保証 | 設計、建設、運転、保守といった原子力発電所の一連の活動において、品質を確保するための体制・手順・記録などを規定し、安全に係る重要な機器やシステムが設計通りに機能することを保証する。 |
NUSS策定の背景

1970年代、世界は石油危機によるエネルギー不足に直面し、その解決策として原子力発電に大きな期待が寄せられました。その結果、各国で原子力発電所の建設が急ピッチで進められ、発電量は飛躍的に増加しました。しかし、原子力発電は膨大なエネルギーを生み出す一方で、放射性物質を扱うという大きなリスクも抱えています。万が一事故が発生した場合、環境や人々の健康に深刻な被害をもたらす可能性は否定できません。
こうした状況下、原子力発電の安全性を確保することは、原子力発電を進める国々にとって共通の課題として認識されるようになりました。そして、各国がそれぞれ独自の安全基準を設けるのではなく、国際社会全体で統一的な安全基準を設ける必要性が高まっていきました。このような世界的な流れを受け、国際原子力機関(IAEA)を中心に、関係各国が協力し、高度な安全基準を盛り込んだNUSSの策定が進められることになりました。NUSSは、原子力発電所の設計、運転、規制など、あらゆる側面における安全基準を網羅しており、国際社会における原子力安全の向上に大きく貢献しています。
| 時代背景 | 原子力発電の特徴 | 課題 | 解決策 |
|---|---|---|---|
| 1970年代の石油危機によるエネルギー不足 |
|
事故発生時の環境・人体への深刻な被害リスク |
|
チェルノブイル事故とNUSSの見直し
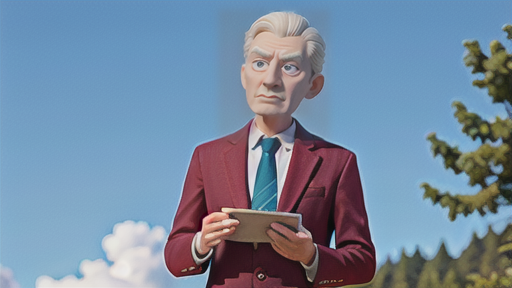
1986年4月26日に発生したチェルノブイル原子力発電所事故は、旧ソビエト連邦(現ウクライナ)で起きた未曾知の大事故であり、世界中に衝撃を与えました。この事故は、原子力発電の安全性を根底から揺るがすものであり、国際社会は改めてその重要性を認識することとなりました。国際原子力機関(IAEA)は、この事故の教訓を深く胸に刻み、原子力発電所の安全性を向上させるための取り組みを強化しました。
具体的には、IAEAは既存の原子力発電所の安全基準であるNUSS(原子力発電所の安全に関する基準)の見直しに着手しました。この見直し作業では、事故の原因を徹底的に分析し、同様の事故を二度と起こさないために、安全基準の強化が図られました。
特に重要な変更点として、「深層防護」の概念を導入したことが挙げられます。これは、複数の安全装置を多重的に設置することで、仮に一つの装置が故障しても、他の装置で事故を防止できるようにする考え方です。加えて、IAEAは「安全文化」の醸成にも力を入れました。これは、原子力発電所に関わる全ての人が、安全を最優先に行動するような意識改革を促すことを目的としています。これらの取り組みは、世界中の原子力発電所の安全性を向上させる上で大きく貢献してきました。
| IAEAの取り組み | 内容 |
|---|---|
| 安全基準の強化 | 既存の原子力発電所の安全基準(NUSS)の見直しを行い、事故の原因を分析し、同様の事故を防止するための強化を図った。 |
| 深層防護の導入 | 複数の安全装置を多重的に設置することで、仮に一つの装置が故障しても、他の装置で事故を防止できるようにする考え方。 |
| 安全文化の醸成 | 原子力発電所に関わる全ての人が、安全を最優先に行動するような意識改革を促す。 |
NUSSの継続的な改善

– NUSSの継続的な改善原子力発電は、高い安全性が求められる技術です。国際原子力機関(IAEA)は、原子力発電所の安全を確保するための重要な国際基準として、原子力安全基準(NUSS)を定めています。世界中の原子力発電所で採用されているNUSSですが、技術の進歩や運転経験の蓄積、新たな知見の獲得などを踏まえ、IAEAは継続的な改善に取り組んでいます。NUSSの改善は、具体的な取り組みによって進められています。例えば、安全基準や安全指針の定期的な見直しや改訂が行われています。これは、最新の技術や知見を反映し、より高い安全性を確保するために重要なプロセスです。また、テロリズムなど新たな脅威への対応も重要な課題です。IAEAは、国際的な協力体制を強化し、最新の情報を共有することで、新たな脅威に対する安全基準の強化を図っています。さらに、NUSSの改善には、国際的な意見交換や情報共有も欠かせません。IAEAは、各国専門家による会合やワークショップなどを開催し、NUSSの運用経験や課題に関する情報交換を積極的に行っています。このように、NUSSは、様々な取り組みを通じて、常に進化し続けています。IAEAは、今後も国際社会と協力しながら、NUSSの継続的な改善に取り組み、原子力発電の安全を確保していく考えです。原子力発電は、将来のエネルギー需要を満たす上で重要な役割を担う可能性を秘めています。NUSSの継続的な改善は、原子力発電の安全性を向上させ、その持続的な利用に貢献する上で、極めて重要な取り組みと言えるでしょう。
| 継続的な改善項目 | 具体的な取り組み |
|---|---|
| 安全基準や安全指針の更新 | 最新の技術や知見を反映した安全基準や安全指針の定期的な見直しと改訂 |
| 新たな脅威への対応 | テロリズムのような新たな脅威への対策として、国際的な協力体制を強化し、最新の情報を共有することで安全基準の強化 |
| 国際的な意見交換と情報共有 | 各国専門家による会合やワークショップなどを開催し、NUSSの運用経験や課題に関する情報交換 |
