原子炉の安全性:再臨界とは

電力を見直したい
先生、「再臨界」って、どういう意味ですか?事故と関係があるみたいだけど、よく分かりません。

電力の研究家
そうだね。「臨界」というのは、原子炉の中で核分裂反応が安定して連鎖的に起きる状態のことなんだ。そして「再臨界」は、計画的にではなく、事故などの予期せぬ事態によって再び臨界状態になってしまうことを指すんだよ。

電力を見直したい
予期せず、ですか? なんでそんなことが起きちゃうんですか?

電力の研究家
例えば、冷却水が失われて原子炉の温度が下がると、ある種の原子炉では核分裂反応が活発になりやすくなるんだ。これが再臨界を引き起こす可能性があるんだよ。原子力発電では、このような事態を防ぐための対策がとられているんだよ。
再臨界とは。
「再臨界」は、原子力発電所で使う言葉の一つです。これは、本来予定して起こす「臨界」という状態とは違って、予期せず原子炉の中で核分裂が連鎖的に起こってしまうことを指します。事故で原子炉の炉心が溶けてしまった場合などに、この「再臨界」が起こることがあります。例えば、水を冷やすタイプの原子炉では、何らかの原因で原子炉を冷やす水が冷えすぎてしまう事故が起きた時に、「再臨界」が起こる可能性があります。
再臨界とは何か
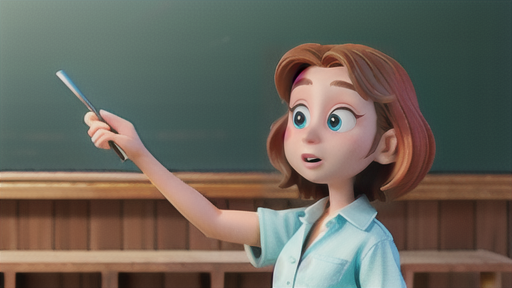
原子力発電所では、ウランなどの核分裂しやすい物質の核分裂反応を利用して、莫大な熱エネルギーを生み出しています。この核分裂反応は、原子炉の心臓部である炉心と呼ばれる場所で、慎重に制御された状態で維持されています。 核分裂反応は、中性子を介して連鎖的に発生しますが、この中性子の数を調整することで、反応の速度を制御することができるのです。 中性子を吸収する制御棒を炉心に挿入したり、冷却材の流量を調整したりすることで、安定したエネルギーを生み出し続けることが可能となります。
しかし、何らかの原因でこの制御が失われ、核分裂反応が制御不能な状態で再び活発化してしまうことがあります。これが「再臨界」と呼ばれる現象です。 計画的に制御された状態ではなく、予期せぬ形で核分裂反応が加速してしまうため、原子炉の冷却システムでは、急激に増加する熱に対応しきれなくなる可能性があります。 その結果、炉心の温度が異常なまでに上昇し、最悪の場合、炉心が溶融してしまう可能性も孕んでいます。 さらに、この過程で放射性物質が外部に放出されるリスクも高まり、環境や人体に深刻な影響を及ぼす可能性も否定できません。
再臨界は、原子力発電所の安全性にとって重大な脅威となる可能性があるため、その発生を未然に防ぐ対策が不可欠です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原子力発電の仕組み | ウランなどの核分裂物質を用いて熱エネルギーを生み出す。炉心で制御された核分裂反応を維持する。 |
| 核分裂反応の制御 | 中性子の数を調整することで反応速度を制御する。制御棒の挿入や冷却材流量調整により安定したエネルギーを生み出す。 |
| 再臨界とは | 制御の喪失により核分裂反応が制御不能に陥る現象。 |
| 再臨界の危険性 | 急激な熱増加による冷却システムの対応不能、炉心溶融の可能性、放射性物質の放出リスク。 |
| 再臨界への対策 | 未然防止策が不可欠。 |
予期せぬ核分裂の連鎖

原子力発電所の中心部にある原子炉では、ウラン燃料が使われています。ウランの原子核に中性子がぶつかると、ウランは分裂して莫大なエネルギーと新たな中性子を放出します。この時、放出された中性子がさらに別のウラン原子核に衝突し、再び核分裂が起こります。このように、次々と核分裂が連続して起こることを連鎖反応と呼びます。
通常運転中の原子炉内では、この連鎖反応は緻密に制御されています。制御棒と呼ばれる装置が中性子を吸収することで、核分裂の速度を調整し、一定の熱出力を保っているのです。しかし、何らかの原因でこの制御が効かなくなり、連鎖反応が過剰に進んでしまうことがあります。これが再臨界と呼ばれる現象です。再臨界が発生すると、原子炉内の核分裂は爆発的に増加し、制御不能な状態に陥ってしまいます。これは、原子炉の安全性を脅かす重大な事態であり、最悪の場合、炉心溶融などの深刻な事故につながる可能性も孕んでいます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 原子力発電の仕組み | ウラン燃料に中性子が衝突 → ウランが核分裂 → 莫大なエネルギーと新たな中性子を放出 → 放出された中性子がさらに別のウランに衝突し連鎖反応的に核分裂を起こす |
| 連鎖反応の制御 | 制御棒が中性子を吸収することで核分裂の速度を調整し、一定の熱出力を保つ |
| 再臨界 | 制御が効かなくなり連鎖反応が過剰に進み、核分裂が爆発的に増加し制御不能になる現象。炉心溶融などの深刻な事故につながる可能性も。 |
炉心溶融との関係

– 炉心溶融との関係原子炉内で核分裂反応が制御不能に陥り、急激に加速する現象を「再臨界」と呼びます。この再臨界は、原子炉の安全性を脅かす重大な事故の一つである「炉心溶融」を引き起こす可能性があります。通常、原子炉内ではウラン燃料の核分裂反応が制御されながら熱を発生し、その熱を利用して発電を行っています。しかし、再臨界が発生すると、制御棒の挿入などの対策が間に合わず、核分裂反応が急激に加速してしまいます。その結果、原子炉内の温度は異常なまでに上昇し、燃料を覆う金属製の被覆管や、炉心の構造を支える材料までもが溶け始めてしまいます。これが炉心溶融です。溶け落ちた炉心は、原子炉圧力容器の底部に落下し、さらに深刻な事態を引き起こす可能性があります。例えば、溶融した炉心が圧力容器を突き破り、放射性物質が外部に放出されるような事態も想定されます。このような事態を避けるためには、原子炉の設計段階から運転管理に至るまで、あらゆる段階において再臨界の発生を防止することが極めて重要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 再臨界 | 原子炉内で核分裂反応が制御不能に陥り、急激に加速する現象。 |
| 炉心溶融 | 再臨界により原子炉内の温度が異常上昇し、燃料被覆管や炉心構造材までもが溶け始める現象。 |
| 炉心溶融の危険性 | 溶融した炉心が原子炉圧力容器を突き破り、放射性物質が外部に放出される可能性。 |
| 再臨界と炉心溶融への対策 | 原子炉の設計段階から運転管理に至るまで、あらゆる段階で再臨界の発生を防止することが重要。 |
軽水炉における再臨界

– 軽水炉における再臨界
軽水炉は、その名の通り水を冷却材と減速材に利用した原子炉で、世界中で広く稼働しています。冷却材であると同時に、中性子の速度を下げる減速材としての役割も担う水が、ある条件下では原子炉を再び臨界状態に導く可能性があり、注意が必要です。
原子炉の運転中には、核分裂反応を制御するために中性子の速度を適切に保つ必要があります。軽水炉では、水はこの中性子の速度を調整する役割を担っています。水は高温になるほど中性子を吸収しやすくなる性質があります。逆に、低温の水は中性子を吸収しにくくなるため、炉心内の水の温度が低下すると中性子の数が相対的に増加し、核分裂反応が活発化する可能性があります。
冷却材喪失事故などにより炉心内の冷却水の温度が低下した場合、炉心に再び水が注入されると、低温の水が中性子を吸収しきれなくなり、核分裂反応が再活性化してしまう可能性があります。これが再臨界と呼ばれる現象です。
再臨界は、炉心の出力制御を困難にするだけでなく、最悪の場合には炉心損傷などの深刻な事故につながる可能性も孕んでいます。そのため、軽水炉の設計や運転においては、再臨界を防止するための対策が厳重に講じられています。
| 軽水炉における再臨界 |
|---|
| 軽水炉は水を冷却材と減速材に利用しており、水が特定の条件下で原子炉を再び臨界状態に導く可能性がある。 |
| 運転中の原子炉は中性子の速度制御が重要。軽水炉では水が減速材として中性子速度を調整する。 |
| 水温が高いほど中性子を吸収しやすく、低いほど吸収しにくい。炉心内の水温低下は中性子数増加、核分裂反応活発化の可能性あり。 |
| 冷却材喪失事故などで炉心冷却水温が低下した場合、再注入された低温水が中性子を吸収しきれず核分裂反応が再活性化する可能性がある。これが再臨界。 |
| 再臨界は出力制御困難、最悪の場合炉心損傷などの深刻な事故につながる可能性あり。軽水炉設計・運転において再臨界防止対策は重要。 |
安全対策の重要性

– 安全対策の重要性原子力発電所は、莫大なエネルギーを生み出すことができる一方で、ひとたび事故が起きれば、深刻な被害をもたらす可能性も孕んでいます。そのため、原子力発電所では、核分裂反応を制御し、安全を確保するための様々な対策が講じられています。原子炉の設計段階においては、負の反応度係数という概念が極めて重要になります。これは、原子炉内の温度や出力が上昇した場合に、核分裂反応を抑制する効果を持つものです。例えば、温度が上昇すると、原子炉内の水が膨張し、中性子の減速が妨げられることで、核分裂反応の速度が低下する仕組みです。運転中の安全確保には、常に原子炉の状態を監視し、異常を早期に検知することが不可欠です。そのため、制御棒の挿入状態や冷却材の流量、原子炉内の圧力や温度などを常時監視するシステムが構築されています。これらの数値に異常が認められた場合には、自動的に警報が発せられ、必要に応じて原子炉の運転が停止される仕組みになっています。さらに、万が一、事故が発生した場合に備え、炉心を緊急に冷却し、放射性物質の放出を抑制するための設備も備えられています。例えば、緊急炉心冷却システムは、冷却材の喪失等が発生した場合に、自動的に作動し、原子炉を冷却するシステムです。原子力発電は、安全性の確保が何よりも重要です。多層的な安全対策を講じることで、原子力発電所の安全性を高め、人々の暮らしと環境を守っていくことが必要です。
| 分類 | 具体的な対策 | 説明 |
|---|---|---|
| 設計段階における安全対策 | 負の反応度係数 | 原子炉内の温度や出力が上昇した場合に、核分裂反応を抑制する効果を持つ。例えば、温度上昇による水の膨張で中性子が減速され、核分裂反応の速度が低下する。 |
| 運転中の安全確保 | 原子炉の状態監視 | 制御棒の挿入状態、冷却材の流量、原子炉内の圧力や温度などを常時監視し、異常を早期に検知する。数値の異常時には警報発報、必要に応じて原子炉の運転を停止する。 |
| 事故発生時の安全対策 | 緊急炉心冷却システム | 冷却材の喪失等が発生した場合に自動的に作動し、原子炉を冷却する。 |
