エネルギー安全保障の強化:新・国家エネルギー戦略の概要

電力を見直したい
先生、「新・国家エネルギー戦略」って、結局どんなことを目指しているんですか?

電力の研究家
そうだね、簡単に言うと「エネルギーを自分たちでまかなえるようにして、安心して暮らせるようにしよう」という計画なんだ。特に、石油に頼りすぎている状態を改善しようとしているんだよ。

電力を見直したい
エネルギーを自分たちでまかなえるようにするって、具体的にどうするんですか?

電力の研究家
石油を海外から買ってばかりではなく、国内でもっと探したり、太陽光や風力など、石油以外のエネルギーをもっと使えるようにしたりする計画なんだよ。
新・国家エネルギー戦略とは。
「新・国家エネルギー戦略」は、資源エネルギー庁が、原油価格の急激な上昇など、最近のエネルギーを取り巻く厳しい状況を踏まえて、2030年までの長期的な展望に立ってまとめたエネルギーに関する計画です。この計画は、エネルギーを将来にわたって安定して確保することを何よりも重要視しており、その目標は、1. 国民から信頼されるエネルギーの安定確保体制を作る、2. エネルギー問題と環境問題を一体的に解決することで、持続可能な成長の基盤を作る、3. アジアや世界のエネルギー問題の解決に積極的に貢献するという3点です。具体的には、(1) 世界で最も進んだエネルギーの需要と供給のしくみを作る、(2) 資源を巡る外交や、エネルギーと環境分野での協力を総合的に強化する、(3) 緊急時に対応する体制を充実させる、といった取り組みが必要です。(1)と(2)については、2030年までに、現在約50%である石油への依存度を40%未満に減らし、現在15%である自国で開発する石油の割合を、実際に使える量を基準として40%程度にまで引き上げるとしています。(3)については、石油製品の備蓄を導入することなどを始めとする、石油の備蓄制度の見直しや機能強化、天然ガスに関する緊急時対応体制の整備など、緊急時に対応する体制の充実に取り組むとしています。
エネルギー戦略の背景

近年、世界情勢が目まぐるしく変化する中で、エネルギーを取り巻く環境はかつてないほど厳しさを増しています。特に、世界的な原油価格の高騰は、資源の乏しい我が国にとって大きな経済的負担となっています。さらに、中東地域など地政学的に不安定な地域からのエネルギー供給は、常に途絶のリスクと隣り合わせです。このような状況下、エネルギー安全保障の強化は、我が国の経済・社会の安定を図る上で、まさに喫緊の課題と言えるでしょう。
我が国は、エネルギー資源の多くを海外からの輸入に頼っており、その割合は極めて高いのが現状です。石油や天然ガス、さらには原子力発電の燃料であるウランに至るまで、国内で自給できる資源は限られています。そのため、国際的なエネルギー市場の動向に大きく左右されやすく、価格高騰や供給途絶といった事態は、私たちの暮らしや経済活動に大きな影響を及ぼす可能性があります。エネルギー安全保障とは、単にエネルギーを安定的に調達するだけでなく、国際的なエネルギー市場における価格変動や供給途絶といったリスクにも適切に対処し、国民生活や経済活動を安定的に維持することを意味します。
| 課題 | 現状 | 影響 |
|---|---|---|
| エネルギー安全保障の強化 | – 世界的な原油価格の高騰 – 中東地域など地政学的に不安定な地域からのエネルギー供給 |
– 我が国にとって大きな経済的負担 – エネルギー供給途絶のリスク |
| エネルギー資源の輸入依存 | – エネルギー資源の多くを海外からの輸入に頼っている – 石油、天然ガス、ウランなど、国内で自給できる資源は限られている |
– 国際的なエネルギー市場の動向に大きく左右される – 価格高騰や供給途絶は、暮らしや経済活動に大きな影響 |
新・国家エネルギー戦略の概要

近年、エネルギーを取り巻く環境は大きく変化しています。地球温暖化の深刻化や資源価格の高騰、そして世界的なエネルギー需要の増加といった課題に直面する中、我が国はエネルギー政策の転換を迫られています。こうした差し迫った課題を踏まえ、資源エネルギー庁は将来を見据えたエネルギー政策の羅針盤として、「新・国家エネルギー戦略」を策定しました。
この戦略は、「エネルギー安全保障の確立」「エネルギー・環境問題の一体的解決」「アジア・世界への貢献」という3つの大きな柱を掲げています。
まず、「エネルギー安全保障の確立」に向けては、エネルギー源の多角化を図り、特定の国や資源への依存度を低減することが重要です。同時に、国内におけるエネルギー資源の開発を促進し、エネルギーの自給率向上を目指します。
次に、「エネルギー・環境問題の一体的解決」には、太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーの導入拡大が不可欠です。再生可能エネルギーは、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出削減に大きく貢献します。さらに、国民一人ひとりが省エネルギーを意識し、エネルギー消費量を抑制していくことも重要です。
そして、「アジア・世界への貢献」としては、これまで培ってきた日本の優れたエネルギー技術やノウハウを積極的に海外に展開していきます。特に、エネルギー分野の発展途上国に対しては、技術協力や人材育成などを推進し、世界のエネルギー問題解決に貢献していきます。
| 柱 | 内容 |
|---|---|
| エネルギー安全保障の確立 | – エネルギー源の多角化 – 国内エネルギー資源の開発促進 – エネルギー自給率向上 |
| エネルギー・環境問題の一体的解決 | – 再生可能エネルギーの導入拡大 – 国民の省エネルギー意識向上 – エネルギー消費量の抑制 |
| アジア・世界への貢献 | – 日本のエネルギー技術・ノウハウの海外展開 – エネルギー分野の発展途上国への技術協力・人材育成 |
具体的な目標値

新たな国家エネルギー戦略では、2030年を目標とした具体的な数値目標が掲げられています。この目標は、エネルギー安全保障の強化と地球温暖化対策の両立を図る上で重要な意味を持ちます。
特に重要なのが、石油への依存度を減らすという目標です。現在、我が国はエネルギーの約半分を石油に頼っており、そのほとんどを海外からの輸入に頼っています。このような状況は、国際情勢の変化によってエネルギーの安定供給が脅かされるリスクを抱えています。そこで、2030年までに石油依存度を40%以下に抑えることを目指し、エネルギー源の多様化を進める計画です。
また、石油の自主開発比率を現在の15%から40%程度に引き上げることも目標に掲げています。これは、国内で消費するエネルギーを少しでも多く自国で調達することで、エネルギーの安定供給を確保する狙いがあります。この目標達成のため、政府は国内での資源開発を促進する policies を展開していく方針です。
| 目標 | 現状 | 2030年目標 |
|---|---|---|
| 石油依存度 | 約50% | 40%以下 |
| 石油の自主開発比率 | 15% | 40%程度 |
エネルギー需給構造の転換
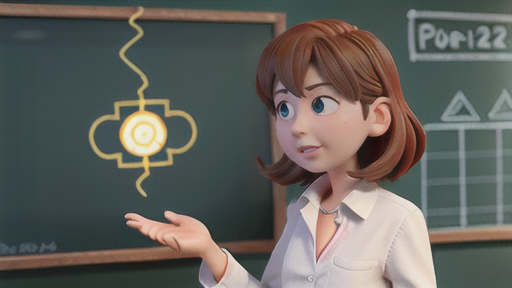
近年の国際情勢や地球温暖化問題を背景に、エネルギーを取り巻く環境は大きく変化しています。エネルギー資源の安定確保と環境保全の両立は、我が国の持続的な発展にとって不可欠な課題です。こうした認識のもと、新たな国家エネルギー戦略では、『世界最先端のエネルギー需給構造の確立』を目標に掲げ、抜本的な改革が進められています。具体的には、エネルギー源の多様化、エネルギー効率の向上、そして、エネルギー技術の革新という3つの柱で構成されています。
まず、エネルギー源の多様化においては、再生可能エネルギーの導入拡大が最重要課題です。太陽光発電や風力発電、地熱発電など、国内で活用できる自然エネルギー資源を最大限に活用することで、エネルギー自給率の向上と二酸化炭素排出量の削減を目指します。
次に、エネルギー効率の向上には、徹底した省エネルギーの推進が求められます。家庭やオフィスビル、工場など、あらゆる場面でエネルギーの無駄をなくし、少ないエネルギー消費で最大の効果を生み出す社会の実現が求められます。具体的には、高効率な設備への投資促進や、エネルギー消費量の見える化など、官民一体となった取り組みが重要となります。
最後に、エネルギー技術の革新は、将来のエネルギー需給構造を支える基盤となります。次世代原子炉の開発や水素エネルギーの利用拡大など、革新的な技術開発への投資を強化することで、エネルギー安全保障の確立と地球温暖化対策の両立を目指します。
このように、新たな国家エネルギー戦略の下、エネルギー需給構造は大きく転換しようとしています。エネルギーの安定供給を確保しつつ、環境負荷を低減していくためには、社会全体でエネルギー問題に取り組む姿勢が重要となります。
| 課題 | 具体的な内容 |
|---|---|
| エネルギー源の多様化 | 再生可能エネルギー(太陽光、風力、地熱など)の導入拡大によるエネルギー自給率向上とCO2排出量削減 |
| エネルギー効率の向上 | 家庭、オフィス、工場などにおける省エネルギーの徹底、高効率設備への投資促進、エネルギー消費量の見える化 |
| エネルギー技術の革新 | 次世代原子炉開発、水素エネルギー利用拡大などによるエネルギー安全保障の確立と地球温暖化対策 |
資源外交と国際協力

日本はエネルギー資源の多くを海外からの輸入に頼っており、資源を産出する国々との良好で安定した関係を築くことが何よりも重要です。新しい国家エネルギー戦略では、「資源外交、エネルギー環境協力の総合的強化」を掲げ、資源産出国との関係をより一層強固なものにすること、そしてエネルギー分野における国際協力を積極的に推進していく方針を明確に打ち出しています。
具体的には、エネルギー分野におけるインフラ整備への支援や技術協力などを積極的に行うことで、資源産出国との間で互いに助け合う関係を築き上げることが重要です。 このような協力関係を通じて、エネルギー資源を安定的に確保し、日本のエネルギー安全保障の強化につなげていくことを目指しています。 また、国際的な枠組みの中での協力も重要です。地球温暖化対策やエネルギー転換など、エネルギー分野が抱える課題は、もはや一国だけで解決できるものではありません。国際社会と連携し、共通の目標達成に向けて共に歩む姿勢が求められています。
|
緊急時への対応

エネルギーは、私たちの生活や経済活動にとって必要不可欠なものです。しかし、自然災害や国際情勢の変化など、予期せぬ出来事によって、エネルギーの供給が不安定になることがあります。このような事態に備え、国民の生活や経済活動を維持するためには、緊急時にも対応できる体制を整えておくことが重要です。
そこで、国が新たに策定したエネルギー戦略では、「緊急時対応の充実」が重要な柱の一つとして掲げられています。具体的には、エネルギーの供給が断たれた場合に備え、石油の備蓄量を増やすことや、電気やガスなど、他に使えるエネルギーを確保することなどが盛り込まれています。
さらに、国民一人ひとりが、いざという時に落ち着いて行動できるよう、エネルギーに関する情報提供を強化していくことも重要な取り組みです。例えば、大規模な災害が発生した場合、どのような影響が出て、どのように対応すべきかを分かりやすく伝えることで、混乱を防ぐことができます。
これらの取り組みを具体的に進めるため、国は、これまで石油の備蓄を行ってきた制度を見直し、より効果的に備蓄できるよう改善していく予定です。また、近年、発電や家庭での利用が増えている天然ガスについても、緊急時に安定供給できるよう、必要な体制を整備していくこととしています。
| 緊急時対応の強化 | 具体的な対策 |
|---|---|
| エネルギー供給途絶への対策 |
|
| 国民への情報提供の強化 |
|
| 具体的な取り組み |
|
