原子力発電の安全対策:浅層処分とは

電力を見直したい
先生、「浅層処分」ってどういう意味ですか?難しそうな単語がいっぱいあってよく分かりません。

電力の研究家
そうだね。「浅層処分」は、原子力発電で出たゴミを安全に処理する方法の一つなんだ。放射能の強さが弱いゴミを、浅い地面に埋めるんだよ。

電力を見直したい
ゴミと言っても、どんなゴミを埋めるんですか?

電力の研究家
例えば、作業員が着ていた服や手袋、フィルターなどだよ。これらのゴミはドラム缶に詰められて、コンクリートで覆われた穴に埋められるんだ。
浅層処分とは。
「浅層処分」は、原子力発電で出るゴミのうち、あまり強くない放射線を出すものを浅い地面に埋める方法のことです。ゴミは、周りを土で覆って、人が掘った穴に入れます。この穴は、コンクリートで作った入れ物に入れたり、そのまま埋めたりします。強い放射線を出すゴミは、もっと深い場所に埋める必要があります。青森県にある六ヶ所という場所では、1992年から原子力発電所から出たゴミを浅い地面に埋める処理を行っています。
浅層処分の基礎知識

– 浅層処分の基礎知識原子力発電所からは、運転や施設の解体に伴い、放射能レベルの異なる様々な廃棄物が発生します。これらの廃棄物は、その放射能レベルに応じて適切な処理・処分を行う必要があります。その中でも、放射能レベルの比較的低い廃棄物は、適切な処理を施した上で浅い地層に埋設処分されます。これを浅層処分と呼びます。浅層処分では、まず廃棄物をセメントやアスファルトなどで固め、ドラム缶などの容器に収納します。さらに、これらの容器をコンクリートなどで作られた箱型構造物に入れた後、地下数十メートルの深さに掘削した処分施設に埋設します。処分施設は、難透水性の高い粘土や岩盤などで構成され、地下水の浸入を抑制する構造となっています。このように、浅層処分は、人工バリアと天然バリアの組み合わせによって、放射性廃棄物を環境から長期にわたって隔離する技術です。これにより、放射性物質が生物圏へ拡散するのを防ぎ、私たち人間や環境への影響を低減することができます。浅層処分は、国際原子力機関(IAEA)も認める、安全で確立された技術であり、世界各国で実施されています。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 対象廃棄物 | 放射能レベルの比較的低い廃棄物 |
| 処理方法 |
|
| 処分施設の特徴 |
|
| 安全性 |
|
浅層処分の対象となる廃棄物

原子力発電所からは、運転や保守、研究活動に伴い、様々な廃棄物が発生します。これらの廃棄物は、放射能のレベルに応じて適切に処理・処分される必要があります。その中でも、放射能レベルが低く、時間の経過とともに放射能が減衰していくものを低レベル放射性廃棄物と呼びます。
この低レベル放射性廃棄物は、地下数百メートルよりも浅い場所に埋め立てる浅層処分の対象となります。具体的な例としては、原子力発電所の運転や保守、研究施設で使われた作業服や手袋、工具、そして装置から出る廃液やフィルターなどが挙げられます。これらの廃棄物は、放射能が環境中に漏れ出さないよう、コンクリート製の箱や鉄製のドラム缶などに詰められます。そして、処分場では、これらの容器をさらにコンクリートやアスファルトなどで覆うことにより、放射性物質の漏洩を長期にわたって防ぐのです。
| 分類 | 説明 |
|---|---|
| 低レベル放射性廃棄物 | 放射能レベルが低く、時間の経過とともに放射能が減衰していく廃棄物 例:作業服、手袋、工具、廃液、フィルターなど |
| 浅層処分 | 地下数百メートルよりも浅い場所に埋め立てる処分方法 |
| 放射性物質の漏洩防止対策 | ・コンクリート製の箱や鉄製のドラム缶に廃棄物を封入 ・容器をコンクリートやアスファルトで覆う |
浅層処分の方法:ピット処分とトレンチ処分

– 浅層処分の方法ピット処分とトレンチ処分原子力発電所では、運転や施設の解体などによって、様々な放射性廃棄物が発生します。これらの廃棄物は、その放射能のレベルや性質に応じて、適切な方法で処分する必要があります。比較的放射能レベルの低い廃棄物は、地下数百メートルよりも浅い場所に埋設する「浅層処分」という方法がとられます。
浅層処分には、主に「ピット処分」と「トレンチ処分」の二つの方法があります。ピット処分は、まず地下に大きな穴を掘削し、その中にコンクリートなどで作られた頑丈な施設(ピット)を構築します。そして、このピットの中にドラム缶などに封入した廃棄物を埋設します。ピットは、廃棄物が外部に漏れ出すのを防ぐために、堅牢で耐久性のある構造となっています。
一方、トレンチ処分は、ピット処分のように大規模な施設を建設するのではなく、地面に掘った溝(トレンチ)に直接廃棄物を埋設する方法です。トレンチ処分は、ピット処分に比べて簡易な方法ですが、廃棄物の種類や量、周辺環境への影響などを考慮して適切に実施する必要があります。
どちらの方法を採用するかは、廃棄物の種類や量、地質学的条件、そして周辺環境への影響などを考慮して決定されます。例えば、比較的放射能レベルの高い廃棄物や、長期間にわたって管理が必要な廃棄物は、より安全性の高いピット処分が選択されることが多いです。反対に、放射能レベルの低い廃棄物や、短期間で減衰する廃棄物は、コスト面などを考慮してトレンチ処分が選択されることがあります。
| 項目 | ピット処分 | トレンチ処分 |
|---|---|---|
| 概要 | 地下に掘った穴にコンクリート製の施設(ピット)を構築し、廃棄物を埋設する方法 | 地面に掘った溝(トレンチ)に直接廃棄物を埋設する方法 |
| メリット | 堅牢で耐久性があり、安全性が高い | ピット処分に比べて簡易で、コストが低い |
| デメリット | コストが高い | 安全性はピット処分に劣る |
| 適用される廃棄物 | 比較的放射能レベルの高い廃棄物、長期間にわたって管理が必要な廃棄物 | 放射能レベルの低い廃棄物、短期間で減衰する廃棄物 |
安全性を確保するための対策
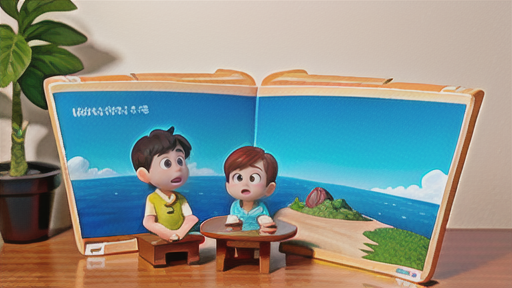
原子力発電所から発生する放射性廃棄物のうち、放射能レベルの低いものは浅層処分という方法で処理されます。この処理方法では、周辺の環境への影響を可能な限り小さくするために、非常に厳しい安全対策を幾重にも重ねて実施しています。
まず、放射性物質を含む廃棄物は、頑丈な遮蔽構造を持つ容器に厳重に封入されます。この容器は、放射性物質の漏洩を確実に防ぐように設計されています。次に、これらの容器を埋設する施設ですが、地下水の浸透を遮断する特別なシートや、万が一、施設内に水が溜まった場合でも、それを安全に排水できる設備などが備えられています。これらの設備により、放射性物質が周囲の環境に拡散することを防ぎます。
さらに、施設の周辺環境は常に監視されており、大気や水、土壌などを採取して、放射性物質の濃度を定期的に測定しています。これは、施設が安全に運用されていることを確認するために行われています。このように、浅層処分においては、厳格な安全対策と継続的な監視を通じて、周辺環境の安全確保に万全を期しています。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 廃棄物処理 | 放射能レベルの低い廃棄物を浅層処分 (周辺環境への影響を最小限にする) |
| 安全対策 | – 頑丈な遮蔽構造を持つ容器に廃棄物を封入 – 地下水の浸透を遮断するシートの設置 – 施設内の水を安全に排水できる設備 – 大気、水、土壌などの定期的な放射性物質濃度測定 |
| 目的 | 放射性物質の漏洩防止、環境への拡散防止 |
日本の浅層処分:六ヶ所村の事例

日本の原子力発電所からは、稼働に伴い、放射能レベルの低い廃棄物が発生します。この低レベル放射性廃棄物は、安全に管理し、将来の世代に負担を残さないよう適切に処分する必要があります。そのための施設として、青森県六ヶ所村に低レベル放射性廃棄物埋設センターが建設され、1992年から操業しています。
六ヶ所村の施設では、ピット処分と呼ばれる方法を採用しています。これは、コンクリートなどで作られた頑丈な箱に廃棄物を封入し、地下の施設に埋設する処分方法です。廃棄物は、セメントなどを混ぜて固めた後、ドラム缶に詰められ、さらにコンクリート製の箱に収められます。そして、地下に掘られたコンクリート製のピットと呼ばれる施設に、慎重に積み重ねていきます。
六ヶ所村の施設は、周辺環境への影響を最小限に抑えるため、厳格な安全基準に基づいて建設、操業されています。具体的には、廃棄物の放射能レベルに応じて適切な深さに埋設すること、施設周辺の地下水や土壌を常に監視し、異常がないかを確認することなどが挙げられます。このように、日本の浅層処分施設は、安全性を最優先に、将来世代への影響も考慮した上で運用されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 廃棄物の種類 | 低レベル放射性廃棄物 |
| 施設名 | 低レベル放射性廃棄物埋設センター |
| 場所 | 青森県六ヶ所村 |
| 操業開始年 | 1992年 |
| 処分方法 | ピット処分 (コンクリート製の箱に封入し地下に埋設) |
| 安全対策 |
|
