エネルギー基本法の3原則とは?

電力を見直したい
先生、「エネルギー基本法の3原則」って、何だか難しそうです。一体どんな原則なんですか?

電力の研究家
そうだね。簡単に言うと、エネルギーをみんなが安心して使えるようにするための3つの大切な約束事なんだ。1つ目は、エネルギーを安定して供給すること。2つ目は、環境を守ること。そして3つ目は、市場の力を活用することだよ。

電力を見直したい
なるほど。でも、環境を守るって、原子力発電だと難しいんじゃないんですか?

電力の研究家
いい質問だね!原子力発電は、地球温暖化につながる二酸化炭素をあまり出さないというメリットがある一方で、放射性廃棄物の処理など、環境への影響が心配されている面もあるんだ。だから、安全に配慮しながら進めていくことが大切なんだよ。
エネルギー基本法の3原則とは。
「エネルギー基本法の3原則」は、原子力発電に関する言葉で、2002年6月に施行されたエネルギー政策の基本となる法律の中で示された三つの大切な考え方を指します。
その三つとは、「エネルギーを安定して供給すること」「環境保全に配慮すること」「市場の力を活用すること」です。
この三つの考え方を基に、国や地方自治体、事業者、そして国民一人ひとりが、それぞれの役割を果たすことが求められています。
また、この法律では、政府は約3年ごとにエネルギー政策の進むべき方向性を決めた「エネルギー基本計画」を決定することになっています。
エネルギー政策の土台
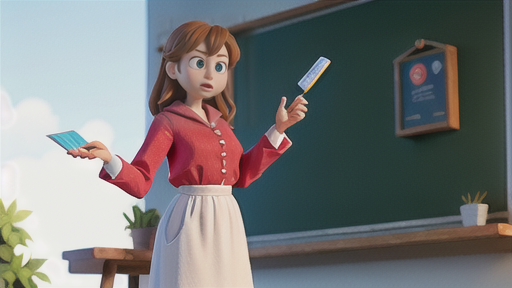
私たちの生活や経済活動を支えるエネルギー。しかし、そのエネルギー源は自給自足できず、海外からの輸入に頼っているのが現状です。さらに、エネルギーの生産や消費は、地球環境にも大きな影響を与えます。
そこで、日本はエネルギー政策の土台となる法律を定め、エネルギーをどのように確保し、利用していくべきか、その基本方針を示しました。それが「エネルギー基本法」です。
この法律の中心となるのが「安全性確保」「安定供給の確保」「環境との調和」という3つの原則です。
まず、「安全性確保」とは、原子力発電所事故のような、国民の生命、健康及び財産を脅かす事故を起こさないよう、徹底した安全対策を講じることを意味します。
次に、「安定供給の確保」とは、エネルギー資源の多くを海外に依存している現状を踏まえ、常に安定的にエネルギーを供給できる体制を構築することを意味します。
最後に、「環境との調和」とは、地球温暖化などの地球環境問題を深刻化させないよう、省エネルギーや再生可能エネルギーの導入を積極的に進め、環境負荷の低いエネルギーシステムを構築していくことを意味します。
「エネルギー基本法」に基づいた、この3原則を柱とするエネルギー政策によって、日本は安全で安定したエネルギー供給と、環境問題への対応の両立を目指しています。
| エネルギー政策の原則 | 内容 |
|---|---|
| 安全性確保 | 原子力発電所事故のような、国民の生命、健康及び財産を脅かす事故を起こさないよう、徹底した安全対策を講じる。 |
| 安定供給の確保 | エネルギー資源の多くを海外に依存している現状を踏まえ、常に安定的にエネルギーを供給できる体制を構築する。 |
| 環境との調和 | 地球温暖化などの地球環境問題を深刻化させないよう、省エネルギーや再生可能エネルギーの導入を積極的に進め、環境負荷の低いエネルギーシステムを構築していく。 |
安定供給の確保

エネルギー政策の基本となるエネルギー基本法には、3つの柱となる原則が定められています。その第一に掲げられているのが「安定供給の確保」です。これは、国民の日常生活や経済活動が滞ることなく円滑に行われるよう、エネルギーを安定的かつ継続的に供給できる体制を築き上げること を意味します。
この「安定供給の確保」を実現するためには、具体的な取り組みとして、まずエネルギー源の多様化を進めることが重要です。特定のエネルギー源に過度に依存する状態を避けることで、国際情勢の変化や災害などの影響を最小限に抑えることができます。同時に、エネルギーを備蓄しておくことも重要です。不測の事態に備え、エネルギー資源を一定量確保しておくことで、供給途絶のリスクを軽減できます。さらに、エネルギーをより効率的に使える技術の開発も欠かせません。同じ量のエネルギーからより多くの電力や熱を生み出す技術や、省エネルギー技術の開発・普及によって、エネルギーの有効活用を進めることが重要です。
特に、日本はエネルギー資源の多くを海外からの輸入に頼っているという現状があります。そのため、産出国の政治状況や経済状況、自然災害などの影響を受けやすく、国際的なエネルギー供給網の混乱にも備える必要があります。エネルギーの安定供給は、国の発展と国民生活の安定に不可欠な要素であり、今後も継続的な取り組みが求められます。
| エネルギー政策の基本原則 | 具体的な取り組み |
|---|---|
| 安定供給の確保 |
|
環境への適合

– 環境への適合私たちがエネルギーを作り出して使うということは、地球温暖化や大気を汚染するなど、環境問題と切っても切り離せない関係にあります。 このため、環境への負荷が少ないエネルギーを選び、エネルギーの節約を積極的に進めることで、未来もずっと続く社会を目指さなければなりません。具体的には、太陽の光や風の力を利用した発電など、繰り返し使えるエネルギーを積極的に取り入れていくことが重要です。 また、ものを燃やした時に発生する二酸化炭素の排出量を減らすための技術開発や取り組みも必要不可欠です。 例えば、工場や発電所から出る二酸化炭素を回収して地中に貯留する技術や、二酸化炭素を再利用して燃料や材料を作り出す技術などが期待されています。さらに、私たち一人ひとりが省エネルギーを心がけることも大切です。 家庭では、電気やガス、灯油などの無駄な使い方を見直したり、エネルギー効率の良い製品を選ぶようにしましょう。 移動手段を見直し、徒歩や自転車、公共交通機関を利用することも、二酸化炭素の排出量削減に繋がります。 環境への負荷を減らしながら、将来もエネルギーを使い続けられる社会を作るために、私たち全員が積極的に行動していく必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 環境問題への取り組みの必要性 | エネルギーの生成・消費は、地球温暖化や大気汚染などの環境問題と密接に関連しており、環境負荷の低いエネルギー選択と省エネルギーが必須である。 |
| 具体的な対策 | – 再再生可能エネルギーの積極的な導入(太陽光発電、風力発電など) – 二酸化炭素排出量削減技術の開発(回収・貯留、再利用) – 一人ひとりの省エネルギー意識の向上(エネルギー消費の見直し、効率的な製品の選択) – 移動手段の見直し(徒歩、自転車、公共交通機関の利用) |
| 目標 | 環境負荷を抑えつつ、エネルギーを持続的に利用できる社会の実現 |
市場原理の活用

– 市場原理の活用三つ目の原則は「市場原理の活用」です。これは、エネルギーの供給と需要の関係を市場の仕組みに任せ、事業者間の競争を進めることで、より効率的で経済的なエネルギー供給体制を確立することを目指すものです。具体的には、これまで国や電力会社などが独占的に担ってきた電力システムを見直し、新規事業者が参入しやすいように規制を緩和します。これは、電力システム改革や都市ガス自由化といった取り組みを通じて実現されます。このような市場における競争促進は、事業者に対して、より質の高いサービスをより安い価格で提供するよう促す効果があります。同時に、消費者は、自身のニーズや経済状況に合わせて、電気やガスの供給元を自由に選択できるようになります。このように、市場原理を活用することで、エネルギー分野における効率性と経済性が向上し、国民生活の安定に貢献すると期待されています。
| 原則 | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 市場原理の活用 | エネルギーの供給と需要の関係を市場の仕組みに任せ、事業者間の競争を促進する 具体的には、電力システム改革や都市ガス自由化などにより新規事業者の参入を促進する |
|
3原則の調和

エネルギーを巡る議論において、エネルギー基本法が掲げる3原則「安全確保」「環境への適合」「エネルギー安全保障」は常に念頭に置くべき重要な指針です。これらの原則は、どれか一つだけを重視すれば良いというものではなく、互いに密接に関係し合い、影響し合っている点を理解する必要があります。
例えば、近年注目されている再生可能エネルギーは、太陽光や風力を利用するため、二酸化炭素排出量が少なく、地球温暖化対策の観点から「環境への適合」に大きく貢献します。しかし、天候に左右されやすいという性質上、安定的に電力を供給できる体制を構築することが課題となっています。つまり、「環境への適合」を重視すると、「エネルギー安全保障」の観点で課題が生じる可能性があるのです。
同様に、「安全確保」を重視しすぎて原子力発電所の稼働を停止すれば、化石燃料への依存度が高まり、「環境への適合」の観点で逆行する可能性も出てきます。
このように、3原則はそれぞれがトレードオフの関係にあるため、どれか一つに偏ることなく、それぞれのバランスをどのように取るかが重要となります。エネルギー政策においては、これらの原則を総合的に判断し、国民生活や経済活動に支障をきたすことなく、持続可能な社会を実現していくことが求められます。
| エネルギー基本法の3原則 | 内容 | 他の原則との関係 |
|---|---|---|
| 安全確保 | エネルギーの安定供給を安全に行うこと | – 安全確保を重視しすぎると、原子力発電所の稼働停止などにより化石燃料への依存度が高まり、「環境への適合」に影響する可能性がある。 |
| 環境への適合 | 地球環境の保全に配慮すること | – 環境への適合を重視すると、再生可能エネルギーの導入により、天候に左右されるなど「エネルギー安全保障」の観点で課題が生じる可能性がある。 – 原子力発電所の稼働停止は、「環境への適合」に逆行する可能性もある。 |
| エネルギー安全保障 | エネルギーの安定供給を確保すること | – 再生可能エネルギーの導入は、天候に左右されるなど「エネルギー安全保障」の観点で課題がある。 |
私たちの役割

今日、私たちは深刻なエネルギー問題に直面しています。この問題を解決するには、国や企業の取り組みだけでなく、私たち一人ひとりの意識と行動の変化が不可欠です。
私たちの毎日の暮らしは、エネルギーと深く結びついています。電気やガス、ガソリンなど、様々なエネルギー資源を使って生活していますが、これらの資源は限りあるものです。また、エネルギーの使用は、地球温暖化などの環境問題にもつながっています。
だからこそ、エネルギー基本計画で掲げられている「省エネルギー」「エネルギーの安定供給の確保」「環境への適合」という3つの原則を理解し、日々の生活の中でエネルギー問題を意識していくことが重要です。
具体的には、電気やガスなどの無駄をなくす省エネルギーに努めたり、環境に配慮した製品を選んで購入したりすることなどが挙げられます。また、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーの利用も、エネルギー問題の解決に貢献する有効な手段の一つです。
エネルギー問題は、私たち一人ひとりの行動が変わることによって、必ず解決に向かっていきます。自分たちができることから始め、持続可能な社会を共に築いていきましょう。
| エネルギー問題の背景 | 解決に向けた取り組み |
|---|---|
|
|
