幻となった高速増殖炉の夢:FFTFの栄光と終焉

電力を見直したい
先生、「FFTF」ってどういう意味ですか?原子力発電のところで出てきたんですけど、よく分からなくて。

電力の研究家
「FFTF」は「高速中性子束試験施設」の略称で、アメリカにあった実験用の原子炉のことだよ。高速増殖炉という種類の原子炉の開発のために、実際に動かして性能や安全性を確かめるために作られたんだ。

電力を見直したい
実験用の原子炉なんですね!でも、どうして今はもう動いていないんですか?

電力の研究家
いい質問だね。実は、高速増殖炉の開発は計画が中止になってしまったんだ。それで、FFTFも役割を終えて、2001年に閉鎖されることが決まったんだよ。
FFTFとは。
「FFTF」とは、高速中性子束試験施設という原子力発電に関する言葉です。これは、熱出力400メガワットの高速実験炉のことを指します。 アメリカでは、1960年代に原子力委員会と民間企業が協力して、1000メガワット級の高速増殖炉の設計研究を始めました。これがきっかけで、FFTFが建設され、原型炉CRBRの試験が行われました。しかし、1994年に計画は中止されました。 FFTFは1992年から稼働しておらず、クリントン政権の終わりには、リチャードソンエネルギー長官(当時)によって廃止が決定されました。 しかし、ブッシュ政権に変わると、この決定は覆され、民間企業による医療用の放射性同位体研究に活用できるかどうか調査されました。 最終的に、アメリカエネルギー省は2001年12月19日に恒久的な閉鎖を決定しました。 アブラハムエネルギー長官(当時)は、「FFTFを再び動かすことは現実的ではない」と結論付けました。
高速増殖炉の試験炉として

高速中性子束試験施設、FFTFは、その名の通り高速増殖炉の開発において中心的な役割を担っていました。1960年代、アメリカは高速増殖炉によるエネルギー革命を夢見ていました。そして、FFTFはその夢を実現するための重要な一歩として、将来建設が予定されていた大型高速増殖炉の設計に必要なデータを取得するために建設されました。
FFTFは、熱出力が400MWという当時としては画期的な規模を誇り、様々な試験や実験に利用されました。中でも重要なのは、高速増殖炉の心臓部とも言える炉心や燃料の試験です。燃料として使われるプルトニウムやウランをどのように配置し、冷却材であるナトリウムをどのように循環させるかなど、炉心の設計に必要なデータがFFTFで集められました。また、高速中性子の照射が炉の材料に及ぼす影響を調べる材料の照射試験も行われました。これらの試験によって得られたデータは、その後の高速増殖炉開発に大きく貢献しました。しかし、FFTFは1992年に運転を終了し、アメリカの高速増殖炉開発は停滞することになりました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施設名 | 高速中性子束試験施設(FFTF) |
| 目的 | 高速増殖炉開発のためのデータ取得 |
| 役割 | 将来の大型高速増殖炉設計に必要なデータ取得 |
| 出力 | 400MW |
| 主な試験内容 | 炉心・燃料試験、材料照射試験 |
| 試験内容詳細 | – 燃料配置、ナトリウム循環に関する炉心設計データ取得 – 高速中性子照射が炉材料に及ぼす影響調査 |
| 運転終了年 | 1992年 |
原型炉開発の頓挫とFFTFの運命
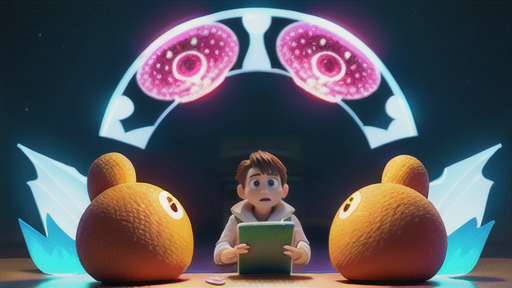
1970年代に入るまで、アメリカは高速増殖炉の実験炉であるFFTFでの実験成果を積み重ね、高速増殖炉開発を着実に進めているように見えました。しかし、1970年代に入ると、世界のエネルギー情勢は大きく変化し始めます。
1973年のオイルショック後、エネルギー需要の伸びは鈍化し、エネルギー源の多様化は、以前ほど喫緊の課題ではなくなりました。それと同時に、高速増殖炉開発には従来の発電方式に比べてコストがかかることが明らかになり、巨額の開発費に見合うだけのメリットが見いだせないと判断されるようになりました。さらに、スリーマイル島原子力発電所事故の影響もあり、原子力発電に対する安全性への懸念が高まったことも、開発を後押しするどころか、むしろ逆風となってしまいました。
こうした状況を受けて、アメリカ政府は高速増殖炉開発の優先度を下げ、FFTFの実験データに基づいて設計が進められていた原型炉「クリンチリバー増殖炉(CRBR)」の計画は、1983年に中止に追い込まれてしまいました。そして、FFTF自身もその役割を終え、1992年に運転を停止し、長い歴史に幕を下ろしました。
| 時期 | アメリカにおける高速増殖炉開発 |
|---|---|
| 1970年代に入るまで | 実験炉FFTFでの実験成果を積み重ね、順調に進展 |
| 1970年代 |
|
| 1983年 | 原型炉「クリンチリバー増殖炉(CRBR)」の計画が中止 |
| 1992年 | FFTFの運転停止 |
閉鎖か活用か、揺れ動くFFTFのその後

米国ワシントン州に位置する高速実験炉「FFTF」は、1992年にその運転を停止しました。その後、FFTFの今後を巡り、様々な議論が巻き起こりました。老朽化が進む施設の維持には、年間数億円にものぼる費用が必要であり、クリントン政権下では、財政負担の観点から廃止の方針が打ち出されました。
しかし、ブッシュ政権に移行すると、FFTFの新たな活用方法が模索され始めます。医療分野で需要が高まる医療用同位体の製造拠点としての活用や、原子力関連技術の研究開発への利用など、様々な可能性が検討されました。原子力業界からは、高速増殖炉技術の維持や技術者の育成の観点から、FFTFの存続を望む声が根強くありました。
しかしながら、度重なる検討の結果、一度停止した原子炉を再稼働させるには、安全性の確保や膨大な費用が必要となることから、「運転再開は現実的ではない」という結論に至りました。そして、2001年、FFTFの恒久閉鎖が正式に決定されました。FFTFのケースは、原子力施設の扱いにおける費用対効果や将来的な技術開発の重要性などを改めて問う、重要な事例となりました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施設名 | 高速実験炉「FFTF」 |
| 場所 | 米国ワシントン州 |
| 運転停止 | 1992年 |
| 停止後の議論 | ・老朽化による維持費負担 ・医療用同位体製造拠点としての活用 ・原子力関連技術の研究開発への利用 ・高速増殖炉技術の維持、技術者育成 |
| 結論 | 2001年恒久閉鎖 |
| 理由 | ・再稼働による安全性確保の困難さ ・膨大な費用 |
| 教訓 | 原子力施設の扱いにおける費用対効果や将来的な技術開発の重要性 |
未完の夢、そして未来へ

アメリカが国の威信をかけて進めていた高速増殖炉開発の夢。その象徴とも言える施設、FFTF。建設には想像を絶する費用が投じられ、多くの技術者や研究者が情熱を注ぎ込みました。誰もが高速増殖炉の輝かしい未来を疑いませんでした。しかし、時代の流れは残酷でした。高速増殖炉を取り巻く状況は大きく変わり、FFTFは本来の目的である発電を行うことなく、その歴史に幕を下ろすことになったのです。莫大な費用と時間、そして技術者たちの努力は、未完の夢として歴史に刻まれました。しかし、FFTFは完全に過去のものではありません。そこで積み重ねられた研究成果や技術、そして何よりも技術者たちの経験は、貴重な財産として未来へ引き継がれていくでしょう。化石燃料の枯渇や地球温暖化など、エネルギー問題は人類にとって大きな課題です。そして、再び高速増殖炉がエネルギー問題の解決策として期待される日が来るかもしれません。その時は、FFTFの遺産が再び輝きを放つ時となるでしょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施設名 | FFTF |
| 目的 | 高速増殖炉の開発 |
| 状況 | 時代の流れにより閉鎖、発電は行われず |
| 結果 | 未完の夢 |
| 遺産 | 研究成果、技術、技術者たちの経験 |
| 未来 | エネルギー問題の解決策として再び期待される可能性 |
