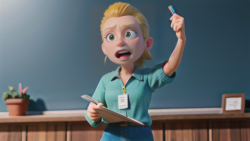原子力発電の基礎知識
原子力発電の基礎知識 原子力の源: 質量欠損の謎
物質を構成する最小単位である原子の中心には、原子核が存在します。原子核は、プラスの電気を帯びた陽子と電気的に中性な中性子から成り立っています。当然、原子核の質量は、それを構成する陽子と中性子の質量の和と等しいと考えられます。しかし、実際に精密な測定を行うと、驚くべきことに、原子核の質量は、陽子と中性子をバラバラにした状態での質量の合計よりも小さくなっているのです。
この不思議な現象は、「質量欠損」と呼ばれ、アインシュタインが提唱した特殊相対性理論によって説明されます。特殊相対性理論によれば、エネルギーと質量は互換性があり、質量はエネルギーに変換することができます。原子核が形成される際には、陽子と中性子を結びつけるために莫大なエネルギーが必要となり、このエネルギーが質量に変換されて、質量欠損として観測されるのです。
つまり、失われたように見える質量は、原子核を結びつけるエネルギーとして、形を変えて存在しているのです。このことから、原子核中にどれだけのエネルギーが蓄えられているかが分かります。このエネルギーは、原子力発電など、様々な分野で利用されています。