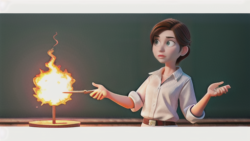その他
その他 戦略兵器削減への道:START条約とその変遷
1980年代、世界はアメリカ合衆国とソビエト社会主義共和国連邦という二つの超大国による冷戦の真っただ中にありました。両国は、いつ核戦争が勃発してもおかしくないという、緊迫した状況にありました。このような状況下、膨大な数の核兵器を保有する両国は、互いに不信感を募らせ、軍拡競争を繰り広げていました。しかし、このような状況は、1980年代後半に入ると変化を見せ始めます。ゴルバチョフ書記長率いるソ連が、ペレストロイカやグラスノストといった改革路線を打ち出し、国際社会との協調路線を模索し始めたのです。このような国際情勢の変化を受けて、1982年から、米ソ両国は戦略兵器削減条約(START)の交渉を開始しました。そして、冷戦終結後の1991年、ついに両国は第一次戦略兵器削減条約(START I)に調印しました。これは、米ソ両国の戦略核弾頭数を、それぞれ6,000発以下に削減するという画期的な内容でした。START Iは、米ソ両国が、核兵器の脅威を減らし、より安全な世界を目指して協力していくという決意を示すものでした。これは、核軍縮に向けた歴史的な一歩として、国際社会から高く評価されました。