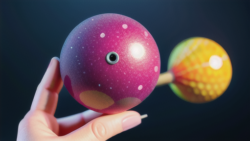その他
その他 地球温暖化の鍵?放射強制力とは
- 放射強制力地球のエネルギーバランスを測る指標
地球は、太陽からエネルギーを受け取って暖められ、同時に宇宙に向かってエネルギーを放出することで、一定の温度を保っています。この地球全体で起こるエネルギーの出入りと、そのバランスを変化させる効果のことを放射強制力といいます。
太陽光のように地球を暖める効果を持つものをプラスの放射強制力、逆に地球を冷やす効果を持つものをマイナスの放射強制力と呼びます。放射強制力は、1平方メートルあたりのエネルギー量で表され、単位にはワット毎平方メートル(W/m2)が用いられます。
例えば、大気中の二酸化炭素が増加すると、地球から宇宙へ放出されるはずの熱が二酸化炭素に吸収され、地球に熱がこもってしまいます。これは地球温暖化の原因の一つとして知られており、プラスの放射強制力を持つ現象の一例です。一方、火山噴火などによって大気中にエアロゾルと呼ばれる微粒子が放出されると、太陽光が遮られ、地球を冷やす効果をもたらします。これはマイナスの放射強制力を持つ現象の一例です。
放射強制力は、地球温暖化を考える上で非常に重要な概念です。地球のエネルギーバランスを左右する様々な要因と、それらがどれだけの影響力を持つのかを理解することで、地球温暖化のメカニズムをより深く理解することができます。