疲労破断:見えない力による破壊

電力を見直したい
先生、「疲労破断」って、具体的にどんなふうに起こるんですか? 鉄の棒を何回も曲げると折れる、みたいなイメージでいいんですか?

電力の研究家
いいところに気がつきましたね!まさに、鉄の棒を何度も曲げると折れる現象も疲労破断の一種です。 ただし、疲労破断は、目に見えるほど大きく曲げなくても、微小な力でも長い時間をかけて繰り返し加わることで起こる点に注意が必要です。

電力を見直したい
なるほど。どれくらい小さな力でも起こるんですか?

電力の研究家
場合によりますが、例えば、原子炉の配管などでは、運転と停止を繰り返すことで、わずかな温度変化や圧力変化が繰り返し加わり、疲労破断が起こることがあります。目には見えないような小さな変化でも、長い間には大きな影響を与えることがあるんですよ。
疲労破断とは。
「疲労破断」は、原子力発電などで使われる言葉で、物体に繰り返し力を加えたり、変形させたりすることで、その物が壊れてしまう現象のことを指します。実際には、100回から1000億回程度の繰り返しで壊れる場合が多いです。繰り返し回数が1万回から10万回以上の場合は「高サイクル疲労」、それ以下の場合は「低サイクル疲労」と呼びます。疲労では、繰り返し加える力や変形の大きさ(振れ幅)と繰り返し回数が重要になります。壊れるまで無限回の繰り返しが必要な力や変形の大きさを「耐久限度」と言いますが、実際にはこの耐久限度をはっきり決めることができないので、1億回に相当する力や変形の大きさを耐久限度としています。
はじめに

私たちの日常生活では、建物や橋、車など、様々な構造物が力を受けています。これらの構造物は、設計段階で想定される最大の力に耐えられるように作られています。しかし、大きな力が一度に加わらなくても、小さな力が繰り返し加わることで、材料は徐々に弱くなり、最終的には壊れてしまうことがあります。このような現象を「疲労」と呼び、疲労が原因で起こる破壊を「疲労破断」と言います。
疲労破断は、一見すると頑丈に見える構造物でも、長い時間をかけて進行するため、非常に危険です。例えば、飛行機の機体や橋げたなど、人々の命を預かる重要な構造物において、疲労破断は絶対に避けるべき現象です。そのため、構造物の設計や材料の選択、定期的な検査など、様々な対策を講じる必要があります。
この「はじめに」では、私たちの身の回りで起こる疲労破断の例や、そのメカニズム、そして予防策などについて詳しく解説していきます。疲労破断は、特別な環境だけで起こるものではなく、私たちの身近に潜む危険です。この機会に、疲労破断についての理解を深め、安全な社会の実現に貢献しましょう。
疲労破断とは
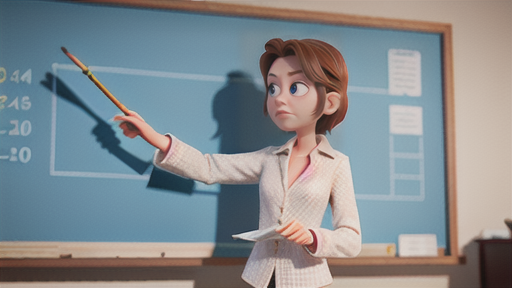
– 疲労破断とは疲労破断とは、金属材料に繰り返し力が加わることで、亀裂が発生し、最終的に破壊に至る現象です。この現象は、橋や飛行機などの構造物において、重大な事故を引き起こす可能性があるため、その危険性が広く認識されています。疲労破断の特徴は、一度に大きな力が加わらなくても、小さな力が繰り返し加わることで発生する点にあります。これは、金属疲労と呼ばれる現象で、たとえるなら、金属製のクリップを想像してみてください。クリップを一度曲げただけでは壊れませんが、何度も繰り返し曲げ伸ばしを繰り返すと、最終的には折れてしまいます。これは、クリップの内部に、目に見えない小さな損傷が蓄積していくためです。同様に、橋や飛行機などの構造物も、稼働中に振動や風圧など、繰り返し小さな力を受け続けます。これらの力は、一見、構造物に影響を与えないように見えますが、長い年月をかけて金属疲労を引き起こし、微細な亀裂を生じさせてしまいます。一度発生した亀裂は、負荷を受けるたびに少しずつ成長し、最終的には構造物全体を破壊するほどの大きな亀裂へと発展します。そして、ある日突然、構造物が耐え切れなくなり、疲労破断に至るのです。疲労破断は、目視で確認するのが難しく、発生を予測することが困難であるため、構造物の設計段階から、疲労に対する強度を十分に考慮する必要があります。また、定期的な検査やメンテナンスによって、早期に亀裂を発見し、重大な事故を未然に防ぐことが重要です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 定義 | 金属材料に繰り返し力が加わることで、亀裂が発生し、最終的に破壊に至る現象 |
| 特徴 | 小さな力が繰り返し加わることで発生(金属疲労) |
| 亀裂の発生と成長 | 繰り返し負荷により微細な亀裂が発生し、徐々に成長 |
| 危険性 | 目視での確認や発生予測が困難 |
| 対策 | 設計段階での強度考慮、定期的な検査とメンテナンス |
疲労破断の種類

– 疲労破断の種類物体に力が繰り返し加わることで、たとえ一度に加わる力が小さくても、やがて破壊に至ることがあります。これを疲労破断と呼びますが、疲労破断は、破壊までの繰り返し回数によって大きく二つに分類されます。10万回以上の繰り返しで発生するものを「高サイクル疲労」と呼びます。高サイクル疲労は、自動車のエンジンや発電機のタービンなど、稼働時間が長く、微小な振動が連続的に発生するような環境で起こりやすいのが特徴です。このような環境では、目に見えないような微小な亀裂が材料内部に発生し、それが徐々に成長することで最終的に破壊に至ります。一方、10万回以下の比較的少ない回数で発生するものを「低サイクル疲労」と呼びます。低サイクル疲労は、地震や台風、あるいは事故など、短時間に大きな力が繰り返し加わるような状況で発生しやすくなります。高サイクル疲労とは異なり、目に見えるほどの比較的大きな亀裂が発生し、それが急速に成長することで破壊に至ります。このように、疲労破断は発生するメカニズムや破壊までの時間スケールが大きく異なるため、それぞれに適した対策を講じる必要があります。例えば、高サイクル疲労に対しては、材料の強度を高めたり、表面を滑らかにして亀裂が発生しにくくするなどの対策が有効です。一方、低サイクル疲労に対しては、構造物の設計を見直して大きな力が加わらないようにしたり、エネルギー吸収体を設置して衝撃を緩和するなどの対策が重要となります。
| 項目 | 高サイクル疲労 | 低サイクル疲労 |
|---|---|---|
| 繰り返し回数 | 10万回以上 | 10万回以下 |
| 発生しやすい環境 | 自動車のエンジン、発電機のタービンなど、稼働時間が長く、微小な振動が連続的に発生するような環境 | 地震、台風、事故など、短時間に大きな力が繰り返し加わるような状況 |
| 破壊プロセス | 目に見えないような微小な亀裂が材料内部に発生し、それが徐々に成長することで最終的に破壊 | 目に見えるほどの比較的大きな亀裂が発生し、それが急速に成長することで破壊 |
| 対策例 | – 材料の強度を高める – 表面を滑らかにして亀裂が発生しにくくする |
– 構造物の設計を見直して大きな力が加わらないようにする – エネルギー吸収体を設置して衝撃を緩和する |
疲労限度と安全設計

物を繰り返し使うと、たとえ小さな力でも壊れてしまうことがあります。このような現象を疲労破壊と呼び、どれだけの力に耐えられるのかを表す限界値を疲労限度といいます。この疲労限度は、材料の種類によって大きく異なるだけでなく、温度や周りの環境によっても変化するため、ものづくりにおいて非常に重要な要素となります。
しかし実際には、すべての材料の疲労限度を明確に求めることは難しいのが現状です。そこで、多くの場合、1,000万回ほど繰り返し力を加えても壊れない強度を疲労限度とみなして設計を行います。
疲労破壊は、目に見える傷から始まるわけではありません。材料の内部で小さな亀裂が発生し、それが繰り返し負荷を受けることで徐々に成長することで起こります。目視では確認できない微小な亀裂が、やがて大きな亀裂へと発展し、最終的に破壊につながるのです。
そのため、疲労破壊を防ぐためには、設計段階で材料の疲労限度を考慮することが重要です。疲労限度よりも低い応力で使用すること、応力集中部を避けること、表面を滑らかに仕上げるなど、様々な対策を講じることで、製品の安全性と信頼性を向上させることができます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 疲労破壊 | 小さな力が繰り返し加わることで、物が壊れる現象 |
| 疲労限度 | 材料が疲労破壊を起こさずに耐えられる力の限界値 |
| 疲労限度の影響因子 | 材料の種類, 温度, 周りの環境 |
| 疲労破壊のメカニズム | 材料内部の微小亀裂発生 → 繰り返し負荷による亀裂成長 → 破壊 |
| 疲労破壊を防ぐための対策 | 疲労限度以下の応力で使用, 応力集中部の回避, 表面を滑らかに仕上げる |
まとめ

今回の記事では、物質の壊れる現象の一つである「疲労破断」について解説しました。
疲労破断は、金属材料に繰り返し力が加わることで、小さなひび割れが発生し、それが徐々に成長して、最終的には破壊に至る現象です。
一見すると頑丈な金属であっても、繰り返し使用されるうちに、目に見えないレベルで小さな損傷が蓄積していくため、注意が必要です。
この疲労破断は、橋梁や航空機、原子炉など、私たちの生活を支える様々な構造物で発生する可能性があります。
もし、これらの構造物で疲労破断が発生すると、大規模な事故につながる可能性もあり、大変危険です。
そのため、構造物や機械の設計を行う際には、疲労破断のリスクを考慮した安全設計が求められます。
具体的には、使用される材料の強度や形状、使用環境などを考慮し、疲労破断が発生しにくい設計にする必要があります。
疲労破断は、目に見えないところで進行するため、その発生を予測することは容易ではありません。
しかし、定期的な検査や適切なメンテナンスを行うことで、疲労破断による事故を未然に防ぐことができます。
今後、より安全な社会を実現していくためには、疲労破断に対する理解を深め、適切な対策を講じていくことが重要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 金属材料に繰り返し力が加わることで、小さなひび割れが発生し、それが徐々に成長して、最終的には破壊に至る現象 |
| 発生メカニズム | 一見すると頑丈な金属であっても、繰り返し使用されるうちに、目に見えないレベルで小さな損傷が蓄積していくため。 |
| 発生可能性のある構造物例 | 橋梁、航空機、原子炉など |
| 設計上の対策 | 材料の強度や形状、使用環境などを考慮し、疲労破断が発生しにくい設計にする。 |
| 予防策 | 定期的な検査や適切なメンテナンス |
