排出量取引制度:地球温暖化対策の新潮流

電力を見直したい
先生、『排出許可証取引制度』って、環境を汚す権利を売ったり買ったりするってどういうことですか? ちょっとイメージが掴めないです。

電力の研究家
なるほど。例えば、工場があるとします。この工場には、環境を汚染する物質を出す量の上限が決められています。もし、上限よりも少ない量の汚染物質ですんだ場合は、その分を他の工場に売ることができるんです。

電力を見直したい
あ、そうか!じゃあ、環境を汚染する物質をたくさん出してしまった工場は、少ない工場から買うこともできるんですね?

電力の研究家
その通りです。このように、売買を通じて、全体として環境汚染物質の排出量を減らそうとするのが『排出許可証取引制度』です。
排出許可証取引制度とは。
「排出許可証取引制度」は、原子力発電に関する言葉ではなく、環境汚染を防ぐための仕組みです。それぞれの国や会社に対して、汚染物質をどれくらい出して良いかという上限を決めます。もし上限を超えてしまった国や会社は、上限よりも少なく済んだ国や会社から、その権利を売買することができるのです。
この制度は、アメリカで1990年代に、酸性雨の原因となる物質を減らすために初めて導入されました。その結果、汚染物質の排出量は減少し、効果が認められました。
その後、地球温暖化を防ぐための国際的な約束である「京都議定書」でも、この制度が取り入れられました。「京都議定書」では、二酸化炭素などの温室効果ガスを減らすために、それぞれの国が削減目標を達成する必要があります。排出許可証取引制度は、目標達成をより柔軟に進めるための方法として位置付けられています。
2008年からは、「京都議定書」に基づいた正式な取引が始まりました。ヨーロッパでは、すでに2005年から、地域内での取引市場を設けて、活発に取引が行われています。
排出許可証取引制度は、経済的な負担を抑えながら、先進国が協力して排出量を減らすための有効な手段だと考えられています。しかし、一方で、ロシアのように排出枠に余裕がある国から、排出枠を買い取ることで、自国の努力を怠ってしまう可能性も懸念されています。
そこで、2001年の「マラケシュ合意」では、排出許可証取引制度は、あくまでも目標達成を助けるための手段であり、その利用は限定的であるべきだと確認されました。
排出量取引制度とは

– 排出量取引制度とは排出量取引制度は、企業や国ごとに温室効果ガスの排出上限を定め、その枠組みの中で排出量を管理する仕組みです。各企業に割り当てられた排出上限を超過してしまう場合、超過分を他の企業から購入することで調整することができます。逆に、省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用などにより、排出量を削減できた企業は、その削減分を他の企業に売却することができます。この制度の目的は、経済的な仕組みを活用することで、全体として温室効果ガスの排出削減を促すことにあります。排出量取引制度では、排出量が多い企業ほどコスト負担が大きくなるため、企業は経済合理性に基づいて自主的に排出削減に取り組むインセンティブが生まれます。 一方、排出量が少ない企業にとっては、削減努力を収益につなげることができるため、更なる技術開発や設備投資を促進する効果も期待できます。このように、排出量取引制度は、環境保護と経済成長の両立を目指す上で重要な役割を果たす制度として、国際的に注目されています。
| 排出量取引制度の仕組み | メリット |
|---|---|
| 企業や国ごとに温室効果ガスの排出上限を設定し、その枠内で排出量を管理する。 超過分は他の企業から購入、削減分は他の企業に売却可能。 |
|
排出量取引制度のメリット

– 排出量取引制度のメリット排出量取引制度は、従来の規制による削減目標設定と比較して、多くの利点を持つ革新的な仕組みです。まず、費用効率の高さが挙げられます。企業は、それぞれの事情に合わせて、排出削減対策を実施するか、他の企業から排出枠を購入するかを選択できます。自ら削減対策を行うよりも排出枠を購入した方が経済的に有利な企業は、排出枠を購入することで、結果的に社会全体での削減費用を抑えながら、排出削減目標の達成に貢献できます。次に、技術革新の促進も期待できます。排出枠の取引価格が上昇すれば、企業はより積極的に排出削減技術の開発や導入に取り組むようになり、技術革新を加速させる効果が期待できます。さらに、排出量取引制度は、企業に対して排出削減への経済的な動機付けを提供します。排出枠を下回る削減を達成した企業は、その分の排出枠を他の企業に売却することで利益を得られます。一方、排出枠を超過する企業は、不足分の排出枠を購入する必要があるため、経済的な負担を強いられます。このように、経済的なインセンティブを導入することで、企業は積極的に排出削減に取り組むようになります。このように、排出量取引制度は、経済的な効率性を持ちながら、技術革新を促進し、企業の排出削減意欲を高める効果的な制度と言えるでしょう。
| メリット | 説明 |
|---|---|
| 費用効率の高さ | 企業は排出削減対策と排出枠購入から費用対効果の高い方を選択できるため、社会全体での削減費用を抑えられます。 |
| 技術革新の促進 | 排出枠の取引価格上昇により、企業は排出削減技術の開発・導入に積極的に取り組み、技術革新を加速させます。 |
| 排出削減への経済的な動機付け | 排出枠を下回る削減を達成した企業は排出枠を売却して利益を得られ、超過した企業は購入が必要になるため、経済的なインセンティブが働きます。 |
京都議定書と排出量取引
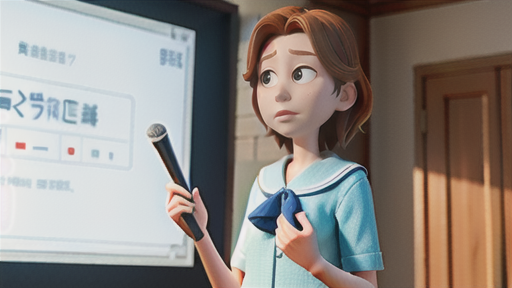
– 京都議定書と排出量取引1997年に採択された京都議定書は、地球温暖化対策のための国際的な枠組みです。この議定書では、先進国に対して温室効果ガスの排出削減目標が具体的に定められました。目標達成のため、各国は国内での排出削減対策に加えて、柔軟性措置と呼ばれるいくつかの仕組みを活用することが認められています。その一つが排出量取引制度です。排出量取引制度では、まず各国に排出枠と呼ばれる排出量の限度が設定されます。企業はこの排出枠の範囲内で経済活動を営む必要がありますが、技術革新や省エネルギー対策などにより排出量を削減した場合、その分の排出枠を他の企業に売却することが可能です。一方、排出削減が難しい企業は、排出枠を不足分だけ購入することで、自らの排出枠を満たすことができます。京都議定書では、この排出量取引制度を国際的に展開することで、より効率的な排出削減を目指しました。排出削減コストの低い国や企業が率先して削減を進め、その削減分を排出削減コストの高い国や企業に売却することで、全体としてより少ない費用で目標達成が可能になるという仕組みです。このように、排出量取引制度は京都議定書の柔軟性措置の一つとして重要な役割を担い、国際的な排出削減目標の達成に向けて活用されました。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 京都議定書の採択年 | 1997年 |
| 目的 | 地球温暖化対策 |
| 対象 | 先進国 |
| 目標 | 温室効果ガスの排出削減 |
| 排出量取引制度 | 排出枠を設定し、企業間で排出枠の売買を可能にする制度 |
| 排出枠を売却できる企業 | 技術革新や省エネルギー対策などで排出量を削減できた企業 |
| 排出枠を購入する企業 | 排出削減が難しい企業 |
| 排出量取引制度の目的 | より効率的な排出削減 |
欧州における排出量取引制度
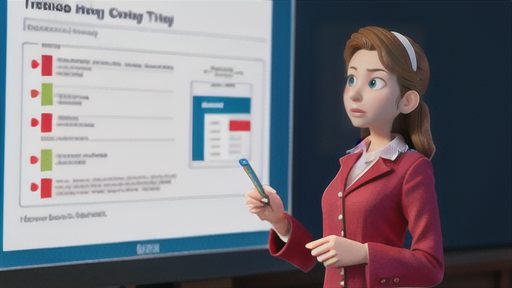
– 欧州における排出量取引制度欧州連合(EU)は、地球温暖化対策として温室効果ガスの排出量削減に取り組んでいます。その取り組みの一つとして、2005年に世界に先駆けて大規模な排出量取引制度(EU ETS)を導入しました。EU ETSは、発電所や工場など、多くの企業を対象としています。具体的にはエネルギー関連産業や航空産業などが含まれており、これらの企業は、二酸化炭素の排出量に応じて排出枠を保有することが義務付けられています。排出枠は、企業ごとに割り当てられる無償のものと、市場で取引される有償のものがあります。企業は、自社の排出量に見合った排出枠を保有しなければなりません。もし、排出量が割り当てられた排出枠を上回った場合、不足分の排出枠を市場で購入する必要があります。逆に、排出削減の努力によって排出量が割り当てられた排出枠を下回った場合には、余剰分の排出枠を市場で売却することができます。このように、EU ETSは、企業に経済的なインセンティブを与えることで、排出削減を促進し、市場メカニズムを通じて効率的に温室効果ガスの排出削減目標を達成することを目指しています。実際、EU ETSは導入以来、EU域内における排出削減に大きく貢献しており、その仕組みは世界中で注目されています。
| 制度名 | 対象 | 排出枠 | 排出枠が不足する場合 | 排出枠が余剰な場合 | 目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| EU ETS (排出量取引制度) | 発電所や工場などの企業 (エネルギー関連産業、航空産業など) | 企業ごとに二酸化炭素の排出量に応じて保有が義務付けられている – 無償で割り当てられるもの – 市場で取引される有償のもの |
市場で購入 | 市場で売却 | 企業に経済的なインセンティブを与え、排出削減を促進し、市場メカニズムを通じて効率的に温室効果ガスの排出削減目標を達成する |
排出量取引制度の課題

地球温暖化への対策として、企業などが排出できる温室効果ガスの量の上限を定め、その権利を売買できるようにする排出量取引制度が注目されています。これは、排出量を減らした企業が、その分を他の企業に売却できる仕組みであり、経済的なインセンティブを活用して、全体として排出量を削減することを目指しています。しかし、この制度にはいくつかの課題も存在します。
まず、排出枠の配分方法が挙げられます。企業に平等に配分する方法や、過去の排出量に応じて配分する方法など、いくつかの方法が考えられますが、どの方法を採用するかは、企業の負担や制度の効果に大きく影響します。
次に、排出枠の価格変動の問題があります。排出枠の需要と供給によって価格が決まるため、経済状況や政策の変化によって価格が大きく変動する可能性があります。価格の変動が大きいと、企業は将来の排出量を予測することが難しくなり、設備投資などの計画が立てにくくなってしまいます。
さらに、市場の透明性をどのように確保するかも課題です。排出枠の取引が公正に行われているか、排出量の算定方法が適切かなど、情報公開が不足すると、市場の信頼性が損なわれる可能性があります。
排出量取引制度を効果的に機能させるためには、これらの課題を克服するための工夫が不可欠です。排出枠の配分方法や価格安定化のための措置、情報公開の強化など、制度設計や運用方法を慎重に検討していく必要があります。
| 課題 | 詳細 |
|---|---|
| 排出枠の配分方法 | – 企業への平等な配分や過去の排出量に応じた配分など、方法によって企業の負担や制度の効果が大きく変わる。 |
| 排出枠の価格変動 | – 需要と供給で価格が決まるため、経済状況や政策の変化で価格が大きく変動する可能性があり、企業の計画策定が困難になる。 |
| 市場の透明性確保 | – 取引の公正さや排出量算定の適切さなど、情報公開不足は市場の信頼性損失につながる。 |
排出量取引制度の未来

地球温暖化は、私たちの社会や経済に深刻な影響を与える喫緊の課題です。その対策として、温室効果ガスの排出量を取引する「排出量取引制度」が注目されています。これは、企業ごとに排出量の限度を設け、超過分を取引できるようにする仕組みです。 企業は、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの利用を進めることで、排出量を削減し、取引で利益を得ることができます。一方、排出量の削減が難しい企業は、排出枠を購入することで、事業を継続できます。
この制度は、すでに世界各国で導入されており、日本でも2012年から実施されています。今後、対象となる産業や参加する国がさらに拡大することで、地球温暖化対策の中核的な役割を担うことが期待されています。
排出量取引制度の普及には、いくつかの課題も挙げられます。例えば、排出量の算定方法や取引価格の決定方法など、制度設計の複雑さや運用コストの高さが課題として挙げられます。また、企業の競争力への影響や、排出枠の価格変動による市場の不安定化といった懸念もあります。
しかし、これらの課題を克服し、排出量取引制度を効果的に運用することができれば、経済的なインセンティブを活用しながら、地球温暖化対策を進めることができます。排出量取引制度は、持続可能な社会を実現するための重要な手段として、今後ますます期待が高まっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 概要 | 企業ごとに温室効果ガスの排出量の限度を設け、超過分を取引できるようにする仕組み |
| メリット |
|
| 現状 |
|
| 課題 |
|
| 期待される効果 | 経済的なインセンティブを活用しながら、地球温暖化対策を進めることができる |
