電力システムの要!負荷曲線を解説

電力を見直したい
先生、「負荷曲線」ってなんですか? 電力会社が使う言葉って聞いたんですけど。

電力の研究家
そうだね。「負荷曲線」は、電力会社が使う大切な言葉の一つだよ。一日または一年を通して、電気の使われ方がどのように変わるかを表したグラフなんだ。

電力を見直したい
一日の中でも、電気の使われ方が変わるんですか?

電力の研究家
そうだよ。例えば、朝ご飯の準備や夜の照明など、時間帯によって電気の使用量は変わるよね?負荷曲線は、そういった電気の需要の変化をグラフで表したものなんだよ。
負荷曲線とは。
『負荷曲線』っていうのは、原子力発電に関する言葉で、電力を使う量が時間によってどう変わるかを表したグラフのことです。例えば、一日のうちで電気をたくさん使う時間帯とあまり使わない時間帯を細かく表したり、一年を通して月ごとに平均してどれくらい電気が使われているかを示したりします。電力会社から見ると、電気を使う量はそのまま負担になる量になるので、『負荷』という言葉が使われています。最近は、電気をたくさん使うようになってきたことに加えて、昼と夜や季節によって使う量の違いが大きくなってきているので、この『負荷曲線』を分析して、将来どれくらい電気が使われるかを予測することがますます大切になっています。
電力の需要と供給のバランス

私たちの生活に欠かせない電気は、発電所で作られ、送電線を通って家庭や工場に届けられています。電気は貯めておくことが難しいという性質があるため、常に需要と供給のバランスを保つことが重要となります。電力会社は、このバランスを維持するために日々努力を重ねています。
需要量は、季節、時間帯、気温などによって大きく変動します。例えば、夏の暑い日にはエアコンの使用が増えるため、電力需要はピークを迎えます。一方、需要が少ない夜間や冬季には、電力需要は低下します。このような変動に対応するために、電力会社は常に需要を予測し、それに合わせて発電所の運転を調整しています。
具体的には、需要が多い時間帯には、稼働率の高い発電所をフル稼働させるとともに、必要に応じて稼働率の低い発電所も稼働させることで、電力の安定供給を図ります。一方、需要が少ない時間帯には、一部の発電所の出力を抑えたり、停止したりすることで、供給過剰にならないように調整しています。このように、電力会社は需要と供給のバランスを常に意識しながら、電力の安定供給という重要な役割を担っています。
| 需要の変動要因 | 需要が多い時間帯の電力会社対応 | 需要が少ない時間帯の電力会社対応 |
|---|---|---|
| 季節、時間帯、気温など (例:夏の暑い日はエアコンの使用増加) |
稼働率の高い発電所をフル稼働 必要に応じて稼働率の低い発電所も稼働 |
一部の発電所の出力抑制または停止 |
負荷曲線とは
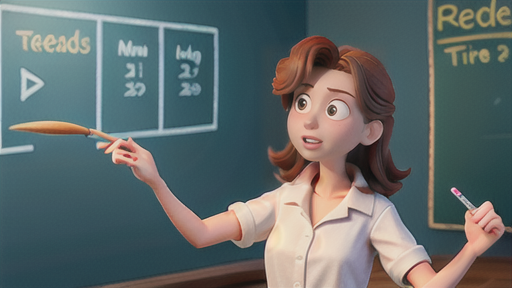
– 負荷曲線とは私たちの生活には、電気は欠かせません。工場を動かしたり、電車を走らせたり、家庭で電化製品を使ったりと、あらゆる場面で電気が使われています。そして、電気を使う量(電力需要)は、時間帯によって大きく変化します。この電力需要の変化の様子をグラフで表したものが、負荷曲線です。負荷曲線は、横軸に時間を、縦軸に電力需要をとり、需要の変化を視覚的に表します。例えば、ある日の電力需要の変化をグラフにすると、朝起きて活動が始まる時間帯から徐々に需要が上がり始めます。そして、日中は工場の操業やオフィスでの業務などで需要がピークを迎えます。夕方以降は、再び家庭での電力使用が増加し、その後、夜遅くになると需要は徐々に減っていきます。このように、負荷曲線は一日の時間帯による需要の変化を明確に示してくれます。負荷曲線は、電力会社が電力の安定供給を行う上で非常に重要な役割を果たします。電力会社は、需要の変化を予測し、常に需要に見合った電力を供給しなければなりません。需要を上回る電力を供給できないと停電が起きる可能性があり、逆に、需要を大きく上回る電力を供給し続けると、エネルギーの無駄になります。負荷曲線は、過去の需要変化のパターンを分析することで、将来の需要を予測するのに役立ちます。また、再生可能エネルギーなど、天候に左右される不安定なエネルギーの導入を進める際にも、負荷曲線の分析は重要です。 電力会社は、負荷曲線の形状を分析することで、効率的かつ安定的な電力供給体制を構築することができます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 負荷曲線とは | 時間帯ごとの電力需要の変化をグラフで表したもの。横軸に時間を、縦軸に電力需要をプロットする。 |
| 負荷曲線の形状 | 時間帯によって変化する。例えば、朝と夕方に需要が高くなり、日中は比較的安定し、夜間は低下する。 |
| 負荷曲線の重要性 | 電力会社が電力の安定供給を行う上で非常に重要。負荷曲線を分析することで、電力会社は需要の変化を予測し、需要に見合った電力を供給することができる。 |
| 負荷曲線の活用例 | – 将来の電力需要の予測 – 再生可能エネルギーなど、天候に左右される不安定なエネルギーの導入計画 |
負荷曲線の種類

電力需要は常に一定ではなく、時間帯や季節によって大きく変動します。この変動の様子をグラフで表したものを負荷曲線と呼びますが、時間軸の長さによって、一日の電力の需要変化を示すものや、一年間の季節変動を示すものなど、様々な種類があります。
例えば、一日の電力の需要変化を示す負荷曲線を見てみましょう。このグラフからは、朝、昼、夕、夜といった時間帯ごとの需要の増減を把握できます。一般的に、朝と夕方は家庭や企業での活動が活発になるため、電力需要がピークを迎えます。一方、深夜から早朝にかけては、人々の活動が減るため、電力需要は最も低くなります。
次に、一年間の季節変動を示す負荷曲線を見てみましょう。日本では、冷房需要が高まる夏場と暖房需要が高まる冬場に需要のピークが見られます。特に、気温が極端に高くなる真夏日には、冷房の使用が集中するため、電力需要が急増することがあります。
このように、負荷曲線は、時間帯や季節による電力需要の変化を把握するために欠かせないツールです。電力会社はこれらのデータに基づいて、発電所の運転計画を立てたり、電力需給のバランスを調整したりしています。
| 負荷曲線の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 一日の電力の需要変化を示す負荷曲線 | 朝と夕方にピーク、深夜から早朝に最低となる。 |
| 一年間の季節変動を示す負荷曲線 | 夏場と冬場にピーク、特に真夏日は冷房需要で急増する。 |
負荷曲線と原子力発電

電力会社は、常に変動する電力需要に安定的に応えるため、さまざまな発電方法を組み合わせた電力供給体制を構築しています。その中でも、原子力発電は、燃料の安定供給という観点で重要な役割を担っています。原子力発電は、大量のエネルギーを生み出すことができるという利点がある一方で、一度運転を始めると、その出力調整が難しいという特徴があります。火力発電のように、燃料の投入量を調整することで出力の増減を容易に行うことができないため、電力需要の変化に対して柔軟に対応することが難しいと言えます。電力需要は、一日を通して大きく変動します。朝夕のピーク時には電力需要が高まり、夜間や早朝には需要が低下します。このような電力需要の変動は、グラフ上に表すと、山と谷が連なる曲線として視覚化されます。この曲線のことを「負荷曲線」と呼びます。原子力発電は、出力調整が難しいため、負荷曲線のベース部分、つまり一日を通して比較的安定した電力需要に対応するベースロード電源として運用されることが一般的です。一方、負荷曲線のピーク部分に対応するピークロード電源としては、出力調整が容易な火力発電や揚水発電などが用いられます。火力発電は、燃料の種類によって出力調整のしやすさが異なりますが、一般的に原子力発電に比べて柔軟に対応することができます。揚水発電は、夜間の電力需要が低い時間帯に水をくみ上げておき、電力需要が高まる時間帯に水を落下させて発電するシステムで、電力貯蔵の役割を果たします。このように、負荷曲線を分析し、それぞれの発電方法の特徴を理解した上で、原子力発電、火力発電、揚水発電などを適切に組み合わせることで、安定した電力供給を実現することができます。
| 発電方法 | 特徴 | 役割 |
|---|---|---|
| 原子力発電 | 出力調整が難しい 大量のエネルギーを生み出すことが可能 燃料の安定供給という観点で重要 |
ベースロード電源:一日を通して比較的安定した電力需要に対応 |
| 火力発電 | 出力調整が比較的容易 燃料の種類によって出力調整のしやすさが異なる |
ピークロード電源:電力需要のピーク時に対応 |
| 揚水発電 | 夜間に水をくみ上げておき、電力需要が高まる時間帯に水を落下させて発電 電力貯蔵の役割を果たす |
ピークロード電源:電力需要のピーク時に対応 |
負荷曲線の変化と再生可能エネルギー
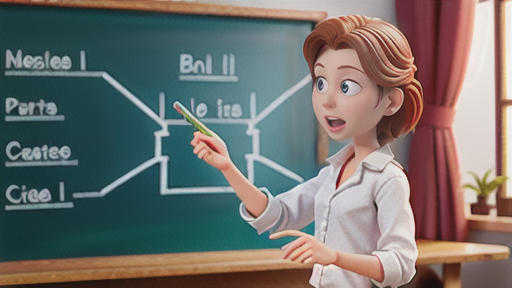
近年、太陽光発電や風力発電といった自然エネルギーの利用が広がっています。これらのエネルギーは、環境への負担が少ないという利点がある一方で、天候に左右されやすく、電力供給が不安定になるという課題も抱えています。
電力会社は、常に電力の需要と供給のバランスを保つ必要があり、そのために需要量の変化を予測した「負荷曲線」を作成し、運用に役立てています。従来の火力発電や原子力発電は、出力調整が比較的容易なため、負荷変動にも対応しやすいため、負荷曲線も比較的緩やかな変化を示していました。
しかしながら、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーは、天候によって発電量が大きく変動するため、負荷曲線に急激な変化が生じやすくなります。例えば、日中に太陽光発電の出力が増加すると、需要が低い時間帯には電力供給が過剰になり、逆に夜間や天候が悪い日には供給不足に陥る可能性があります。
このような状況に対応するために、電力会社は、より精度の高い負荷曲線の分析と予測が求められます。具体的には、気象データの活用や蓄電池の導入、需要家側の電力使用の調整など、さまざまな対策を組み合わせることで、再生可能エネルギーの導入拡大に伴う電力供給の安定化を図っていく必要があります。
| エネルギー源 | メリット | デメリット | 負荷曲線への影響 | 対策 |
|---|---|---|---|---|
| 火力発電 原子力発電 |
出力調整が容易 | 環境負荷が高い | 緩やかな変化 | – |
| 太陽光発電 風力発電 |
環境負荷が低い | 天候に左右されやすい 電力供給が不安定 |
急激な変化 | – 気象データの活用 – 蓄電池の導入 – 需要家側の電力使用の調整 |
