核医学検査:体の中のミクロな世界を探る

電力を見直したい
『核医学検査』って、放射線を使うんですよね? 危険じゃないんですか?

電力の研究家
そうだね、核医学検査は放射線を使う検査だよ。でも、検査で使う放射線の量はごくわずかで、体への負担は少ないんだ。レントゲン検査と比べても、ずっと少ない量なんだよ。

電力を見直したい
そうなんですね。でも、やっぱり少しは心配です…

電力の研究家
もちろん、心配な気持ちはよくわかるよ。もし不安なことがあれば、検査の前に先生や看護師さんに相談してみるといいよ。きちんと説明してくれるから、安心して検査を受けられると思うよ。
核医学検査とは。
「核医学検査」は、放射線を出す特殊な物質を目印として体に投与し、病気の診断や検査に役立てる方法です。検査には、体内で行う方法と体外で行う方法の二種類があります。体内で行う検査では、目印となる物質を患者さんに投与し、体内のどこにどれくらい、どのように変化していくかを調べます。これにより、組織や臓器、病巣の働きを評価することができます。体内で行う核医学検査で、現在最も多く行われているのは、陽電子断層法や単光子放射型CTなどです。一方、体外で行う検査では、患者さんから採取した血液や尿などを使い、目印となる物質を加えて検査を行います。この方法は、ごくわずかな物質でも測定できる感度の高さと、操作が簡単なことが特徴です。また、一度に多くの検体を検査できるという利点もあります。体外で行う検査の代表的な例としては、放射免疫測定法や免疫放射分析法などがあります。
核医学検査とは

– 核医学検査とは核医学検査は、ごくわずかな放射線を含む薬剤を体内に投与し、そこから放出される放射線を専用のカメラで捉えることで、病気の診断や状態を把握する検査方法です。検査で用いる薬剤は、検査対象となる臓器や組織に集まりやすい性質を持っているため、体内の特定の場所に集まります。この薬剤が出す放射線をカメラで撮影することで、臓器や組織の働きや状態を画像として映し出すことができます。核医学検査の特徴は、臓器や組織の機能を調べることができる点です。これは、レントゲン検査やCT検査など、体の構造を調べる検査とは大きく異なる点です。例えば、心臓であれば、心臓の筋肉の動きや血液の流れを調べることができますし、脳であれば、脳の血流や代謝の状態を調べることができます。このように、核医学検査は、臓器や組織の機能を評価することで、病気の早期発見や適切な治療方針の決定に役立ちます。さらに、核医学検査で用いる放射線の量はごくわずかであるため、体への負担は非常に少ないです。検査時間も比較的短く、検査後すぐに日常生活に戻ることができます。安全性が高く、体の負担が少ない検査方法として、近年注目されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 検査方法 | 微量の放射線を含む薬剤を投与し、放出される放射線をカメラで捉え、臓器や組織の状態を画像化 |
| 特徴 | 臓器や組織の機能を調べることができる。
|
| メリット |
|
体の中を“見る”検査

– 体の中を“見る”検査
健康診断などで広く行われているレントゲン検査は、体の外からX線を照射して、骨の状態などを確認する検査です。一方、核医学検査は、微量の放射性物質を含む薬剤を体内に入れることで、臓器や組織の働きを調べる検査です。
レントゲン検査などの画像診断が、例えるなら家の外観を撮影するものであるとすれば、核医学検査は家の中の様子、つまり臓器や組織がどのように機能しているかを調べることができる検査といえます。
検査では、放射性物質を含む薬剤を注射や内服で体内に取り込みます。この薬剤は、検査対象となる臓器や組織に集まる性質があります。薬剤から出る放射線を特殊なカメラで捉え、コンピューターで画像処理することで、臓器や組織の働きや病変の有無、大きさなどを調べることが可能となります。
核医学検査は、がん、心臓病、脳神経疾患など、様々な病気の診断に用いられています。また、病気の進行度を把握したり、治療の効果を判定したりするためにも役立てられています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 検査方法 | 微量の放射性物質を含む薬剤を体内に入れ、臓器や組織に集まった薬剤から出る放射線をカメラで捉え画像化 |
| 薬剤投与方法 | 注射、内服 |
| 検査対象 | 臓器や組織の働き |
| 診断可能な病気 | がん、心臓病、脳神経疾患など |
| その他 | 病気の進行度把握、治療効果判定 |
インビボ検査:生きたまま体の機能を調べる
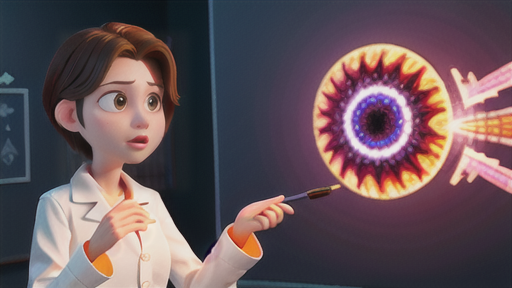
– 生きたまま体の機能を調べるインビボ検査インビボ検査とは、生きた動物や人間を対象に、体内で起こる様々な生命現象を直接観察したり、測定したりする検査方法です。これは、臓器や組織を採取して調べる「生体外検査」とは異なり、生命活動を行っている状態での体の機能を評価できるという大きな利点があります。インビボ検査では、検査対象にごく微量の放射性物質をつけた薬剤などを投与し、その動きを特殊なカメラで追跡します。薬剤は、臓器や組織に集まったり、特定の細胞と結合したりすることで、その部位の機能や状態を映し出します。代表的なインビボ検査としては、陽電子断層撮影法(PET)や単光子放射型コンピューター断層撮影法(SPECT)などが挙げられます。PET検査では、グルコースなどの代謝物質に微量の放射性物質をつけた薬剤を投与し、がん細胞など代謝が活発な部位を画像化します。一方、SPECT検査では、血流や特定の受容体などと結合する薬剤を用いることで、臓器の機能や疾患の存在を診断します。インビボ検査は、がん、心臓病、脳神経疾患など、様々な疾患の診断に用いられています。また、新しい薬の効果や安全性を確認する際にも重要な役割を担っています。
| 検査方法 | 説明 | 用途 |
|---|---|---|
| インビボ検査 | 生きた動物や人間を対象に、体内で起こる様々な生命現象を直接観察したり、測定したりする検査方法。ごく微量の放射性物質をつけた薬剤などを投与し、その動きを特殊なカメラで追跡する。 | 臓器や組織の機能や状態を評価する。がん、心臓病、脳神経疾患など、様々な疾患の診断。新しい薬の効果や安全性を確認。 |
| 陽電子断層撮影法(PET) | グルコースなどの代謝物質に微量の放射性物質をつけた薬剤を投与し、がん細胞など代謝が活発な部位を画像化する。 | がん細胞など代謝が活発な部位の画像化。 |
| 単光子放射型コンピューター断層撮影法(SPECT) | 血流や特定の受容体などと結合する薬剤を用いることで、臓器の機能や疾患の存在を診断する。 | 臓器の機能や疾患の存在診断。 |
インビトロ検査:採取した検体からミクロな世界を分析

– インビトロ検査採取した検体からミクロな世界を分析インビトロ検査とは、患者さんから採取した血液や尿などの検体を、試験管やシャーレといった体外の人工的な環境で分析する検査方法です。採取した検体の中には、私たちの健康状態を示す様々な情報が含まれており、インビトロ検査では、ホルモンやタンパク質、酵素などの量や働きを調べることで、病気の診断や治療効果の判定に役立てられています。インビトロ検査の代表的な方法として、放射免疫測定法(RIA)や免疫放射分析法(IRMA)などがあります。これらの方法は、放射性物質を用いて特定の物質を検出する高感度な測定法であり、ごく微量のホルモンや腫瘍マーカーなどを測定することができます。インビトロ検査は、体への負担が少なく、比較的短時間で結果が得られるため、病気の早期発見や治療方針の決定に大きく貢献しています。また、近年では、遺伝子検査や遺伝子診断など、遺伝子レベルで病気のリスクや体質を調べるインビトロ検査も登場しており、個別化医療や予防医療の分野での活用が期待されています。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| インビトロ検査とは | 患者から採取した血液や尿などの検体を、試験管やシャーレといった体外の人工的な環境で分析する検査方法 |
| 目的 | 検体中のホルモンやタンパク質、酵素などの量や働きを調べることで、病気の診断や治療効果の判定 |
| 代表的な方法 | 放射免疫測定法(RIA)、免疫放射分析法(IRMA)など |
| 特徴 | 体への負担が少なく、比較的短時間で結果が得られる。 高感度な測定法であり、ごく微量のホルモンや腫瘍マーカーなどを測定することができる。 |
| 貢献 | 病気の早期発見や治療方針の決定に大きく貢献 |
| 近年登場した検査 | 遺伝子検査や遺伝子診断など、遺伝子レベルで病気のリスクや体質を調べるインビトロ検査 |
| 今後の展望 | 個別化医療や予防医療の分野での活用が期待 |
様々な病気の診断に貢献

核医学検査は、放射性同位元素と呼ばれる、ごくわずかな放射線を出す物質を体内に投与し、その物質が出す放射線を専用のカメラで捉えることで、様々な病気の診断に役立つ画像を得る検査法です。
この検査は、がんなどの腫瘍性疾患だけでなく、心臓病、脳血管障害、甲状腺疾患など、広範囲な疾患の診断に利用されています。
例えば、心臓病の検査では、放射性同位元素を注射し、心臓の筋肉にどれだけ血液が行き渡っているかを画像化することで、狭心症や心筋梗塞などの診断に役立ちます。また、脳血管障害の検査では、脳内の血流状態を画像化することで、脳梗塞や脳出血などの診断をサポートします。
さらに、核医学検査は病気の進行度や治療効果の判定にも非常に役立ちます。治療前に検査を行うことで、病気の広がりや悪性度を把握し、適切な治療方針を決定することができます。また、治療後に検査を行うことで、治療の効果を客観的に評価し、治療方針の変更や継続を判断する材料となります。
このように、核医学検査は患者さん一人ひとりに最適な医療を提供するために欠かせない検査と言えるでしょう。
| 検査項目 | 目的 | 診断可能な病気 |
|---|---|---|
| 心臓病検査 | 心臓の筋肉への血液供給を画像化 | 狭心症、心筋梗塞など |
| 脳血管障害検査 | 脳内の血流状態を画像化 | 脳梗塞、脳出血など |
