許容被曝線量から線量当量限度へ

電力を見直したい
先生、「許容被曝線量」って、今は使われない言葉なんですよね? どうして使われなくなったんですか?

電力の研究家
よく調べているね! 「許容被曝線量」は、昔は放射線を浴びても大丈夫と考えられていた量の上限を示す言葉だったんだ。でも、放射線は少しでも危険がゼロではないという考え方に変わってきたんだ。

電力を見直したい
なるほど。じゃあ、今は何というのですか?

電力の研究家
今は「線量当量限度」という言葉を使っているよ。これは、健康への影響をできるだけ少なくするために、被曝する量をできるだけ少なく抑えるという考え方に基づいているんだ。
許容被曝線量とは。
「許容被ばく線量」という言葉は、原子力発電の分野で使われていましたが、今は使われていません。1965年の国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告では、仕事で放射線を浴びる場合の線量の限度を「最大許容(被ばく)線量」と呼んでいました。
現在の「線量当量限度」という言葉は、放射線から体を守るために、健康への影響がはっきり出ることを防ぎ、影響が出る確率を低いレベルに抑えることを目指して、ICRPが勧告しているものです。日本では、昭和63年に法律で、放射線を使う仕事をする人の被ばく線量の限度を「許容被ばく線量」から「線量当量限度」に変更しました。具体的には、体の線量限度は1年間で50ミリシーベルト、目の水晶体の線量限度は1年間で150ミリシーベルトとなっています。
過去の用語:許容被曝線量

かつて、放射線を扱う仕事に従事する人たちは、体への影響を考慮して、一定量までは放射線を浴びても許容されるという考え方が主流でした。この許容される放射線の量のことを「許容被曝線量」と呼んでいました。
この考え方が生まれた背景には、1965年に国際放射線防護委員会(ICRP)が出した勧告があります。この勧告では、放射線を浴びることで健康への悪影響が生じる可能性を認めつつも、その影響を一定レベルに抑えることを目的として、放射線業務に従事する人々に対する被曝線量の上限を定めていました。
しかし、時が経つにつれて、放射線から人々を守るための考え方は大きく進歩しました。放射線による健康への影響は、わずかでも浴びれば浴びるだけリスクが高まるという考え方が広まり、国際的な基準もより厳格なものへと変化していきました。
このような変化に伴い、「許容被曝線量」という言葉は、放射線防護の考え方の変化を適切に反映した「線量当量限度」という用語に置き換えられました。これは、放射線業務に従事する人々が、業務上浴びてもよいとされる線量の上限値を示すものです。
| 時代 | 考え方 | 用語 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 過去 | 一定量までは放射線を浴びても許容される | 許容被曝線量 | 放射線業務に従事する人々に対する被曝線量の上限 |
| 現在 | わずかでも浴びれば浴びるだけリスクが高まる | 線量当量限度 | 放射線業務に従事する人々が、業務上浴びてもよいとされる線量の上限値 |
現在の用語:線量当量限度
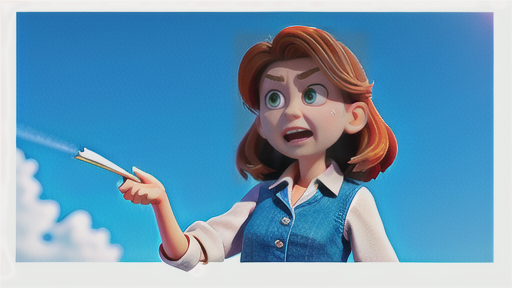
– 現在の用語線量当量限度
「線量当量限度」とは、人体が放射線を浴びることで健康に悪影響が及ぶリスクを、可能な限り抑えるために設けられた、被ばく線量の限度値のことです。これは、放射線から人々を守るという考え方が、「放射線を浴びる量を可能な限り少なくする」という方向に変化してきたことを示しています。
以前は「許容被ばく線量」という言葉が使われていました。これは、ある程度の放射線被ばくはやむを得ないと考えていたことを示唆しています。しかし、現在では、放射線による健康への影響をより重視し、被ばくを制限することが重要視されています。そのため、「線量当量限度」は、あくまで被ばくを制限するための指標としての意味合いが強くなっています。
「線量当量限度」は、放射線業務に従事する人々や一般の人々など、対象となる人々や被ばくする身体の部位によって、それぞれ異なる値が定められています。これは、放射線によるリスクを適切に管理し、人々の健康と安全を確保するために重要なことです。
私たちは、日常生活で医療現場や自然界などから、常に微量の放射線を浴びています。しかし、「線量当量限度」を理解し、放射線被ばくを適切に管理することで、健康へのリスクを抑えながら、原子力エネルギーの恩恵を安全に享受していくことができます。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 線量当量限度 | 人体への放射線の影響を最小限に抑えるために設定された被曝線量の限度値。 |
| 以前の用語:許容被ばく線量 | ある程度の放射線被曝はやむを得ないと考えていた過去の用語。 |
| 線量当量限度の対象 | 放射線業務従事者、一般の人々、被曝する身体部位によって異なる。 |
線量当量限度の算出基準

放射線業務に従事する人や一般の方々を守るため、放射線被ばくによる健康影響を考慮し、被ばく線量の限度として線量当量限度が定められています。線量当量限度を決めるにあたっては、主に二つの健康影響が考慮されます。
一つ目は「決定論的影響」と呼ばれるものです。これは、ある一定量以上の放射線を浴びると、身体に障害などの悪影響が必ず現れるというものです。例えば、大量の放射線を短時間に浴びた場合に起こる急性放射線症などが挙げられます。
二つ目は「確率的影響」と呼ばれるものです。これは、被ばく線量が多いほど、将来に癌や白血病などの病気の発症確率が高くなるというものです。浴びた量に比例して発症確率が上昇することがわかっています。
線量当量限度は、これらの健康影響を考慮し、決定論的影響を確実に防ぐレベルに設定されています。さらに、確率的影響についても、その発生確率を社会的に容認できるレベルに抑えるように定められています。このように、線量当量限度は、放射線被ばくから人々の健康を守る上で重要な役割を担っています。
| 分類 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 決定論的影響 | 一定量以上の被ばくで必ず健康被害が出る | 急性放射線症 |
| 確率的影響 | 被ばく線量が多いほど、将来、癌や白血病などの病気の発症確率が高くなる。 | 癌、白血病 |
日本の法令における線量当量限度

日本では、人々が放射線から適切に守られるよう、様々な法律や規則が定められています。その中でも、放射線業務に従事する人々の被ばくに関する法律は、1988年に大きな変更がありました。この改正では、それまで使われていた「許容被曝線量」という言葉が「線量当量限度」という言葉に置き換えられました。
この変更は、単なる言葉の置き換えではなく、放射線防護における考え方の変化を示すものでした。「許容被曝線量」という言葉には、ある程度の被ばくは許容されるという考え方が含まれていましたが、「線量当量限度」という言葉は、被ばくを可能な限り低く抑えるという考え方を明確に示しています。
この改正により、放射線業務に従事する人々の年間の実効線量当量限度は50ミリシーベルトに、眼の水晶体の組織線量当量限度は年間150ミリシーベルトに定められました。これらの数値は、国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告に基づいており、世界保健機関(WHO)などの国際機関も支持する、科学的な知見に基づいたものです。日本はこれらの国際的な基準を参考にしながら、人々が放射線の影響から適切に守られるよう努めています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 年 | 1988年 |
| 変更点 | 「許容被曝線量」→「線量当量限度」 |
| 変更の意図 |
|
| 線量当量限度 |
|
| 根拠 |
|
