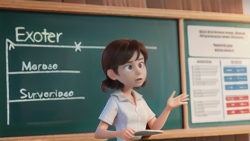核燃料
核燃料 ウランの埋蔵量: 資源量という視点
かつて、ウランの地下に眠る量の表現として、『埋蔵鉱量』や『埋蔵量(reserves)』が使われていました。しかし、近年は国際的な基準に合わせる形で『資源量(resources)』という用語が用いられるようになっています。これは単なる言葉の置き換えではなく、より広い概念を反映した重要な変化です。
従来の『埋蔵鉱量』や『埋蔵量』は、確認されたウラン鉱石の量を指していました。一方、『資源量』は経済性や技術的な採掘可能性を考慮に入れており、将来採掘できる可能性のあるウランも含んでいます。つまり、同じウランの量であっても、経済状況や技術革新によって『資源量』は変動する可能性があるのです。
具体的には、『資源量』は、経済性や採掘技術の確実性に応じてさらに細かく分類されます。例えば、比較的低いコストで採掘可能なものを『確認資源量』、技術開発が必要なものや経済性が低いものを『推定資源量』などと呼びます。このように、『資源量』はウランの供給ポテンシャルをより正確に把握するために不可欠な概念と言えるでしょう。