遺伝子の化学:形質転換

電力を見直したい
先生、『形質転換』って遺伝子の性質が変わることって意味ですよね? どうして遺伝子の性質が変わると、例えば毒を作れるようになるんですか?

電力の研究家
良い質問だね! 遺伝子の性質が変わるというのは、設計図が変わるようなものなんだ。毒を作るための設計図が、形質転換によって細菌の中に組み込まれるんだよ。

電力を見直したい
設計図が組み込まれるんですか! つまり、元々毒を作れなかった細菌が、毒を作れるようになるってことですか?

電力の研究家
その通り! 形質転換によって、細菌は全く新しい能力を獲得することができるんだ。この発見は、遺伝子がDNAという物質によって受け継がれているという証拠の一つにもなったんだよ。
形質転換とは。
「形質転換」という言葉を原子力発電の分野で使うことがあります。これは、ある細菌の性質が、別の細菌から受け取った遺伝子の情報によって変わることを指します。分かりやすく説明すると、毒性を持たない細菌に、毒性を持つ細菌から取り出した遺伝子の情報を与えると、毒性を持つようになる現象です。この現象は、1928年にグリフィスという学者が肺炎を起こす細菌を使って発見しました。彼は、毒性のない細菌が、毒性のある細菌から取り出した物質によって毒性を帯びることを突き止めました。そして、1944年、アヴェリーという学者が、その物質が遺伝子の情報を持つDNAであることを明らかにしました。このような現象は、哺乳類の細胞でも確認されています。
遺伝子が変化する?形質転換とは
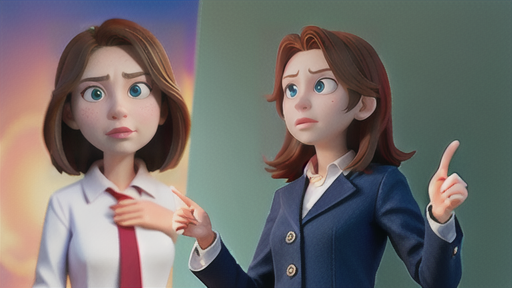
生き物の特徴を決める設計図、それが遺伝子です。通常、遺伝情報は親から子へと受け継がれていきます。しかし、時には全く異なる個体間で、遺伝情報の一部が移動することがあります。これを「形質転換」と呼びます。
形質転換は、ある生物から別の生物へ、遺伝情報の一部を移し替える操作です。例えば、毒素を作らない無毒な細菌を想像してみてください。この細菌に、毒素を作る細菌から取り出した遺伝情報を与えると、無毒だった細菌が毒素を作るようになる、という驚きの変化が起こり得るのです。
このように、形質転換は、ある生物の持つ性質を、別の生物に与えることができる現象です。これは、遺伝子が生物の設計図としての役割を持つことを示すだけでなく、生物の性質を人工的に変えることができる可能性を示唆しています。形質転換は、医学や農学などの分野で、新しい薬や品種の開発に役立てられています。
| 用語 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 遺伝子 | 生き物の特徴を決める設計図 | – |
| 形質転換 | 異なる個体間で遺伝情報の一部が移動する現象。 生物の性質を人工的に変えることができる。 |
毒素を作らない細菌に、毒素を作る細菌の遺伝情報を与えると毒素を作るようになる。 |
肺炎球菌を使った実験と形質転換の発見

1928年、イギリスの細菌学者フレデリック・グリフィスは、肺炎を引き起こす細菌である肺炎球菌を使って、後に「形質転換」と呼ばれることになる重要な生物学的現象を発見しました。この発見は、遺伝情報がどのように伝達されるのかを理解する上で、画期的な出来事となりました。
グリフィスは、毒性の強い肺炎球菌と毒性のない肺炎球菌を用いて、一連の実験を行いました。彼はまず、毒性の強い肺炎球菌を加熱処理して殺し、この死んだ細菌をマウスに注射しました。予想通り、マウスは肺炎を発症しませんでした。次に、グリフィスは、加熱殺菌した毒性の強い肺炎球菌と、生きている無毒の肺炎球菌を混ぜてマウスに注射しました。すると驚くべきことに、マウスは肺炎を発症して死んでしまったのです。さらに、死んだマウスからは、生きた毒性の強い肺炎球菌が検出されました。
このことから、グリフィスは、加熱殺菌された毒性の強い肺炎球菌の中に、無毒の肺炎球菌を毒性のある肺炎球菌に変える物質が存在すると考えました。この未知の物質は、死んだ細菌から生きている細菌へと遺伝情報を伝達し、その性質を変化させる能力を持っていたのです。グリフィスはこの物質を「形質転換因子」と名付けました。後の研究により、この「形質転換因子」の正体はDNAであることが明らかになりました。
| 実験 | 内容 | 結果 |
|---|---|---|
| 1 | 加熱処理した毒性の強い肺炎球菌をマウスに注射 | マウスは生存 |
| 2 | 生きている無毒の肺炎球菌をマウスに注射 | マウスは生存 |
| 3 | 加熱処理した毒性の強い肺炎球菌と生きている無毒の肺炎球菌を混ぜてマウスに注射 | マウスは死亡、生きた毒性の強い肺炎球菌が検出 |
形質転換の担い手:DNAの特定

1928年、イギリスの細菌学者フレデリック・グリフィスは、肺炎球菌を用いた実験で、遺伝情報を担う物質が存在することを示唆しました。これを「形質転換」と呼びますが、この物質の正体は謎のままでした。それから16年後、アメリカの医学研究者オズワルド・アベリーらはこの謎に挑みました。
アベリーらは、グリフィスが実験に使用したのと同じ肺炎球菌を用い、加熱殺菌した毒性のある肺炎球菌をすりつぶして様々な成分に分離しました。そして、それぞれの成分を無毒の肺炎球菌に混ぜて培養し、形質転換が起きるかを観察したのです。
実験の結果、タンパク質や多糖類などを加えても無毒の肺炎球菌は毒性を持ちませんでしたが、DNAを加えた場合のみ、無毒の肺炎球菌が毒性を持つようになったのです。このことから、アベリーらは「形質転換因子」、すなわち遺伝子の本体はDNAであると結論付けました。
この発見は、それまで遺伝子の正体と考えられていたタンパク質ではなく、DNAこそが遺伝情報を担う物質であることを明確に示しました。この成果は、その後の分子生物学の発展に大きく貢献し、ワトソンとクリックによるDNAの二重らせん構造の発見へとつながる、重要な一歩となりました。
| 実験 | 結果 | 結論 |
|---|---|---|
| 加熱殺菌した毒性肺炎球菌をすりつぶして成分に分離し、無毒肺炎球菌に混ぜて培養 | DNAを加えた場合のみ、無毒肺炎球菌が毒性を持つようになった | DNAは「形質転換因子」であり、遺伝子の本体である |
形質転換:自然界と応用

生物が遺伝情報であるDNAを獲得し、その性質を変える現象を形質転換と言います。形質転換は、何も実験室の中だけで起こる特別な現象ではありません。自然界でも、様々な場面で細菌などによって行われています。では、一体どのようにして、自然界で形質転換が起こるのでしょうか?細菌は、周りの環境からDNAを取り込む能力を持っています。そして、取り込まれたDNAが持つ遺伝情報が、その細菌自身のもつ遺伝情報に組み込まれることで、新たな性質を獲得することがあります。この現象こそが、自然界における形質転換です。細菌にとって、形質転換は厳しい環境下を生き抜くための有効な手段になりえます。例えば、抗生物質が散らばる環境に生息する細菌の中には、抗生物質を分解する酵素を作る遺伝情報を獲得し、抗生物質に対する耐性を獲得するものもいます。このようにして獲得された耐性遺伝子は、形質転換によって他の細菌にも広がっていく可能性があります。抗生物質の過剰な使用が問題視される現代において、細菌の形質転換は、薬剤耐性菌の出現と拡散に深く関わる現象として、私たち人類にとっても決して軽視できない問題なのです。一方、この形質転換の仕組みは、人類にとって有益な技術にも応用されています。それが遺伝子組み換え技術です。この技術では、特定の遺伝子を細胞に導入し、その遺伝子が持つ働きを利用することで、様々な分野に役立つ技術の開発が可能になります。例えば、ある種のタンパク質を作る遺伝子を植物に導入することで、病気に強い作物の品種改良を行ったり、栄養価の高い食品を開発したりすることが可能になります。また、医療の分野では、インスリンなどの不足するホルモンを体内で作れるようにする遺伝子治療の開発も進められています。このように、形質転換は、食糧問題や医療といった人類共通の課題解決にも貢献できる可能性を秘めた技術と言えるでしょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 形質転換とは | 生物が外部からDNAを取り込み、自身の性質を変える現象 |
| 自然界での形質転換 | 細菌などが周りの環境からDNAを取り込み、新たな性質を獲得する。 例:抗生物質耐性遺伝子の獲得と拡散 |
| 遺伝子組み換え技術への応用 | 特定の遺伝子を細胞に導入し、その遺伝子の働きを利用する技術。 例:
|
