「もんじゅ」:日本の高速増殖炉開発の道のり

電力を見直したい
『もんじゅ』って原子力発電の施設の名前だって聞いたんですけど、どんな施設なんですか?

電力の研究家
いい質問だね。『もんじゅ』は、福井県敦賀市にある高速増殖炉という種類の原子力発電施設なんだ。高速増殖炉は、普通の原子力発電所とは違う特徴を持っているんだよ。

電力を見直したい
普通の原子力発電所と何が違うんですか?

電力の研究家
簡単に言うと、燃料を燃やすだけでなく、燃料を増やすこともできる施設なんだ。夢の原子炉とも呼ばれていたんだよ。でも、事故やトラブルもあったので、今は動いていないんだ。
もんじゅとは。
「もんじゅ」は、福井県敦賀市にある、日本で初めて作られた高速増殖炉の名前です。これは、かつての動力炉・核燃料開発事業団(今の日本原子力研究開発機構)が開発しました。1968年から設計と建設が始まり、熱出力は714MW、発電能力は約280MWあります。燃料には、炉の中心部ではプルトニウムとウランの混合酸化物、周りを囲む部分にはウランを使います。この炉は、使った燃料よりも多くの燃料を作ることができ、その割合は約1.2倍です。1983年5月に設置が許可され、1991年5月18日に完成、1994年4月に核分裂が開始され、1995年8月29日に初めて電気を送りました。しかし、1995年12月8日に、冷却材であるナトリウムが漏れる事故が起きてしまいました。その後、1998年3月に安全に関する報告書をまとめ、2005年2月には福井県などから、ナトリウム漏えいを防ぐための工事を進める了解を得て、運転再開に向けて工事が始まりました。2007年度末には一通りの工事と試験が終わり、2008年度初めには核分裂の試験を行う予定でした。「もんじゅ」という名前は、「ふげん」とともに、仏様の脇に仕える菩薩の名前からつけられました。
夢の原子炉
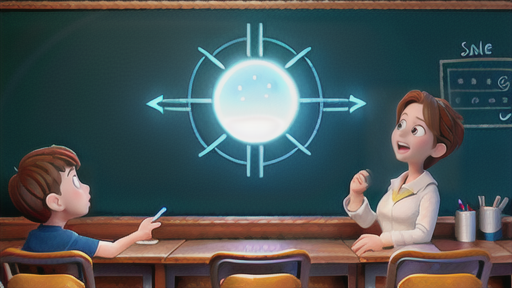
「もんじゅ」は、日本のエネルギー問題解決の切り札として、「夢の原子炉」と期待を込めて呼ばれていました。従来の原子炉とは異なり、ウラン燃料をより効率的に活用できる高速増殖炉という技術を採用していました。高速増殖炉は、ウランを核分裂させてエネルギーを取り出すだけでなく、その過程で発生する中性子を吸収させてプルトニウムを生成します。生成されたプルトニウムは、再び燃料として使用することができるため、資源の有効利用に大きく貢献します。さらに、使用済み核燃料からプルトニウムを取り出して再利用することで、核廃棄物の量を大幅に減らすことも期待されていました。このように、「もんじゅ」はエネルギーの自給率向上と環境負荷低減の両面から、日本の未来を担う夢の技術として、大きな注目を集めていたのです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 愛称 | 夢の原子炉 |
| 目的 | 日本のエネルギー問題解決 |
| 技術 | 高速増殖炉 |
| 特徴 | – ウラン燃料をより効率的に活用 – 核分裂でエネルギーを取り出す – 中性子を吸収させてプルトニウムを生成 – 生成したプルトニウムを燃料として再利用 |
| メリット | – 資源の有効利用 – 核廃棄物の量の大幅な削減 – エネルギーの自給率向上 – 環境負荷低減 |
福井県敦賀の地で

雄大な自然が広がる福井県敦賀の地で、1968年、日本の原子力開発史に新たなページが刻まれようとしていました。「もんじゅ」と名付けられた高速増殖炉の設計・建設計画が、まさにその場所で始動したのです。当時、未来のエネルギー源として大きな期待を寄せられていた高速増殖炉は、従来の原子炉とは異なる、より高度な技術を要するものでした。設計から建設に至るまで、20年以上にわたる歳月が費やされ、延べ1000万人以上もの技術者や作業員がその巨大プロジェクトに携わりました。そして、1991年5月18日、幾多の困難を乗り越え、「もんじゅ」はついに完成の時を迎えます。熱出力714MW、電気出力約280MWという、当時世界最大級の高速増殖炉は、まさに日本の技術力の粋を集めた結晶であり、多くの関係者の熱い情熱とたゆまぬ努力の証でもありました。敦賀の地で産声を上げた「もんじゅ」は、日本の原子力開発の未来を担う希望の光として、大きく羽ばたこうとしていたのです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施設名 | もんじゅ |
| 炉型 | 高速増殖炉 |
| 建設地 | 福井県敦賀 |
| 計画開始 | 1968年 |
| 建設期間 | 約20年以上 |
| 関係者数 | 延べ1000万人以上 |
| 完成日 | 1991年5月18日 |
| 熱出力 | 714MW |
| 電気出力 | 約280MW |
困難な道のり

1995年8月29日、福井県敦賀市に建設された高速増殖炉「もんじゅ」は、長年の開発期間を経てついに初送電を達成しました。これは日本の原子力開発にとって歴史的な一歩であり、将来のエネルギー源として大きな期待が寄せられました。しかし、その喜びも束の間、わずか数か月後の12月8日、「もんじゅ」は2次冷却系ナトリウムの漏えい事故を起こしてしまいます。
この事故は、原子炉本体ではなくても、放射性物質を含むナトリウムが漏えいする可能性を示したことから、社会に大きな衝撃を与えました。想定外の事故発生により、「もんじゅ」の安全性に対する信頼は大きく揺らいでしまいました。
その後、事故原因の究明や再発防止策の検討など、運転再開に向けた取り組みが行われましたが、その道のりは決して平坦ではありませんでした。国民の不安や不信は根強く、運転再開に慎重な意見も多くありました。結局、「もんじゅ」はその後一度も運転再開を果たすことなく、2016年に廃炉が決まりました。
| 日付 | 出来事 | 備考 |
|---|---|---|
| 1995年8月29日 | 高速増殖炉「もんじゅ」初送電達成 | 日本の原子力開発にとって歴史的一歩 |
| 1995年12月8日 | 「もんじゅ」2次冷却系ナトリウム漏えい事故発生 | 原子炉本体以外からの放射性物質漏えいの可能性を示し、社会に衝撃を与える |
| 1995年~2016年 | 事故原因究明、再発防止策検討など、運転再開に向けた取り組みが行われるも、国民の不安や不信は根強く、再開は困難を極める。 | |
| 2016年 | 「もんじゅ」廃炉決定 |
再運転への挑戦

– 再運転への挑戦あの事故の後、発電所は長く運転を停止していました。国民の皆様に再び安心して電気をお届けできるよう、徹底的な安全点検と、事故の教訓を活かした大規模な改造工事を行いました。そして、長い年月を経て、2007年度末には、ようやく一連の工事を完了させることができました。翌2008年度初頭には、原子炉が安全に起動できるかを確認するための臨界試験の実施を予定していました。ところが、再稼働に向けた準備を進める中で、様々な問題点が新たに浮上してきました。想定外の箇所の劣化や、部品の不具合など、安全を最優先に考えれば、解決しなければならない課題が次々と見つかったのです。これらの問題を放置することは許されません。関係機関と連携し、一つ一つの問題に対して原因の究明と対策を進めていきましたが、その作業には膨大な時間と労力を要しました。そのため、当初予定していたスケジュールは大幅に遅延し、再稼働を実現するには至らなかったのです。
| フェーズ | 内容 | 結果 |
|---|---|---|
| 事故後 |
|
2007年度末に工事完了 |
| 2008年度初頭 | 臨界試験(原子炉が安全に起動できるかを確認する試験)を予定 | 様々な問題点が新たに浮上したため延期 |
| 問題発生時 |
|
関係機関と連携し、原因の究明と対策を実施 |
| 現在 |
|
再稼働に至らず |
「もんじゅ」の教訓

– 「もんじゅ」の教訓
福井県に建設された高速増殖炉「もんじゅ」は、従来の原子炉とは異なる新しい仕組みを持つ、未来のエネルギー源として大きな期待を集めていました。しかし、1995年のナトリウム漏れ事故をはじめとする様々なトラブルにより、長期間にわたって運転が停止。そして、2016年には廃炉が決定されました。「もんじゅ」の道のりは、革新的な技術の実用化には、克服すべき課題が山積していることを改めて私たちに示しました。
「もんじゅ」の開発においては、高度な技術力に加えて、安全性の確保が最も重要な課題でした。高速増殖炉は、従来の原子炉とは異なる燃料や冷却材を使用するため、その安全性について社会に丁寧に説明し、理解と信頼を得ることが不可欠でした。しかし、度重なるトラブルや情報公開の遅れにより、社会の不安を増大させてしまった側面は否めません。
「もんじゅ」の経験は、今後の原子力開発、特に新しい技術の導入において、技術的な課題解決と同時に、社会との対話を重視し、透明性の高い情報公開を進めることの重要性を明確にしました。国民の理解と信頼なくして、原子力開発を進めることは不可能です。私たちは「もんじゅ」の教訓を胸に、安全で持続可能な社会の実現に向けて歩み続ける必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期待された役割 | 従来の原子炉とは異なる新しい仕組みを持つ、未来のエネルギー源 |
| 主な出来事 | – 1995年 ナトリウム漏れ事故 – 長期間の運転停止 – 2016年 廃炉決定 |
| 教訓 | – 革新的な技術の実用化には課題が多い – 高度な技術力に加えて安全性の確保が重要 – 社会への丁寧な説明と理解と信頼の獲得が不可欠 – トラブルや情報公開の遅れは社会の不安を増大させる – 技術的な課題解決と同時に社会との対話、透明性の高い情報公開が必要 |
未来への展望

– 未来への展望
日本は、エネルギー資源の乏しい島国という宿命を背負っています。そのため、エネルギーの安定供給は、国の発展と国民生活の安定にとって非常に重要な課題です。そのような中で、従来型の原子力発電に加えて、より効率的にウラン資源を活用できる高速増殖炉技術への期待が高まっています。高速増殖炉は、発電しながら燃料を増やすことができる夢の原子炉として、長年研究開発が進められてきました。
「もんじゅ」は、日本における高速増殖炉開発の先駆けとして、多くの期待を背負って建設されました。しかしながら、度重なるトラブルや厳しい安全基準への適合性の問題などから、最終的には再稼働を断念することとなりました。これは非常に残念な結果ではありますが、「もんじゅ」の開発過程で得られた貴重なデータや経験は、決して無駄になることはありません。
「もんじゅ」の開発で培われた技術や知見は、将来の高速炉開発に確実に引き継がれていきます。例えば、ナトリウム冷却材の安全性に関するデータや、高速中性子に対する材料の耐久性に関する知見などは、次世代の高速炉開発において非常に重要な役割を果たすでしょう。今後も、国内外の研究機関と連携しながら、高速増殖炉技術の研究開発を継続していくことが重要です。そして、将来のエネルギー問題解決に向けて、日本の技術力を結集し、安全で安定したエネルギー供給を実現していく必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 日本のエネルギー事情 | エネルギー資源の乏しい島国であり、エネルギーの安定供給が国の発展と国民生活の安定にとって非常に重要。 |
| 高速増殖炉への期待 | 従来型の原子力発電に加えて、ウラン資源をより効率的に活用できる高速増殖炉技術への期待が高まっている。 |
| 「もんじゅ」の成果と課題 | 高速増殖炉開発の先駆けとして建設されたが、トラブルや安全基準適合性の問題から再稼働を断念。しかし、開発過程で得られたデータや経験は将来の高速炉開発に活かされる。 |
| 今後の展望 | 「もんじゅ」の技術や知見を次世代の高速炉開発に活用。国内外の研究機関と連携し、高速増殖炉技術の研究開発を継続し、安全で安定したエネルギー供給の実現を目指す。 |
