原子力発電の将来を支える資源: 推定追加資源量とは?

電力を見直したい
「推定追加資源量」って、確認資源量と比べて、どれくらい不確かなものなんですか?

電力の研究家
良い質問ですね。「推定追加資源量」は、直接的・間接的な地質学的兆候はあるものの、確認資源量に比べると、存在の確実性や量の正確さについては低いとされています。

電力を見直したい
じゃあ、どのくらいの確実性があれば「確認資源量」になるんですか?

電力の研究家
「確認資源量」は、実際にボーリング調査を行って、量や質が確認されたものです。つまり、「推定追加資源量」は、まだボーリング調査などで裏付けられていない段階と言えますね。
推定追加資源量とは。
「推定追加資源量」は、原子力発電に使うウラン資源の量を表す言葉です。これは、確実に見つかる資源量に比べると、不確かさが大きいものの、地質学的な根拠から存在すると推定されるウラン資源量を指します。この概念は、経済協力開発機構の原子力機関と国際原子力機関の共同調査で使われていましたが、2003年版の報告書までしか使われませんでした。
推定追加資源量は、英語で「Estimated Additional Resources」と書くことから、「EAR」と略されることもあります。EARは、さらに「EAR-I」と「EAR-II」の二つに分けられます。EAR-Iは、地質学的な調査である程度存在が推測できるものの、質や量の詳しい情報が不足しているものを指します。一方、EAR-IIは、間接的な情報ではあるものの、信頼性の高い地質学的な根拠に基づいて存在が推測されるものを指します。
2005年版の報告書からは、EAR-Iは「推定資源量」、EAR-IIは「予測資源量」と呼ばれるようになり、それぞれ異なる分類に分けられました。推定資源量は、確実に見つかるとされる資源量と合わせて「発見資源量」に、予測資源量は、将来的に見つかることが期待される資源量と合わせて「未発見資源量」に分類されるようになりました。この変更により、「推定追加資源量」という言葉は、特に重要な意味を持たなくなりましたが、2007年版の報告書でも、推定資源量と予測資源量の分類は引き続き使われています。
資源量の分類と推定追加資源量の登場

原子力発電の燃料であるウラン。その資源量は、どのように見積もられているのでしょうか?ウラン資源量は、存在の確実性と経済性という2つの要素を基準に、いくつかの段階に分類されます。
まず、存在がほぼ確実で、現在の技術や経済状況で採掘可能なウラン資源量は「確認資源量」と呼ばれます。一方、存在する可能性は低いものの、将来的な技術革新や価格の上昇によって採掘が可能になるかもしれないウラン資源量は「予測資源量」と呼ばれます。このように、ウラン資源量は確実性と経済性に応じて、段階的に分類されているのです。
こうした資源量の分類の中で、かつて重要な役割を担っていたのが「推定追加資源量」です。確認資源量ほど存在の確実性は高くありませんが、地質学的兆候に基づいて存在が推定されるウラン資源量を指します。2003年版までは、経済協力開発機構原子力機関(OECD/NEA)と国際原子力機関(IAEA)が共同で発行する調査報告書において、資源量評価の重要な指標として用いられていました。しかし、その後の報告書からは、評価基準の変更に伴い、推定追加資源量の記載はなくなりました。
| ウラン資源量の分類 | 説明 |
|---|---|
| 確認資源量 | 存在がほぼ確実で、現在の技術や経済状況で採掘可能なウラン資源量 |
| 予測資源量 | 存在する可能性は低いものの、将来的な技術革新や価格の上昇によって採掘が可能になるかもしれないウラン資源量 |
| 推定追加資源量(2003年版まで) | 確認資源量ほど存在の確実性は高くありませんが、地質学的兆候に基づいて存在が推定されるウラン資源量。2004年版以降は、評価基準の変更に伴い、記載なし。 |
推定追加資源量の区分: EAR-IとEAR-II

原子力発電の燃料となるウランは、地球上の様々な場所に存在しますが、その埋蔵量を正確に把握することは容易ではありません。そこで、資源量の推定には、その確実性に応じて段階的な区分が用いられます。この区分の一つに「推定追加資源量」がありますが、これはさらにEAR-IとEAR-IIの二つのカテゴリーに分類されます。
EAR-Iは、地質調査によってウランの存在を示す直接的な兆候が確認されているものの、詳細な情報が不足しているために、その規模や品質を正確に評価できない資源量を指します。例えば、ウラン鉱床の一部が実際に確認されているものの、その全体像やウランの含有量が未確定な場合などがこれに該当します。
一方、EAR-IIは、直接的な地質学的兆候は乏しいものの、地質構造や周辺地域のウラン鉱床の存在など、間接的な情報からウランの存在する可能性が高いと推定される資源量を指します。EAR-IIはEAR-Iに比べて不確実性が高いと言えるでしょう。
このように、推定追加資源量は、地質学的データに基づく確実性の度合いによって、EAR-IとEAR-IIに区分されることで、より詳細な資源量の評価が可能となっています。
| 区分 | 説明 | 確実性 | 例 |
|---|---|---|---|
| EAR-I | 直接的な兆候でウランの存在は確認済み 規模や品質は未確定 |
比較的高い | 鉱床の一部は確認済みだが、全体像や含有量は不明 |
| EAR-II | 直接的な兆候は乏しい 間接的な情報からウランの存在可能性あり |
低い | 周辺地域にウラン鉱床が存在するなど |
資源量分類の改定と推定追加資源量の終焉
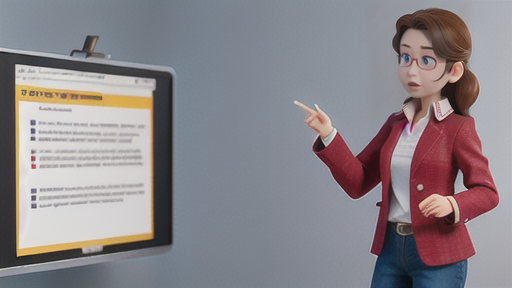
2005年、経済協力開発機構原子力機関(OECD/NEA)と国際原子力機関(IAEA)は、資源量の分類方法を改定しました。この改定は、資源量の評価をより正確で分かりやすくすることを目的としていました。
大きな変更点の一つとして、従来の「推定追加資源量 (Estimated Additional Resources – EAR)」という概念が廃止されました。EARは、EAR-IとEAR-IIの二つに区分されていましたが、この区分はそれぞれ「推定資源量 (Inferred Resources)」と「予測資源量 (Prognosticated Resources)」に名称が変更されました。
さらに、資源量は「発見資源量 (Identified Resources)」と「未発見資源量 (Undiscovered Resources)」の二つに大別されることになりました。発見資源量は、実際に確認された資源量である「確認資源量 (Reasonably Assured Resources)」と、推定資源量を合わせたものを指します。一方、未発見資源量は、存在の可能性はあるものの、具体的な埋蔵場所や規模が未確認の資源量を指し、予測資源量と期待資源量 (Speculative Resources)を含みます。
このように、資源量分類の改定によって、従来の推定追加資源量という概念は明確な位置づけを失い、使用されなくなりました。資源量の評価は常に進化しており、より正確で透明性の高い資源量の把握に向けて、国際機関による継続的な取り組みが行われています。
| 資源量分類 | 説明 |
|---|---|
| 発見資源量 (Identified Resources) | |
| 確認資源量 (Reasonably Assured Resources) | 実際に確認された資源量 |
| 推定資源量 (Inferred Resources) (旧: EAR-I) |
確認資源量に加えて、地質学的類似性などから推定される資源量 |
| 未発見資源量 (Undiscovered Resources) | |
| 予測資源量 (Prognosticated Resources) (旧: EAR-II) |
地質学的知見に基づき、存在が予測される資源量 |
| 期待資源量 (Speculative Resources) | 既存の知見から存在する可能性が期待される資源量 |
資源評価の進化と将来展望: 推定追加資源量の教訓

– 資源評価の進化と将来展望 推定追加資源量の教訓資源とは、人間活動にとって有用な物質やエネルギーの源泉であり、その中でも特にウランは原子力発電の燃料として重要な役割を担っています。資源を有効に活用するためには、賦存量の把握が不可欠ですが、地下に眠る資源の量を正確に知ることは容易ではありません。そこで用いられるのが資源量評価という手法です。従来の資源量評価においては、「推定追加資源量」という概念が存在しました。これは、既知の鉱床周辺や、地質学的データに基づいて資源の存在が期待される地域から、将来的に発見・採掘が見込まれる資源量を推定したものです。しかしながら、推定追加資源量は、その不確実性の高さから、2005年以降、国際的に認められた資源量分類からは姿を消しました。推定追加資源量の変遷は、資源量評価が常に進化を続けるものであることを示しています。地質学的知識や調査技術の進歩、経済状況の変化など、様々な要因によって資源量評価は影響を受けます。例えば、新たな分析技術の導入によって、従来は採算が取れないとされていた低品位の鉱石からも、資源として回収が可能になるといったことも起こりえます。原子力発電の未来を考える上で、ウラン資源量の正確な評価は極めて重要です。過去の資源量評価の変遷から学び、私たちは常に最新の知識と技術に基づいた、より精度の高い資源量評価を目指していく必要があります。また、資源の安定供給を確保するために、資源開発技術の向上や、リサイクル技術の確立などにも積極的に取り組んでいく必要があります。資源量評価の進化は、エネルギーの未来を左右する重要な課題と言えるでしょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資源の定義 | 人間活動にとって有用な物質やエネルギーの源泉 |
| ウランの重要性 | 原子力発電の燃料として重要な役割 |
| 資源量評価の必要性 | 資源の有効活用には賦存量の把握が不可欠 |
| 推定追加資源量 | – 既知の鉱床周辺や、地質学的データに基づいて資源の存在が期待される地域から、将来的に発見・採掘が見込まれる資源量を推定したもの – 不確実性の高さから、2005年以降、国際的に認められた資源量分類からは姿を消した |
| 資源量評価の進化要因 | – 地質学的知識や調査技術の進歩 – 経済状況の変化 – 例:新たな分析技術の導入による低品位鉱石からの資源回収 |
| ウラン資源量評価の重要性 | 原子力発電の未来を考える上で極めて重要 |
| 資源の安定供給確保のための取り組み | – 資源開発技術の向上 – リサイクル技術の確立 |
