高温環境の難敵:クリープ現象とその影響

電力を見直したい
先生、クリープって言葉が出てきたのですが、どういう意味ですか?

電力の研究家
良い質問ですね!クリープは、高温で長時間力がかかり続けると、ものがゆっくり変形していく現象のことだよ。例えば、熱いお湯に長時間つけたプラスチックのコップが、だんだん変形していくのをイメージすると分かりやすいかな?

電力を見直したい
なるほど!高温でなくても、長時間経てば変形するんですか?

電力の研究家
クリープは特に高温で起きやすい現象なんだ。常温でも長い年月をかければ変形することはあるけど、高温だとそれが顕著に現れるんだね。だから、原子力発電のように高温で稼働する機器では特に注意が必要なんだよ。
クリープとは。
「クリープ」は、原子力発電などで使われる専門用語の一つです。高温で物体に一定の力がかかり続けると、時間とともに物体がゆっくりと変形していく現象を指します。これは、物質を構成する小さな粒の境界での流れや、粒内部でのずれが原因だと考えられています。鉄の一種である鋼では、およそ300度からこの現象が始まります。一定の温度と重さの下では、クリープは時間の経過とともに、(1)変形の速度が徐々に遅くなる時期、(2)変形の速度が一定になる時期、(3)変形の速度が再び速くなり、最終的に壊れる時期、という3つの段階に分けられます。ものづくりにおいては、高温状態でのクリープの速度と、クリープによって壊れるまでの強さが特に重要視されています。
クリープ現象とは

– クリープ現象とは
物質は、高い温度に置かれると、たとえ溶けるほど熱くなくても、ゆっくりと形を変えることがあります。これをクリープ現象と呼びます。
例えば、ろうそくに火を灯し続けると、ろうが溶け出す前から徐々に曲がってきてしまう現象を見たことがあるでしょう。これは、ろう自身の重さによって、時間をかけてゆっくりと変形していくクリープ現象の一例です。
クリープ現象は、高温で動作する機械や構造物にとって、大きな問題となる可能性があります。例えば、火力発電所や原子力発電所などで使用されるタービンや配管などは、常に高温高圧の環境下に置かれています。このような環境下では、たとえ材料の強度よりも低い力であっても、長い時間をかけて力が加わり続けることで、クリープ現象によって変形や破損が起こる可能性があります。
クリープ現象は、材料の選択や設計、運転条件の管理などによって抑制することができます。そのため、高温で使用する機器や構造物を設計する際には、クリープ現象による影響を考慮することが重要です。
| 現象 | 説明 | 影響 | 対策 |
|---|---|---|---|
| クリープ現象 | 高温下で長時間力が加わることで、材料がゆっくりと変形する現象。 | 機械や構造物の変形や破損に繋がる可能性がある。 | 材料の選択、設計、運転条件の管理を行う。 |
クリープ現象の発生メカニズム

物質は一見すると滑らかで均一に見えますが、実際には無数の微小な結晶が集まってできています。顕微鏡で観察すると、この結晶同士の境界線が網目のように広がっているのが分かります。実は、この結晶の境界部分こそが、クリープ現象と呼ばれる現象を引き起こす重要な場所なのです。
クリープ現象とは、一定の力が加わった状態で、時間が経過するにつれて物質が変形していく現象を指します。高温環境下では、物質を構成する原子は活発に運動しています。特に、結晶の境界部分では原子の配列が乱れているため、原子は比較的動きやすい状態にあります。高温になると、この原子の運動エネルギーがさらに大きくなるため、原子は結晶の境界部分を移動しやすくなるのです。これが、高温でクリープ現象が顕著に現れる理由です。
物質の構造や温度、負荷される力によって、クリープ現象の進行速度は大きく変化します。例えば、結晶のサイズが小さく、境界部分が多い物質ほど、クリープ現象は進行しやすくなります。また、高温になるほど原子の運動エネルギーが大きくなるため、クリープの進行速度は速くなります。さらに、負荷される力が大きくなると、原子が移動しやすくなるため、やはりクリープ現象は加速します。このように、クリープ現象は様々な要因が複雑に関係し合って発生する現象なのです。
| 要因 | クリープ現象への影響 |
|---|---|
| 物質の構造 |
|
| 温度 |
|
| 負荷される力 |
|
クリープ現象の段階
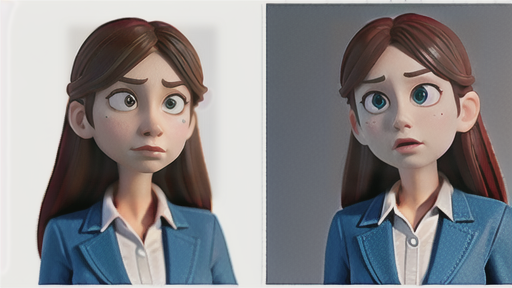
物体が長時間、一定の力にさらされ続けると、時間とともに変形が進みます。この現象をクリープ現象と呼びますが、クリープ現象は時間の経過とともにその変形速度が変化することが知られており、大きく3つの段階に分けられます。
最初の段階は、一次クリープと呼ばれ、変形速度は時間とともに徐々に減速していきます。これは、材料内部で変形を抑えようとする力が働くためです。例えば、バネを思い浮かべてください。バネを引っ張ると、最初は勢いよく伸びますが、次第に伸びがゆっくりになっていきますよね。これは、バネ自身が元の形に戻ろうとする力が働くためです。一次クリープでも、これと似たような現象が起きています。
次の段階は、二次クリープと呼ばれ、変形速度はほぼ一定になります。この段階では、材料内部で変形を進めようとする力と、変形を抑えようとする力が釣り合っている状態です。この段階は、比較的長い期間続くことが特徴です。
最後の段階は、三次クリープと呼ばれ、変形速度が再び増加し、最終的には破壊に至ります。この段階では、材料内部に微小な亀裂などが発生し、それが成長することで破壊が引き起こされます。例えば、粘土をイメージしてみてください。粘土をゆっくりと引っ張っていくと、最初は形を変えますが、ある程度のところでちぎれてしまいますよね。これは、粘土に小さな亀裂が入り、それが大きくなっていくことで、最終的にちぎれてしまうのです。三次クリープでも、これと似たような現象が起きています。
| クリープ段階 | 特徴 | 例え |
|---|---|---|
| 一次クリープ | 変形速度は時間とともに徐々に減速 | バネの伸びが次第にゆっくりになる |
| 二次クリープ | 変形速度はほぼ一定 | – |
| 三次クリープ | 変形速度が再び増加し、最終的には破壊に至る | 粘土を引っ張るとちぎれる |
クリープ現象がもたらす影響

発電所の中でも、特に火力発電所や原子力発電所のように高い温度で運転される施設では、クリープ現象と呼ばれる現象が大きな問題として立ちはだかります。この現象は、金属材料が高温に長時間さらされることで、負荷がかかっていなくても徐々に変形してしまう現象を指します。
高温高圧の蒸気を扱う配管などを例に挙げると、これらの配管はクリープ現象によって設計時の形状から変形し、本来の機能である蒸気の輸送を適切に行えなくなる可能性があります。最悪の場合、蒸気漏れや配管の破損といった深刻な事態を引き起こし、発電所の運転停止や周辺環境への影響、さらには人命に関わる重大な事故につながる危険性も孕んでいます。
このような事態を避けるため、火力発電所や原子力発電所では、クリープ現象への対策が最も重要な課題の一つとして位置付けられています。具体的には、クリープ現象に強い耐熱合金の使用や、運転温度と圧力の管理、定期的な点検による設備の劣化状況の把握など、様々な対策が講じられています。
| 現象 | 内容 | 影響とリスク | 対策 |
|---|---|---|---|
| クリープ現象 | 高温に長時間さらされることで、金属材料が負荷がかかっていなくても徐々に変形する現象 |
|
|
クリープ現象への対策

原子力発電所などの高温・高圧環境下では、金属材料は時間経過と共にゆっくりと変形する「クリープ現象」を起こすことがあります。この現象は、発電所の安全運転に大きな影響を与える可能性があるため、様々な対策が講じられています。
まず、クリープ現象への対策として最も重要なのは、耐クリープ性に優れた材料を選ぶことです。高温でも変形しにくい特殊な合金などが開発されており、発電所の設計条件や運転温度に応じて最適な材料が選定されます。例えば、配管やタービンなど高温にさらされる部位には、ニッケルやクロムなどを含んだ耐熱合金が使われています。
設計の段階でも、クリープ現象を考慮することが重要です。具体的には、コンピュータシミュレーションなどを用いて、運転中の温度や圧力条件におけるクリープによる変形量を予測し、その影響を最小限に抑える設計を行います。例えば、部材の厚さを増やしたり、形状を工夫したりすることで、クリープによる変形を抑制することができます。
さらに、定期的な検査やメンテナンスも欠かせません。運転中に材料の状態を監視し、クリープ現象の発生状況を早期に発見することで、重大な事故を未然に防ぐことができます。検査では、非破壊検査などを用いて、材料の内部に発生した微小なき裂などを検出します。もし、クリープ現象による損傷が確認された場合は、部品の交換などの適切な処置を行います。
| 対策 | 詳細 | 例 |
|---|---|---|
| 耐クリープ性に優れた材料を選ぶ | 高温でも変形しにくい特殊な合金などを、発電所の設計条件や運転温度に応じて選定する。 | 配管やタービンなど高温にさらされる部位には、ニッケルやクロムなどを含んだ耐熱合金が使われている。 |
| クリープ現象を考慮した設計 | コンピュータシミュレーションなどを用いて、運転中の温度や圧力条件におけるクリープによる変形量を予測し、その影響を最小限に抑える。 | 部材の厚さを増やしたり、形状を工夫したりすることで、クリープによる変形を抑制する。 |
| 定期的な検査やメンテナンス | 運転中に材料の状態を監視し、クリープ現象の発生状況を早期に発見する。 | 非破壊検査などを用いて、材料の内部に発生した微小なき裂などを検出する。損傷が確認された場合は、部品の交換などの適切な処置を行う。 |
