地震の発生場所: 震央とは

電力を見直したい
先生、地震の震源と震央の違いがよく分からないのですが…

電力の研究家
なるほど。簡単に言うと、震源は地面の中で地震が起きた場所、震央は震源の真上の地面の地点のことだよ。

電力を見直したい
じゃあ、震源は地下で、震央は地上にあるっていうことですか?

電力の研究家
その通り!例えば、海の底で地震が起きたとする。この時、海の底で地震が起きた場所が震源で、その真上の海の表面が震央になるんだね。
震央とは。
地震は、地球の表面の下で起こる急な動きが原因で発生します。この動きが始まった場所を「震源」と呼びます。そして、その真上にある地上の点を「震央」と言います。震央は、地図上で緯度と経度を使って表されます。
地震を観測する地点から震源までの距離を「震源距離」、震央までの距離を「震央距離」と呼びます。地震の揺れには、P波(縦波)とS波(横波)の二種類があり、それぞれの伝わる速さが違います。このため、観測地点に二つの波が到着する時間には差が生じます。この時間差を利用することで、観測地点から震源までの距離を計算することができます。
さらに、三箇所以上の観測地点があれば、それぞれの地点から震源までの距離を基に、震央の位置を特定することができます。そして、震源までの距離と震央までの距離が分かれば、震源の深さを計算することができます。
地震の発生源

私たちの住む地球の表面は、プレートと呼ばれる巨大な岩盤のようなもので覆われています。まるでジグソーパズルのように組み合わさったこのプレートですが、実は常にゆっくりと動き続けています。
プレートはそれぞれが別々の方向へ移動しているため、プレート同士がぶつかり合う場所も存在します。このような場所では、想像を絶する力が長年に渡って蓄積されていきます。そして、ついに限界を超えた時に、岩盤が破壊され、私たちが地震と呼ぶ現象が起こるのです。
この岩盤の破壊が始まった最初の地点を震源と呼びます。震源は多くの場合、地球内部の深い場所に位置しています。地震のエネルギーが解放されるまさにその起点こそが震源であり、そこから地震波が四方八方へと伝播していくのです。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| プレート | 地球の表面を覆う巨大な岩盤。常にゆっくりと動き続けている。 |
| 地震 | プレート同士の衝突により、蓄積された力が解放され、岩盤が破壊される現象。 |
| 震源 | 地震のエネルギーが解放される最初の地点。多くの場合、地球内部の深い場所に位置する。 |
震央の位置

地震が発生すると、その揺れは発生源である地下深くの震源から四方八方へと伝わっていきます。そして、この震源の真上に位置する地表の地点を「震央」と呼びます。
地震の発生場所を示す際に、ニュースなどで目にするのは、まさにこの震央です。地図上に震央を記すことで、どこで地震が発生したのかを分かりやすく伝えることができます。
震央は、地震の規模や被害状況などを伝える上でも欠かせない重要な情報です。地震の規模を示すマグニチュードは、震源から放出されるエネルギーの大きさを表すものですが、私たちが実際に感じる揺れの強さは、震央からの距離が大きく影響します。震央に近いほど揺れは強く、被害も大きくなる傾向があります。
そのため、地震が発生した際には、気象庁などから発表される震源の情報に加え、震央がどこなのかにも注意することが大切です。震央の位置を把握することで、自分のいる場所が震源からどの程度離れているのか、どの程度の揺れが予想されるのかを推測することができます。これは、地震への備えや適切な行動をとる上で非常に重要な情報となります。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 震源 | 地震が発生した地下深くの地点 |
| 震央 | 震源の真上に位置する地表の地点 |
震源からの距離

地震が発生すると、大地を揺らしながらあらゆる方向に波のように広がっていくのが地震波です。この地震波は、地下深くにある岩石が破壊される際に放出されるエネルギーによって発生します。
地震の規模や発生場所を知るためには、震源からの距離を正確に把握することが重要となります。観測点と地震の発生源である震源との間の距離を「震源距離」、観測点と震源の真上の地表地点である震央との間の距離を「震央距離」といいます。
では、これらの距離はどのように測定されるのでしょうか。地震波には、伝わる速度が異なるいくつかの種類があります。観測点には、これらの地震波が時間差を持って到達します。この時間差と、それぞれの地震波の速度を用いることで、三角測量の原理と同様の方法で震源距離を計算することができます。
震源距離が分かれば、地震の規模を示すマグニチュードを算出することができます。マグニチュードは、地震そのもののエネルギーの大きさを表す指標であり、震源距離と地震計で観測された地震波の振幅から計算されます。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 地震波 | 地下深くの岩石破壊により発生するエネルギー。あらゆる方向に波のように広がり、地面を揺らす。 |
| 震源距離 | 観測点と地震の発生源(震源)との間の距離。地震波の到達時間差と速度から計算。 |
| 震央距離 | 観測点と震源の真上の地表地点(震央)との間の距離。 |
| マグニチュード | 地震のエネルギーの大きさを表す指標。震源距離と地震波の振幅から計算。 |
地震波の種類
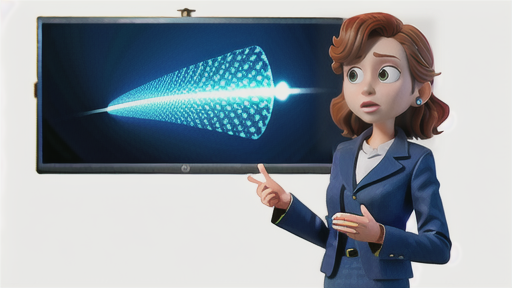
地震が発生すると、地球内部を伝わる波と、地面を伝わる波の二種類の地震波が発生します。これらの波はそれぞれ特徴が異なり、伝わる速度や揺れ方にも違いが見られます。
まず、地球内部を伝わる地震波には、大きく分けて『P波』と『S波』の二つの種類があります。P波は、地震波の中で最も速く伝わる波として知られています。この波は、ばねを圧縮した時のような動きで、進行方向に振動しながら伝わっていきます。そして、固体だけでなく、液体の中も伝わっていくことができるという性質を持っています。
一方、S波はP波に比べて速度が遅く、地面を上下左右に大きく揺らしながら伝わっていきます。この波は、ひもを上下に振った時のような動きで、進行方向に対して垂直に振動しながら伝わります。P波とは異なり、S波は固体の中しか伝わることはできません。
これらの地震波の速度の違いを利用することで、地震の発生場所を特定することができます。また、それぞれの波の揺れ方の特徴を理解しておくことは、地震発生時の被害軽減にも繋がります。
| 特徴 | P波 | S波 |
|---|---|---|
| 伝わる速度 | 速い | 遅い |
| 揺れ方 | 進行方向に振動(縦揺れ) | 進行方向と垂直に振動(横揺れ) |
| 伝わる物質 | 固体、液体 | 固体のみ |
震源の深さを求める

地震が発生すると、様々な種類の地震波が地面を伝わります。これらの波の中で、P波(縦波)は最も速く伝わる波であり、S波(横波)はP波よりも遅い速度で伝わります。
このP波とS波の速度差を利用することで、地震の震源の深さを特定することができます。地震が発生すると、まずP波が観測点に到達し、その後、時間差をおいてS波が到達します。このP波とS波の到着時間差は、震源から観測点までの距離が遠いほど大きくなるという性質があります。
複数の観測点において、この到着時間差を記録することで、それぞれの観測点から震源までの距離を計算することができます。そして、3カ所以上の観測点で得られた震源距離を用いることで、震央(震源の真上の地表の地点)と震源の深さを正確に計算することができます。
これは、空間における位置を特定する際に、3点からの距離が分かれば一意に定まるという原理と同じです。このように、地震波の速度差を利用することで、私たちが直接見ることのできない地下深くの地震の震源を特定することができるのです。
| 地震波の種類 | 特性 | 利用方法 |
|---|---|---|
| P波(縦波) | 最も速い地震波 | P波とS波の到着時間差から震源までの距離を計算 |
| S波(横波) | P波より遅い地震波 |
| 観測点数 | 結果 |
|---|---|
| 複数 | 震源までの距離を計算可能 |
| 3箇所以上 | 震央と震源の深さを正確に計算可能 |
