原子力発電の安全性:状態監視保全とは

電力を見直したい
先生、「状態監視保全」ってどういう意味ですか?

電力の研究家
良い質問だね。「状態監視保全」は、簡単に言うと、機械の状態を常に見ていて、壊れそうになったら修理する方法だよ。

電力を見直したい
いつも見ているんですか? それは大変そうですね。

電力の研究家
そうだね。でも、壊れてから直すより、壊れる前に直した方が、大きな事故を防げるし、無駄に部品を交換する必要も無くなるんだよ。原子力発電所みたいに、安全が特に大切な施設では、特に有効な方法なんだ。
状態監視保全とは。
原子力発電所で使われる言葉に「状態監視保全」というものがあります。これは、壊れるのを防ぐための方法の一つで、設備を常にチェックし、故障の兆しが見えたら必要な時に修理や交換をすることで安全を保つ方法です。一方で、定期的に、故障しているかどうかに関わらず、機械の点検や交換を行う方法を「時間管理保全」と言います。日本の原子力発電所では、今までこの「時間管理保全」が主に使われてきました。しかし、アメリカでは「状態監視保全」が広く使われており、日本でも無駄をなくすために導入が進められています。
原子力発電における保全の重要性
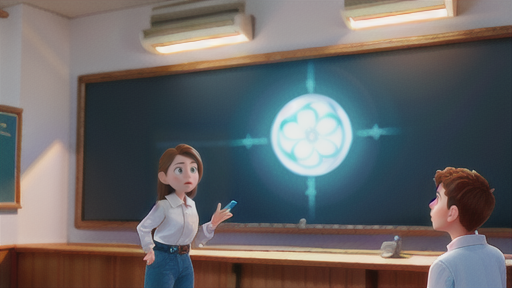
原子力発電所は、私たちの暮らしに欠かせない電気を送り出す、重要な役割を担っています。この施設を安全に運用していくためには、発電所の設備が常にきちんと動く状態を保つことが非常に重要であり、そのためには適切な保全活動が欠かせません。ほんの小さな異常も見逃せば、大きな事故につながりかねないため、様々な保全活動が実施されています。
原子力発電所における保全活動は、大きく分けて「定期検査」と「予防保全」の二つに分類できます。定期検査は、法律で定められた期間ごとに行われる、発電所全体を対象とした大規模な点検です。この検査では、原子炉やタービンなど、主要な設備を分解・検査し、劣化や損傷がないかを入念に確認します。さらに、最新技術を用いた検査や、過去の運転データに基づく評価なども行い、設備の健全性を多角的に評価します。
一方、予防保全は、定期検査の間にも、設備の状態を監視し、異常の兆候を早期に発見して、故障や事故を未然に防ぐための活動です。例えば、センサーを用いて設備の振動や温度、圧力などを常時監視したり、定期的に設備の目視点検や油の分析などを行い、異常の有無を確認します。
このように、原子力発電所では、人々の安全を最優先に、様々な保全活動を通じて、設備の信頼性と安全性の維持に努めています。
| 分類 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 定期検査 | 法律で定められた期間ごとに行われる発電所全体の点検 原子炉やタービンなどを分解・検査 最新技術や過去の運転データに基づく評価 |
設備の劣化や損傷の確認 設備の健全性の多角的評価 |
| 予防保全 | 定期検査期間中の設備状態の監視 センサーによる振動、温度、圧力等の常時監視 定期的な目視点検や油の分析 |
異常の兆候の早期発見 故障や事故の未然防止 |
従来の保全手法:時間管理保全

– 従来の保全手法時間管理保全日本の原子力発電所では、長い間、「時間管理保全」と呼ばれる方法が機器の保全の主流でした。これは、機器の使用時間や経過時間をもとに、あらかじめ決めた時期に点検や部品交換を行う方法です。 例えば、ある部品の使用時間が1万時間を超えたら交換する、といったように、時間に基づいて保全を実施します。これは、自動車の定期点検と似たような考え方です。定期的に点検と部品交換を実施することで、 車の故障を未然に防ぎ、安全を確保するのと同じように、原子力発電所の機器も、定期的な点検と部品交換によって寿命を事前に予測し、故障のリスクを減らすことを目的としています。時間管理保全は、計画的に保全を実施できるため、管理がしやすいというメリットがあります。しかし、実際に機器の状態を詳細に把握せずに、一律に時間だけで判断するため、まだ使える部品を交換してしまう可能性や、逆に、時間経過だけでは発見できない劣化を見逃してしまう可能性も孕んでいます。
| 保全手法 | 概要 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 時間管理保全 | 機器の使用時間や経過時間をもとに、あらかじめ決めた時期に点検や部品交換を行う方法。 | 計画的に保全を実施できるため、管理がしやすい。 | – 実際に機器の状態を詳細に把握せずに、一律に時間だけで判断するため、まだ使える部品を交換してしまう可能性がある。 – 時間経過だけでは発見できない劣化を見逃してしまう可能性がある。 |
新しい保全手法:状態監視保全とは
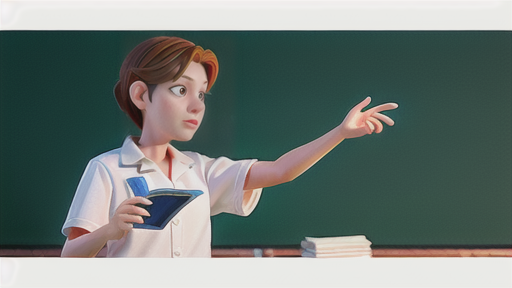
– 新しい保全手法状態監視保全とは近年、製造業やインフラ分野など、様々な産業において、設備の老朽化や高度化に伴い、より効率的かつ効果的な保全方法が求められています。従来の、一定期間や使用時間ごとに一律に部品交換や点検を行う時間基準保全とは異なり、状態監視保全は、設備の状態を常時監視し、異常の兆候が現れた場合にのみ必要な保全を行うという、予知保全の一種です。具体的には、センサーやコンピューターシステムを用いて、設備の振動、温度、圧力、音、電流値などの様々なデータを収集します。そして、集めたデータを分析し、設備の劣化状況や異常の兆候を早期に検知します。このデータ分析には、統計的な手法やAI技術が活用されるケースも増えています。状態監視保全を導入するメリットは、従来の時間基準保全に比べて、保全にかかる費用や時間を大幅に削減できる点にあります。無駄な部品交換や点検を減らすことで、資源の節約にもつながります。また、設備の異常を早期に発見し、適切なタイミングで保全を行うことで、重大な事故や故障を未然に防ぐ効果も期待できます。状態監視保全は、あらゆる設備に適用できるわけではありませんが、近年ではセンサー技術やデータ分析技術の進歩により、導入が容易になりつつあります。今後、設備の安全性や信頼性の向上、そして保全の効率化を図る上で、状態監視保全はますます重要な役割を担っていくと考えられます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手法 | 状態監視保全(予知保全の一種) |
| 概要 | 設備の状態を常時監視し、異常の兆候が現れた場合にのみ必要な保全を行う |
| 具体的な方法 | センサー等で振動、温度、圧力、音、電流値等のデータを収集し、分析して設備の劣化状況や異常の兆候を早期に検知する。 |
| メリット | – 保全にかかる費用や時間を大幅に削減できる – 無駄な部品交換や点検を減らすことで、資源の節約 – 設備の異常を早期に発見し、適切なタイミングで保全を行うことで、重大な事故や故障を未然に防ぐ効果 |
| 導入状況 | センサー技術やデータ分析技術の進歩により、導入が容易になりつつある |
| 今後の展望 | 設備の安全性や信頼性の向上、そして保全の効率化を図る上で、ますます重要な役割を担っていくと考えられる。 |
状態監視保全のメリット

– 状態監視保全のメリット状態監視保全は、従来の時間に基づいて行う保全とは異なり、設備の状態を常時監視し、そのデータに基づいて必要なときに必要な保全を行う手法です。この手法は、原子力発電所において多くのメリットをもたらします。まず、状態監視保全は、過剰な保全を抑制し、必要なときに必要なだけの保全を実施することを可能にします。従来の時間管理保全では、たとえ部品が正常に動作していても、あらかじめ決められた期間が経過すると交換が行われていました。これは、資源の無駄遣いであるだけでなく、交換作業に伴うリスクも孕んでいました。状態監視保全では、センサーなどを通じて設備の状態を常時監視し、データ分析に基づいて実際に劣化が進んでいる部品のみを交換するため、資源の効率的な活用とリスクの低減を実現できます。さらに、状態監視保全は、予兆保全を可能にすることで、重大な事故を未然に防ぐ効果も期待できます。設備の異常は、多くの場合、小さな兆候が現れてから最終的に故障に至ります。状態監視保全では、これらの兆候を早期に検知し、適切な対策を講じることで、重大な事故につながるような故障を未然に防ぐことが可能になります。これは、原子力発電所の安全性向上に大きく貢献すると言えるでしょう。加えて、状態監視保全は、保全作業の頻度を減らすことで、保全コストの削減と発電所の稼働率向上にも寄与します。設備の状態を把握することで、不要な点検や部品交換を減らし、保全作業を効率化できます。また、予兆保全の実施により、突発的な設備の停止リスクを低減できるため、発電所の安定稼働にもつながります。このように、状態監視保全は、安全性向上、コスト削減、稼働率向上など、原子力発電所にとって多くの利点をもたらす重要な保全手法と言えるでしょう。
| 状態監視保全のメリット | 内容 |
|---|---|
| 過剰な保全の抑制 | – センサー等で状態を監視し、劣化が進んでいる部品のみを交換 – 資源の効率的な活用とリスクの低減 |
| 予兆保全による事故防止 | – 異常の兆候を早期に検知し、適切な対策を実施 – 重大な事故につながる故障を未然に防止 |
| 保全コストの削減と稼働率向上 | – 不要な点検や部品交換を削減 – 突発的な設備の停止リスクを低減し、安定稼働に寄与 |
状態監視保全の導入状況と今後の展望

– 状態監視保全の導入状況と今後の展望原子力発電所における安全性の向上と効率的な運用は、社会全体のエネルギー安定供給という観点からも非常に重要です。そのための有効な手段の一つとして、近年注目されているのが状態監視保全です。状態監視保全とは、機器や設備の状態を常に監視し、そのデータに基づいて適切な時期にメンテナンスを行うことで、突発的な故障を未然に防ぎ、安全性を高めつつ、設備の長寿命化も図る保全手法です。従来の時間基準保全のように、決まった期間や使用時間ごとに部品交換などを行うのではなく、機器の状態に合わせて必要な時に必要な対応を行うことで、無駄なコストを抑えられます。状態監視保全はすでに米国など原子力発電先進国では広く導入されており、その有効性が実証されています。日本でも、近年導入が進みつつあり、今後ますます普及していくことが予想されます。状態監視保全の導入を加速させているのが、センサー技術やデータ解析技術の進歩です。近年、高性能かつ低価格なセンサーが開発され、大量のデータを収集することが可能になりました。また、人工知能(AI)などのデータ解析技術も進化しており、膨大なデータの中から機器の状態を正確に把握することができるようになってきました。これらの技術革新により、従来は検知が難しかった軽微な異常も早期に発見できるようになり、より精度の高い状態監視保全が可能になっています。このように、状態監視保全は原子力発電所の安全性向上、効率性向上に大きく貢献する技術として、今後もその重要性を増していくと考えられます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 概要 | 機器や設備の状態を常に監視し、データに基づいて適切な時期にメンテナンスを行う保全手法 |
| メリット |
|
| 現状 |
|
| 導入を加速させる要因 |
|
| 効果 |
|
| 今後の展望 | 原子力発電所の安全性向上、効率性向上に大きく貢献する技術として、重要性を増す |
