加速器の歴史を開いたコッククロフト・ワルトン型加速器

電力を見直したい
先生、「コッククロフト・ワルトン型加速器」って、どんなものですか? 水素イオンを加速するって書いてあるんですけど、何だか難しそうです。

電力の研究家
そうだね。「コッククロフト・ワルトン型加速器」は、簡単に言うと静電気をためて、その電気の力で水素イオンを加速させる装置なんだ。 コンセントの電気をイメージしてみて。でも、もっともっと高電圧にする必要があるんだ。

電力を見直したい
なるほど。それで、高電圧にするためにコンデンサーや整流器を使うんですか?

電力の研究家
その通り! コンデンサーに電気をためて、整流器で電流の流れを整えることで、高い電圧を作り出すんだ。 でも、最近はもっと性能のいい加速器が使われていることが多いかな。
コッククロフト・ワルトン型加速器とは。
「コッククロフト・ワルトン型加速器」という言葉は、原子力発電の分野で使われる言葉です。これは、1932年にコッククロフトさんとワルトンさんが発明した、一定の電圧をかけることで粒子を加速させる装置です。この装置は、電気を一方向にだけ流す仕組みを使って高い電圧を作り、その電圧を電極に与えることで水素イオン(陽子)を加速させます。電気をためる部品と、電気を一方向にだけ流す部品を何段も重ねることで、空気中でも約100万ボルトまでの電圧を作り出すことができます。さらに、この電圧発生装置を高圧の絶縁ガスを詰めた鉄製のタンクに入れることで、数百万ボルトまでの電圧を得ることも可能です。最近では、コッククロフト・ワルトン型加速装置の代わりに、波を使ってイオンを加速させる線形加速器やシンクロサイクロトロンが主流となっています。
原子核研究の幕開け

20世紀初頭、物質の根源を探る科学の世界では、原子の構造が徐々に明らかになりつつありました。原子の中心には、プラスの電気を帯びた原子核が存在し、その周りをマイナスの電気を帯びた電子が飛び回っているという描像です。しかし、原子核は非常に小さく、その内部構造やそこに働く力は謎に包まれていました。
この謎を解き明かすためには、原子核を構成する粒子を互いに衝突させ、その反応を観測する必要がありました。しかし、原子核はプラスの電気を帯びているため、互いに反発し合って簡単には近づけません。そこで、原子核同士を衝突させるために開発されたのが粒子加速器です。
粒子加速器は、電場や磁場を使って荷電粒子を加速し、高いエネルギー状態を作り出す装置です。1932年、イギリスの物理学者コッククロフトとワルトンは、世界で初めて原子核反応を人工的に起こすことに成功した加速器を開発しました。これは、高電圧発生装置と直線状の加速管を組み合わせた画期的な装置で、彼らはこの功績により1951年にノーベル物理学賞を受賞しました。コッククロフト・ワルトン型加速器の登場は、原子核物理学という新たな学問分野の幕開けを告げるものでした。
| 原子構造 | 原子核の謎 | 粒子加速器の開発 | コッククロフトとワルトン |
|---|---|---|---|
| 原子の中心にはプラス電荷の原子核があり、その周りをマイナス電荷の電子が回っている | 原子核の内部構造や力は不明だった | 原子核同士を衝突させるために開発された。電場や磁場を使って荷電粒子を加速し、高エネルギー状態を作り出す装置 | 1932年、世界で初めて人工的に原子核反応を起こすことに成功した加速器を開発し、1951年にノーベル物理学賞を受賞した |
コッククロフトとワルトンの発明

1932年、イギリスのケンブリッジ大学キャベンディッシュ研究所において、ジョン・コッククロフトとアーネスト・ワルトンという二人の俊英によって、人類史上初めて原子核反応が人工的に制御され、莫大なエネルギーが取り出せることが実証されました。この偉業は、原子核物理学の夜明けを告げ、その後の原子力開発の礎を築いたと言えるでしょう。彼らは、当時としては画期的な加速器を開発し、陽子を人工的に加速することで、リチウム原子核に衝突させました。その結果、リチウム原子核は二つに分割され、ヘリウム原子核に変換したのです。この時、アインシュタインの有名な式「E=mc²」に従い、莫大なエネルギーが放出されました。この実験は、それまで理論上の存在に過ぎなかった原子力の可能性を現実のものとし、世界に衝撃を与えました。この功績により、二人は1951年にノーベル物理学賞を受賞しました。彼らの開発した加速器は、「コッククロフト・ワルトン型加速器」と名付けられ、現在でも粒子加速器の基本原理として、医療分野や工業分野など幅広く応用されています。
| 年 | 1932年 |
|---|---|
| 場所 | イギリスのケンブリッジ大学キャベンディッシュ研究所 |
| 人物 | ジョン・コッククロフトとアーネスト・ワルトン |
| 内容 | 人類史上初めて原子核反応を人工的に制御し莫大なエネルギーを取り出すことに成功 |
| 方法 | 当時としては画期的な加速器を開発し陽子を人工的に加速することでリチウム原子核に衝突させました。その結果、リチウム原子核は二つに分割されヘリウム原子核に変換した。 |
| 結果 | アインシュタインの有名な式「E=mc²」に従い莫大なエネルギーが放出された。この実験はそれまで理論上の存在に過ぎなかった原子力の可能性を現実のものとし世界に衝撃を与えた。 |
| 受賞 | 1951年にノーベル物理学賞を受賞 |
| 影響 | 彼らの開発した加速器は「コッククロフト・ワルトン型加速器」と名付けられ現在でも粒子加速器の基本原理として医療分野や工業分野など幅広く応用されている。 |
加速の仕組み
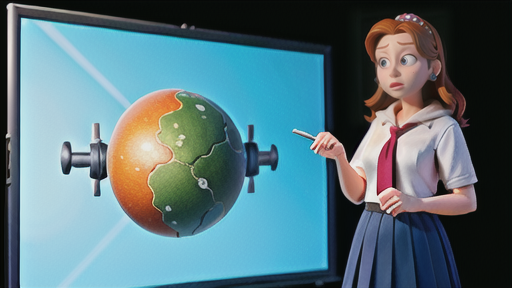
加速の仕組みを理解するには、コッククロフト・ワルトン型加速器の構造を知る必要があります。この加速器は、直流電圧を用いて粒子を加速する装置です。しかし、乾電池のように最初から高い直流電圧を得ているわけではありません。家庭用のコンセントから供給される交流電流を、整流器と呼ばれる部品を使って直流電流に変換するところから始まります。
この直流電流は、次にコンデンサーに蓄えられます。コンデンサーとは、電気を溜めておくことができる部品です。コッククロフト・ワルトン型加速器は、コンデンサーと整流器を何段も重ねる構造を持つため、電圧を段階的に上げていくことができます。イメージとしては、階段を一段ずつ上るように電圧が高くなっていくと考えると分かりやすいでしょう。
こうして作り出された高電圧は、加速器の中にある電極に印加されます。電極間に高い電圧がかかると、電場が生じます。この電場によって、プラスの電荷を持った水素イオン(陽子)は、まるで坂道を転がるように加速されていきます。加速された陽子は、原子核の研究など様々な分野で利用されます。コッククロフト・ワルトン型加速器は、大気中で約100万ボルト、絶縁ガスを封入したタンクを用いることで数百万ボルトもの高電圧を得ることができました。
| 構成要素 | 役割 | 動作 |
|---|---|---|
| 整流器 | 交流電流を直流電流に変換する | 家庭用コンセントからの交流電流を直流電流に変換 |
| コンデンサー | 電気を溜める | 整流された直流電流を蓄える |
| コンデンサーと整流器の複数段構成 | 段階的に電圧を上げる | 階段を上るように一段ずつ電圧を上昇させる |
| 電極 | 高電圧を印加し、電場を生成する | 電場によって陽子を加速する |
その後の発展と応用

コッククロフト・ワルトン型加速器は、初期の原子核研究において、革新的な役割を果たし、その後の物理学の発展に大きく貢献しました。この加速器は、原子核や素粒子の性質を調べるための重要な装置として、数々の重要な発見を支えてきました。
しかし、科学技術の進歩は目覚ましく、原子核・素粒子物理学の分野では、より高エネルギーの粒子を加速できる、より強力な加速器が求められるようになりました。その結果、線形加速器やサイクロトロンといった、コッククロフト・ワルトン型加速器よりも高いエネルギーを実現できる加速器が登場しました。これらの新型加速器は、より深く物質の根源に迫る研究を可能にし、現代物理学の最先端を拓いてきました。
一方、コッククロフト・ワルトン型加速器は、最先端の研究には使われなくなりましたが、その役割を終えたわけではありません。この加速器は、堅牢な構造を持ち、比較的シンプルな仕組みで動作するため、現在でも様々な分野で活用されています。特に、医療分野における放射線治療や、材料科学分野におけるイオン注入といった分野では、その特性を生かして重要な役割を担っています。小型で扱いやすいという利点から、現在でも様々な研究機関や医療機関で活躍を続けています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コッククロフト・ワルトン型加速器の貢献 | 初期の原子核研究を革新し、その後の物理学の発展に貢献。原子核や素粒子の性質を調べるための重要な装置として、数々の重要な発見を支えた。 |
| コッククロフト・ワルトン型加速器の限界 | 科学技術の進歩により、より高エネルギーの粒子を加速できる強力な加速器(線形加速器、サイクロトロンなど)が登場した。 |
| コッククロフト・ワルトン型加速器の現在 | 最先端の研究には使われなくなったが、堅牢な構造とシンプルな仕組みを生かし、医療分野(放射線治療)や材料科学分野(イオン注入)で活躍。小型で扱いやすいという利点から、現在でも様々な研究機関や医療機関で使用されている。 |
技術革新の礎

– 技術革新の礎
コッククロフト・ワルトン型加速器は、1932年にジョン・コッククロフトとアーネスト・ウォルトンによって開発された画期的な装置でした。これは、高電圧発生装置を用いて陽子を加速し、リチウム原子核に衝突させることで、世界で初めて人工的に原子核反応を誘起することに成功しました。
この発明は、それまでの原子核に関する理解を根本から覆し、原子核や素粒子の世界を探求するための新たな扉を開きました。 コッククロフト・ワルトン型加速器の登場は、現代物理学の幕開けを告げる画期的な出来事だったと言えるでしょう。
さらに、彼らの開発した加速技術は、現代社会においても様々な分野で応用されています。例えば、医療分野では、がん治療などに用いられる放射線治療装置に利用されています。また、工業分野では、材料の分析や非破壊検査などに活用されています。
このように、コッククロフト・ワルトン型加速器は、現代物理学の発展に貢献しただけでなく、私たちの生活にも大きな影響を与えているのです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発明者 | ジョン・コッククロフト、アーネスト・ウォルトン |
| 発明年 | 1932年 |
| 概要 | 高電圧発生装置を用いて陽子を加速し、リチウム原子核に衝突させることで、世界で初めて人工的に原子核反応を誘起することに成功 |
| 意義 | – 原子核や素粒子の世界を探求するための新たな扉を開いた – 現代物理学の幕開けを告げる画期的な出来事 |
| 応用例 | – 医療分野:がん治療などに用いられる放射線治療装置 – 工業分野:材料の分析や非破壊検査 |
