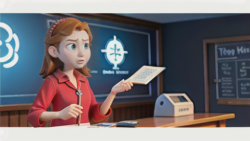原子力発電の基礎知識
原子力発電の基礎知識 低減速軽水炉:資源活用とエネルギーの未来
- 低減速軽水炉とは原子力発電所で使われている炉には、大きく分けて軽水炉と重水炉の二つの種類があります。現在、世界中の原子力発電所で最も多く採用されているのは軽水炉で、その中でも減速材の水と冷却材の水を兼用する沸騰水型軽水炉と加圧水型軽水炉の二つが主流となっています。
低減速軽水炉は、このうち軽水炉の一種です。従来型の軽水炉とは異なる新しい設計思想に基づいて開発が進められています。
従来型の軽水炉では、原子核分裂によって発生する莫大なエネルギーを持った中性子を水によって減速させることで、ウラン燃料の核分裂反応を効率的に起こしています。この水のように中性子を減速させる物質のことを「減速材」と呼びます。
一方、低減速軽水炉では、その名の通り、減速材として使用される水の量を従来の軽水炉よりも減らし、中性子の速度をあまり落とさないように設計されています。
中性子の速度が速い状態の方が、ウラン燃料からプルトニウムが生成される割合が高くなるという利点があります。プルトニウムはウランと同様に核燃料として利用できるため、低減速軽水炉はウラン資源をより有効活用できるという点で注目されています。さらに、プルトニウムを燃料として利用することで、原子力発電に伴って発生する高レベル放射性廃棄物の量を減らせる可能性も秘めています。
このように、低減速軽水炉は、従来の軽水炉の技術を基に、資源の有効利用と環境負荷の低減を目指した、次世代の原子炉として期待されています。