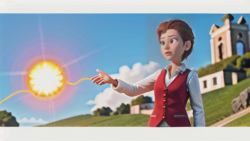放射線について
放射線について 意外と知らない?放射線の強さを表す「吸収線量率」
私たちは普段、光や音など、五感で感じ取れるものと、そうでないものが身の回りに混在していることを意識せずに生活しています。目には見えないけれど、確かにそこに存在し、影響を及ぼすものの一つに放射線があります。放射線は、光や音のように直接感じることができないため、その影響を測るためには特別な指標が必要となります。
その指標となるのが「吸収線量」です。
吸収線量は、ある物質が放射線を浴びた際に、その物質の単位質量あたりにどれだけのエネルギーが吸収されたかを表すものです。
たとえば、太陽の光を浴びると体が温まりますが、これは体が太陽光のエネルギーを吸収しているためです。
吸収線量もこれと同じように、放射線という目に見えないエネルギーが、物質にどれだけ吸収されたかを測るものさしと言えます。
この吸収線量は、エネルギーの量を表す単位であるジュール毎キログラム(J/kg)で表されます。
さらに、放射線に関してよりわかりやすくするために、グレイ(Gy)という特別な単位も用いられます。
1グレイは1ジュール毎キログラムと等しく、放射線の影響を考える上で重要な指標となります。