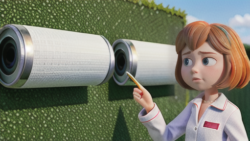 放射線について
放射線について 原子力と細胞: 半透膜への影響
私たちの体は、顕微鏡でなければ見えないほど小さな細胞が集まってできています。そして、その一つ一つの細胞は、まるで秩序だって働く工場のようです。この小さな工場を囲む壁の役割を果たしているのが「半透膜」です。細胞と外界の間を隔てるこの薄い膜は、細胞が生きていく上で非常に重要な役割を担っています。
半透膜は、まるで工場の出入り口のように、物質の出入りを厳しく管理しています。細胞が活動するためのエネルギー源となる栄養素は積極的に取り込み、逆に、細胞の活動で生じた不要な老廃物は外に排出します。このように、必要なものと不要なものを選り分けることで、半透膜は細胞内の環境を一定に保ち、生命活動が滞りなく行われるようにしています。
もしも、この半透膜がなければどうなるでしょうか。細胞は、必要な栄養素を取り込むことができなくなり、また、老廃物が細胞内に溜まっていくでしょう。やがて、細胞は自身の毒性に蝕まれ、その機能を失ってしまうと考えられます。つまり、半透膜は、細胞を正常に機能させ、ひいては私たちの生命を維持するために、無くてはならない存在なのです。























