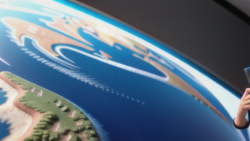その他
その他 地球全体の気候を監視する仕組み – 全球気候観測システム
地球温暖化に代表される気候変動は、私たちの社会や生態系に様々な影響を与える深刻な問題です。この問題に取り組むためには、地球全体の気候変動を正確に把握することが何よりも重要になります。そこで、世界気象機関(WMO)など国際機関によって1992年に設立されたのが、全球気候観測システム、英語名Global Climate Observing System、略称GCOSです。
GCOSは、世界中の様々な機関が協力して気候に関するデータを集め、そのデータを分析して気候変動の実態を解明し、将来予測を行うための国際的な枠組みを提供しています。
具体的には、GCOSは気候観測の対象となる要素(気温、降水量、海水面高度、二酸化炭素濃度など)や、観測データの精度、観測頻度などを定め、世界共通の基準で気候観測が行われるように努めています。
集められたデータは、世界中の研究機関に提供され、気候変動に関する研究や将来予測に活用されます。さらに、GCOSは、観測データに基づいて気候変動に関する報告書を作成し、国際社会や政策決定者に科学的な情報を提供する役割も担っています。
GCOSの活動は、気候変動対策を進める上で非常に重要な役割を果たしており、国際社会全体で協力してGCOSを支援していく必要があります。