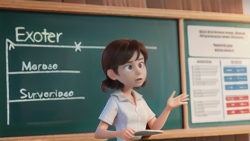その他
その他 原子力平和利用の要:ロンドンガイドライン
世界中で平和的に原子力を使うためには、核兵器の拡散を防ぐことが非常に重要です。これを目指して、国際的な協力体制である「ロンドンガイドライン」が作られました。これは、1975年にインドが核実験を行ったことがきっかけで始まりました。この出来事を深刻に受け止めた日本、アメリカ、旧ソ連などを含む7つの国が、イギリスのロンドンに集まって話し合いを始めました。
当初は7ヶ国だった参加国は、その後15ヶ国に増え、原子力に関する技術や材料を、核兵器を持っていない国に輸出する際のルールが作られました。これが「ロンドンガイドライン」と呼ばれるもので、1978年に国際原子力機関(IAEA)によって正式に発表されました。
このガイドラインでは、原子力関連の輸出を行う際には、輸出先の国がIAEAによる査察を受け入れることなどを条件としています。これにより、平和的な目的以外に原子力が使われることを防ぐことを目指しています。現在では、27ヶ国がこのガイドラインに参加しており、核兵器の拡散を阻止するための国際的な取り組みの柱となっています。