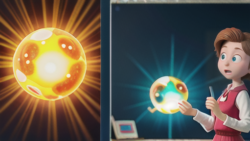放射線について
放射線について 放射線感受性と細胞の神秘
- ベルゴニー・トリボンドーの法則とは1906年、フランスの科学者であるジャン・ベルゴニーとルイ・トリボンドーは、放射線が生物に与える影響に関する重要な法則を発見しました。これは、彼らの名を取り「ベルゴニー・トリボンドーの法則」と呼ばれています。この法則は、簡単に言うと、「細胞分裂が活発な細胞ほど、放射線の影響を受けやすい」というものです。二人の科学者は、ラットの睾丸を用いた実験を行いました。睾丸の中には、精子を作るために盛んに細胞分裂を繰り返している細胞と、すでに精子になり、分化を終えている細胞の両方が存在します。彼らは、ラットの睾丸に放射線を照射し、それぞれの細胞への影響を調べました。すると、活発に分裂を繰り返している細胞は、分化を終えた細胞に比べて、放射線によるダメージをはるかに大きく受けることが明らかになったのです。この発見は、細胞分裂の活発さと放射線の感受性に深い関係があることを示しており、放射線生物学において非常に重要な意味を持ちます。特に、放射線治療においてはこの法則が応用されています。がん細胞は、正常な細胞に比べて細胞分裂が活発であるため、放射線治療によって、がん細胞をより選択的に破壊することが可能になります。ベルゴニー・トリボンドーの法則は、100年以上も前に発見された法則ですが、今日でも放射線生物学の基礎として重要な役割を担っています。