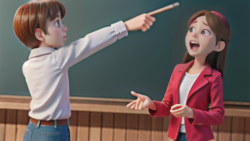その他
その他 地球の気候を司る: 熱塩循環
地球の表面は広大な海で覆われており、そこでは熱と塩が織りなす壮大なドラマが繰り広げられています。
舞台となるのは、地球全体を巡る海水です。海水は場所によって温度や塩分濃度が異なり、そのわずかな違いが海の循環を生み出す原動力となっています。
太陽の熱で温められた海水は軽くなり、海の表面から極域へと向かいます。一方、極域で冷やされた海水は重くなり、海の底へと沈み込みます。
塩分濃度もまた、海水の密度に影響を与えます。海水の蒸発が盛んな地域では塩分濃度が高くなり、その分海水は重くなります。逆に、雨や川の水が流れ込む地域では塩分濃度は低くなり、海水は軽くなります。
このように、温度と塩分の微妙なバランスによって、海水は上下に移動し、地球規模の循環を形成します。これが、熱塩循環と呼ばれる現象です。
熱塩循環は、地球の気候や生態系にも大きな影響を与えています。深海から栄養豊富な海水を海面へと運び上げたり、赤道付近の熱を極域へと運ぶことで、地球全体の気温を調整する役割も担っています。まるで、地球の心臓のように、休むことなく働き続けているのです。