原子力発電と海洋:処分方法の過去と現状

電力を見直したい
『海洋処分』って、具体的にどんなことをするんですか?

電力の研究家
簡単に言うと、放射性廃棄物を海に捨てることだね。でも、ただ闇雲に捨てるわけじゃなくて、いくつか方法があるんだ。大きく分けて『海洋投棄』と『沿岸放出』の二つがあるよ。

電力を見直したい
『海洋投棄』と『沿岸放出』はどう違うんですか?

電力の研究家
『海洋投棄』は、放射性廃棄物をドラム缶に入れて海の底に沈める方法だよ。一方、『沿岸放出』は、薄めた放射性廃棄物を、国の基準よりもさらに薄めてから海に流す方法なんだ。どちらも、もう使われていない方法だけどね。
海洋処分とは。
「海洋処分」とは、原子力発電で出た放射性廃棄物を、二度と回収しないつもりで、人の管理する場所から海に移す最終的な処分方法のことです。海洋処分には、海の遠くへ捨てる「海洋投棄」と、海岸近くで流す「沿岸放出」の二つがあります。
「海洋投棄」は、濃度の高い液体状の放射性廃棄物を、セメントやアスファルト、プラスチックなどで固めて、200リットルのドラム缶に入れます。そして、このドラム缶を、簡単には壊れないようにして、国の近くの海ではない、広い海に捨てます。ただし、この方法で捨ててもよいのは、固めたものの中に含まれる放射性物質が、海水に溶け出して人間の生活する場所に届くまでの時間が、放射性物質が半分に減るまでの時間よりもずっと長いものに限られます。つまり、放射性物質をしっかり閉じ込めておけるものだけが対象です。そのため、強い放射能を持つ液体状の廃棄物は、この方法で捨てることはできません。
「沿岸放出」は、放射性物質を含む液体が発生した施設内で、放射能をできるだけ取り除き、それぞれの国の政府が決めた、人体や環境への影響が少ないとされる濃度よりもずっと低くなったことを確認した上で、施設のある国の近くの海や川に流す方法です。そして、海の流れなどによって、さらに薄められます。つまり、管理しながら放出する方法です。
なお、1975年に「ロンドン条約」という国際的な約束事ができ、1982年以降、「海洋投棄」は行われていません。
海洋処分とは

– 海洋処分とは原子力発電は、私たちに欠かせない電力を安定して供給してくれる一方、放射線を出す物質である「放射性廃棄物」が発生します。この放射性廃棄物は、その放射線の強さや性質に応じて、適切に管理し、最終的には人間社会から隔離して処分する必要があります。このような中、過去に検討された処分方法の一つに「海洋処分」があります。海洋処分とは、放射性廃棄物をドラム缶などの容器に封入し、海底の地層や深い海溝に沈めて処分する方法です。広大な海は、放射性廃棄物を薄めて拡散させる力を持っているため、かつては最終的な処分場として有効な選択肢と考えられていました。 しかし、放射性廃棄物が海洋環境や生態系に及ぼす長期的な影響に関する懸念や、将来世代への影響に対する倫理的な問題などが浮上しました。海は地球全体の気候や生態系に大きな影響を与えており、一度汚染されると回復が難しいことから、国際社会全体で議論が重ねられました。 その結果、1993年には「ロンドン条約」と呼ばれる国際条約が改正され、放射性廃棄物を含む廃棄物の海洋投棄が全面的に禁止されました。現在では、海洋処分は国際的に認められておらず、より安全で持続可能な陸上の処分方法の研究開発が進められています。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 海洋処分とは | 放射性廃棄物を容器に封入し、海底の地層や深い海溝に沈めて処分する方法 |
| メリット | 広大な海が放射性廃棄物を薄めて拡散させる |
| デメリット | – 海洋環境や生態系への長期的な影響への懸念 – 将来世代への影響 – 海の汚染は回復が難しい |
| 現状 | 1993年の「ロンドン条約」改正により海洋投棄が全面的に禁止され、国際的に認められていない |
海洋処分の二つの方法
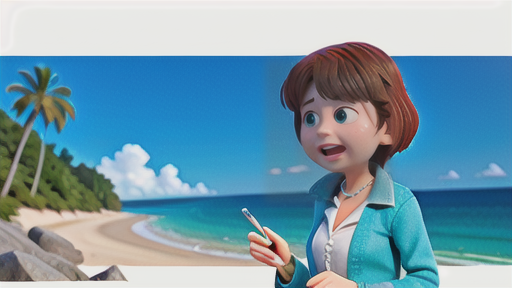
海への放射性廃棄物の処分方法には、『海洋投棄』と『沿岸放出』の二つの方法がありました。
『海洋投棄』は、放射性廃棄物をセメントなどで固め、ドラム缶に詰めてコンクリートで覆った後、水深4,000メートル以上の深海に沈める方法です。放射性物質を封じ込めた固化体が海底に沈んでいく過程で、海水に接触することでわずかに放射性物質が溶け出す可能性はありますが、広大な海洋で拡散し、薄まるため、人体や環境への影響は無視できると考えられていました。
一方、『沿岸放出』は、原子力施設などから発生する放射性物質を含む廃液を、国の基準値以下に薄めてから、沿岸海域に放出する方法です。薄められた廃液は、海流によって拡散し、さらに時間をかけて薄まっていきます。これは、環境中にもともと存在する自然放射線レベル以下になるように管理されていたため、人体や環境への影響は極めて低いと考えられていました。
しかしながら、これらの方法は、現在では国際条約によって禁止されています。これは、将来にわたって海洋環境と人間の健康を守るためです。
| 処分方法 | 内容 | 影響 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 海洋投棄 | 放射性廃棄物をドラム缶に入れ、コンクリートで覆って水深4,000m以上の深海に沈める | 広大な海洋で拡散し、薄まるため、人体や環境への影響は無視できると考えられていた | 現在、国際条約で禁止 |
| 沿岸放出 | 放射性物質を含む廃液を国の基準値以下に薄めてから、沿岸海域に放出する | 環境中にもともと存在する自然放射線レベル以下になるように管理されていたため、人体や環境への影響は極めて低いと考えられていた | 現在、国際条約で禁止 |
海洋投棄の実際

– 海洋投棄の実際
原子力発電所から発生する放射性廃棄物は、環境や人体への影響を最小限に抑えるため、厳重に管理され処理されます。過去には、海洋投棄と呼ばれる方法で処理が行われていました。
この方法では、まず放射性廃棄物をセメントやアスファルトなどで固化し、ドラム缶に詰め込みます。これは、放射性物質が容易に環境中に漏れ出すことを防ぐための対策です。そして、このドラム缶を海底深くまで運び、慎重に沈めていました。
海底は、人間の生活圏から遠く離れているため、放射性物質の影響が直接的に及ぶ可能性は低いと考えられていました。また、固化体の周囲を海水が覆うことで、放射線が遮蔽される効果も期待されていました。さらに、放射性物質が自然に崩壊するまでの時間を稼ぐことで、環境への影響を軽減できると考えられていました。
しかし、この海洋投棄には、長期的な安全性の確保や海底生態系への影響など、解決すべき課題が多くありました。例えば、固化体が長期間にわたって海水にさらされることで、腐食したり破損したりする可能性があります。また、海底の地殻変動や海底生物の影響を受ける可能性も否定できません。これらの懸念から、現在では、海洋投棄は国際条約によって禁止されています。
| 海洋投棄の方法 | メリット | デメリット・懸念点 |
|---|---|---|
| 放射性廃棄物を固化し、ドラム缶に詰めて海底に沈める | – 人間の生活圏から離れているため、影響は少ないと考えられていた – 海水による放射線遮蔽効果 – 放射性物質の自然崩壊までの時間稼ぎ |
– 長期的な安全性の確保 – 固化体の腐食・破損の可能性 – 海底生態系への影響 – 海底の地殻変動の影響 – 現在、国際条約により禁止 |
沿岸放出の管理

– 沿岸放出の管理沿岸放出とは、原子力発電所などで発生する放射性物質を含む水を、安全なレベルまで処理した後に、海へ放出することです。この処理では、まず放射性物質を可能な限り除去します。そして、国の定める安全基準を満たすまで海水で薄めてから、沿岸海域へ放出します。海には、広大な面積と常に動いている流れがあるため、放出された放射性物質は拡散し、急速に薄まります。 この拡散と希釈の効果によって、放射性物質の濃度は環境基準値よりもはるかに低いレベルに保たれます。しかし、沿岸放出を行うには、海洋環境の継続的な監視と生態系への影響評価が欠かせません。 放出する水の放射性物質の濃度を常に監視し、周辺海域の海水、海底の土、そして海の生物への影響を定期的に調査する必要があります。万が一、環境への影響が懸念される場合は、速やかに放出を停止し、適切な対策を講じなければなりません。このように、沿岸放出は、安全性確保のための徹底した管理と責任ある運用が求められる方法です。
| プロセス | 詳細 | 安全対策 |
|---|---|---|
| 放射性物質の除去 | 可能な限り放射性物質を除去する | – |
| 海水による希釈 | 国の安全基準を満たすまで海水で薄める | – |
| 沿岸放出 | 処理水を沿岸海域へ放出する。海の広さと流れによって拡散・希釈される。 | – |
| 海洋環境の監視 | – 放出する水の放射性物質濃度の監視 – 周辺海域の海水、海底の土、海の生物への影響調査 |
環境への影響が懸念される場合は、放出を停止し対策を講じる |
海洋処分と国際条約

地球全体の環境保全への意識が高まる中、1972年に採択されたロンドン条約は、海洋への廃棄物投棄に対する規制を強化する画期的なものでした。この条約は、海洋が人類にとってかけがえのない資源であり、その汚染は取り返しのつかない影響を及ぼすという認識に基づいていました。
その後、国際社会の連携はさらに進み、1993年の条約改正によって、海洋投棄は原則禁止となりました。これは、海洋がすべての国の共有財産であるという考え方が世界的に広まり、将来世代に美しい海を残していくべきだという共通認識が形成された結果と言えるでしょう。
日本もこの条約の精神に賛同し、批准国として国内法を整備することで、海洋環境保護に積極的に取り組んでいます。具体的な取り組みとしては、廃棄物の陸上処理の推進や、海洋汚染のモニタリングなどが挙げられます。
このように、国際条約と各国の努力によって、海洋環境は守られています。しかし、依然として違法な投棄や事故による汚染のリスクは存在するため、国際協力と技術革新を通じた、より一層の取り組みが必要とされています。
| 年 | 出来事 | 内容 |
|---|---|---|
| 1972年 | ロンドン条約採択 | 海洋への廃棄物投棄に対する規制強化 |
| 1993年 | ロンドン条約改正 | 海洋投棄の原則禁止 |
