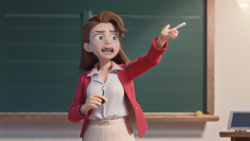その他
その他 未分化癌:診断が難しい癌の種類について
- 未分化癌とは未分化癌は、癌細胞が元の細胞の特徴をほとんど、あるいは全く示さない特殊な癌です。通常、癌は発生源となった臓器の細胞の特徴をある程度残しているため、顕微鏡で観察することで、胃癌、肺癌など、ある程度起源を特定することができます。しかし、未分化癌の場合、顕微鏡で観察しても、細胞は本来持つべき組織構造や形態を持たず、バラバラに増殖しているように見えます。この未分化性のために、細胞の起源を特定することが非常に困難です。つまり、どこの臓器から発生した癌なのかが分かりにくいため、診断や治療方針の決定が難しく、課題が多い癌と言えます。さらに、未分化癌は一般的に増殖が早く、転移しやすい傾向があります。これは、細胞が未分化であるために、正常な細胞のように周囲の組織と連携して増殖を抑制することができず、制御不能な状態になっているためと考えられています。未分化癌の診断には、病理組織検査や画像検査などが用いられますが、確定診断には、細胞の起源を特定するための免疫染色検査などが追加で行われることもあります。治療法としては、手術、放射線療法、化学療法などがありますが、最適な治療法は、患者の状態や癌の進行度などによって異なります。