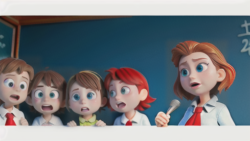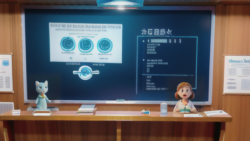放射線について
放射線について 放射線と腸の関係:陰窩細胞の重要性
私たちの腸は、食べたものから栄養を吸収するという大切な役割を担っています。その吸収効率を高めるために、腸の内壁は絨毛と呼ばれる小さな突起で覆われています。絨毛は、まるでビロードの布のようにびっしりと生えており、これにより腸の内壁の表面積は大きく広がっています。
この絨毛の表面を覆っているのが、腸上皮細胞と呼ばれる細胞です。腸上皮細胞は、栄養の吸収を担うだけでなく、体内に侵入しようとする細菌やウイルスなどの病原体から体を守るという、重要な役割も担っています。
しかし、腸上皮細胞は、常に食べ物や病原体に触れているため、傷つきやすく寿命が短いという特徴があります。そこで、腸は常に新しい細胞を作り出し、古い細胞と入れ替えることで、その機能を維持しています。
新しい腸上皮細胞は、絨毛の根元にある腸陰窩と呼ばれる場所で生まれます。腸陰窩には、活発に分裂する腸陰窩上皮細胞が存在し、これが新しい細胞の供給源となっています。生まれたばかりの細胞は、成熟しながら絨毛の先端に向かって移動し、最終的には古い細胞と入れ替わり、体外へ排出されます。
このように、腸は常に細胞を新しく作り替えながら、私たちの健康を支えています。