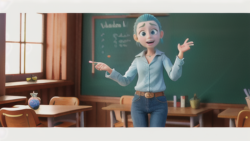原子力の安全
原子力の安全 地層処分:放射性廃棄物の未来へのタイムカプセル
地球温暖化対策として、二酸化炭素を排出しない原子力発電に期待が高まっていますが、一方で、放射能を持つ廃棄物の処理は、解決すべき重要な課題として認識されています。放射性廃棄物は、その放射能のレベルや性質によって分類され、それぞれに適した処理方法が検討されています。
放射能のレベルが高い高レベル放射性廃棄物は、ガラス固化体という安定した状態に加工した後、地下深くの地層に最終的に処分する方法が国際的に有力視されています。地下深くに埋設することで、人間の生活圏から長期間にわたって隔離し、環境への影響を最小限にすることを目指しています。
放射能のレベルが低い低レベル放射性廃棄物は、セメントなどで固化処理した後、適切な管理施設で保管されます。これらの施設では、厳重な監視体制のもと、環境への影響がないよう管理されます。
放射性廃棄物の処理は、将来世代に負担を残さないように、安全を最優先に進める必要があります。そのためには、国は、国民への丁寧な情報提供と対話を重ね、国民の理解と協力を得ながら、処分方法や処分場所の選定を進めていくことが重要です。